デューデリジェンスで発覚した「想定外の問題」とその乗り越え方
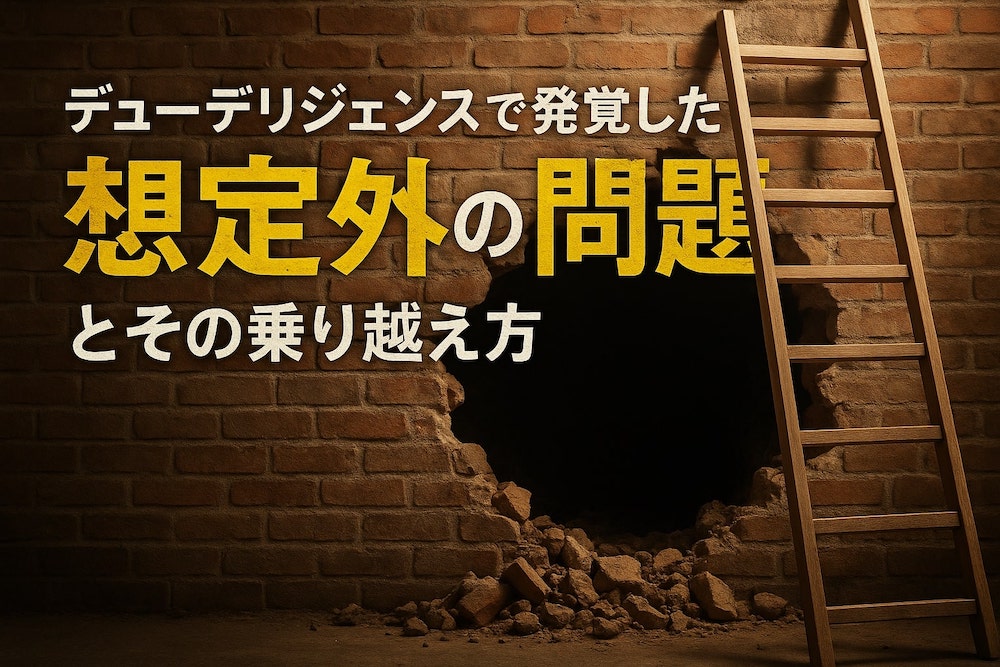
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの高橋健一です。
M&Aのプロセスにおいて、デューデリジェンス(DD)は避けて通れない重要な関門です。
買い手による詳細な調査の結果、自社でも把握していなかった「想定外の問題」が発覚し、交渉が暗礁に乗り上げてしまうのではないか。
多くの経営者が、そうした不安を抱えていらっしゃいます。
しかし、断言します。
DDにおける問題発覚は、決してM&Aの終わりを意味するものではありません。
むしろ、それは自社の真の姿を買い手と共有し、双方が納得できる条件を見出すための「交渉のスタートライン」なのです。
本記事では、私がこれまで数多く手掛けてきた経験、特に5億円規模のM&Aで散見されるDDでの問題点と、それを乗り越え「納得感のあるM&A」を実現するための具体的な思考法と対処法を、売り手経営者の視点から徹底的に解説します。
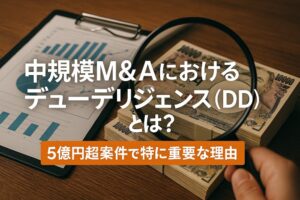
そもそもデューデリジェンス(DD)とは?– 経営者が知るべき本質
DDは「あら探し」ではなく「相互理解のプロセス」
まず、デューデリジェンスの本質を正しく理解することが重要です。
DDは、買い手による「あら探し」だと誤解されがちですが、その目的は全く異なります。
【用語解説】デューデリジェンス(Due Diligence: DD)
買収監査のこと。買い手がM&A対象企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセス。財務・法務・人事・事業・ITなど、多岐にわたる分野で実施される。
DDの真の目的は、買い手が企業の価値やリスクを正しく理解し、M&A後の統合プロセス〈PMI: Post Merger Integration〉を円滑に進めるための情報収集にあります。
言わば、企業の「健康診断」のようなものです。
精密な検査を通じて企業の現状を正しく把握することで、初めて適切な治療方針〈=M&A後の経営戦略〉を立てられるのです。
これは売り手にとっても、自社の強みや課題を第三者の客観的な視点で再認識する、またとない機会となります。
なぜ5億円規模のM&AでDDが重要なのか
では、なぜ特に企業価値5億円規模の中小企業M&Aで、DDがこれほどまでに重要視されるのでしょうか。
その理由は、この規模の企業の多くがオーナー経営であり、経営と所有が一体化している点にあります。
私の父も中小企業を経営していましたが、まさに公私の区別が曖昧な部分がありました。
例えば、節税を意識した会計処理、社長個人の資産と会社の資産の混同、整備されていない社内規程などです。
これらは日常の経営では問題にならなくても、M&Aという第三者の厳しい目が入る局面では、将来のリスクとして顕在化します。
買い手は、これらのリスクを正確に把握し、買収価格に織り込むために、徹底したDDを行うのです。
【分野別】DDで発覚しがちな「想定外の問題」とその背景
私がM&Aの現場で見てきた中で、特に発覚しやすい「想定外の問題」を分野別にご紹介します。
財務・税務:「見えない負債」が最も多い論点
財務DDで最も多く指摘されるのが「簿外債務」〈=貸借対照表に計上されていない債務〉の存在です。
代表的な例が「未払い残業代」です。
長年の慣行でサービス残業が常態化している場合、M&Aを機に従業員から過去に遡って請求されるリスクがあります。
これは買い手にとって想定外のコストとなるため、非常に厳しくチェックされるポイントです。
その他にも、
- 賞与・退職給付引当金の計上漏れ
- 経営者が会社の債務を個人的に保証している「債務保証」
- 実態と異なる在庫の過大評価
- 過去の税務申告の誤り
などが挙げられます。
これらは悪意なく行われた節税対策が、結果として会計基準とのズレを生んでいるケースがほとんどです。
法務:「契約書一枚」が命取りになるリスク
法務DDでは、過去の契約書が将来の事業継続性を揺るがすリスクとして浮かび上がることがあります。
特に注意が必要なのが「チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項」です。
【用語解説】チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項
会社の支配権(経営権)に重要な変更があった場合に、契約の相手方が契約を解除したり、事前の通知や承諾を要求したりできる権利を定めた条項。
ある老舗の部品メーカーのケースでは、最大の取引先との基本契約書にこのCOC条項が含まれていました。
M&Aによって経営権が移ることを理由に、その取引先から契約を打ち切られる可能性が浮上し、交渉は一時中断。
買い手が期待していた収益の前提が、根底から覆されかねない事態でした。
その他にも、事業に必要な許認可の承継がスムーズにいくか、自社製品の特許権の帰属が明確か、といった点が厳しく問われます。
「あの件は口約束で大丈夫だから」という長年の信頼関係が、M&Aの局面では通用しないのです。
人事・労務:「人」にまつわる根深い課題
企業の最大の資産は「人」ですが、同時に人事・労務は根深い課題を抱えていることが多い分野です。
最も懸念されるのが「キーパーソンの離職リスク」です。
社長の右腕として活躍してきた工場長や、トップセールスマンが、M&Aを機に「新しい会社ではやっていけない」と離職してしまえば、事業の根幹が揺らぎます。
また、労働関連法規の遵守状況も重要です。
- サービス残業の常態化
- 36協定の未締結・不備
- 従業員との雇用契約書が未整備
これらの法令違反は、買い手にとって是正コストや訴訟リスクを意味し、企業価値を大きく損なう要因となります。
事業・IT:ビジネスモデルの脆弱性
財務諸表には直接現れにくいものの、将来の収益性を左右するのが事業モデルそのものの脆弱性です。
例えば、
- 特定の大口取引先への過度な依存(売上の50%以上を1社に依存しているなど)
- 老朽化したITシステムや、特定の担当者しか使えない「属人化」した業務フロー
- 市場の変化に対応できていない旧式のビジネスモデル
これらは、買い手がM&A後の成長戦略を描く上で、大きな障害となり得ます。
「うちはこのやり方でずっとやってきた」という自負が、客観的にはリスクと評価されることもあるのです。
問題発覚!その時、売り手経営者が取るべき3つのステップ
では、実際にDDで問題が指摘された時、経営者はどう行動すべきでしょうか。
パニックに陥らず、以下の3つのステップで冷静に対処することが肝要です。
ステップ1:冷静な事実確認と影響の分析
まず何よりも重要なのは、感情的にならず、指摘された問題を客観的な事実として受け止めることです。
「そんなはずはない」「あら探しばかりしやがって」という気持ちは痛いほど分かります。
しかし、その感情は一旦脇に置き、まずは事実関係を正確に確認しましょう。
そして、仲介会社やFA、弁護士、会計士といった専門家チームと連携し、その問題が将来にわたって企業価値にどの程度の金銭的影響を与えるのかを冷静に分析します。
例えば、「未払い残業代」であれば、最大でいくらの支払い義務が発生しうるのかを試算するのです。
ステップ2:専門家チームとの戦略会議
問題の性質が明らかになったら、次は専門家チームとの戦略会議です。
ここで経営者自身が主体的に関わることが極めて重要になります。
- 法務の問題(契約書、許認可など) → M&Aに強い弁護士
- 財務・税務の問題(簿外債務、会計処理など) → 公認会計士・税理士
- 人事・労務の問題(未払い残業代、労務規程など) → 社会保険労務士
問題の種類に応じて、どの専門家に主導してもらい、どのような役割を期待するのかを明確にします。
仲介会社やFAに任せきりにするのではなく、自らが司令塔となって専門家を使いこなすという気概が、交渉を有利に進める上で不可欠です。
ステップ3:誠実な情報開示と交渉戦略の立案
問題を隠蔽することは、最悪の選択です。
発覚した際に関係が崩壊するだけでなく、表明保証違反として法的な責任を問われる可能性もあります。
重要なのは、分析した事実関係と、こちらが考える対応策をセットで、誠実に買い手へ開示することです。
その上で、次に解説するような具体的な解決策を交渉のテーブルに乗せ、自社にとっての最善の落としどころを探っていくのです。
この誠実な姿勢こそが、買い手との信頼関係を再構築する第一歩となります。
具体的な「乗り越え方」の選択肢 – 交渉の武器を知る
問題が発覚した後、交渉を妥結に導くための具体的な「武器」が存在します。
代表的なものを4つご紹介します。
① 価格調整(ディールプライスの減額)
最もシンプルで一般的な解決策です。
DDで発覚した問題に起因する将来の損失額や、問題を是正するために必要なコストを合理的に算出し、その分を買収価格から減額します。
例えば、簿外債務が1,000万円あると判明した場合、買収価格を1,000万円引き下げる、といった交渉です。
② 表明保証(表明した事実を保証する)
これは、売り手が「DDで開示した情報が真実であり、例えば未開示の簿外債務などは存在しません」と最終契約書で保証するものです。
万が一、M&A成立後に保証した内容に反する事実が発覚した場合、売り手は契約で定めた上限額や期間の範囲内で、買い手が被った損害を補償する責任を負います。
これにより、買い手は潜在的なリスクをヘッジできます。
売り手としては、補償の上限額や期間をいかに限定するか、が交渉のポイントになります。
③ アーンアウト条項(将来の業績達成で追加支払い)
事業計画の達成可能性について、売り手と買い手の見解が大きく異なる場合に用いられる手法です。
まず、M&A成立時点では最低限の対価を支払い、その後1〜3年程度の期間内に、事前に定めた売上や利益などの業績目標を達成した場合、追加の対価が支払われる仕組みです。
売り手にとっては自社の成長性を証明して最終的により多くの対価を得るチャンスがあり、買い手にとっては買収リスクを低減できるメリットがあります。
ただし、売り手は対価の全額をすぐに受け取れない点に注意が必要です。
④ M&Aスキームの変更(事業譲渡への切り替え)
会社全体を丸ごと売買する「株式譲渡」ではなく、問題のある部分を切り離し、必要な事業や資産だけを売買する「事業譲渡」にスキームを変更する選択肢です。
例えば、特定の工場に土壌汚染のリスクが発覚した場合、その工場を除いた形で事業譲渡を行う、といったケースです。
これにより、買い手は不要なリスクを引き継がずに済み、ディールを前に進めることが可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q: DDで問題が指摘されたら、M&Aは破談になってしまうのですか?
A: 必ずしもそうではありません。
むしろ、ほとんどのM&Aで何らかの問題は発覚します。
重要なのは、その問題の深刻度と、売り手・買い手双方が納得できる解決策を見つけられるかです。
本記事で解説したような手法を駆使し、誠実な対応と建設的な交渉を行うことができれば、乗り越えられるケースがほとんどです。
Q: 買い手から過大な減額要求をされています。どう対応すれば良いですか?
A: まずは減額の根拠を明確に、書面で提示してもらいましょう。
その上で、公認会計士や弁護士などの専門家と共に、要求額の妥当性を客観的に評価します。
例えば「未払い残業代リスクとして3,000万円減額」という要求に対し、こちらの試算では最大でも500万円程度である、といった具体的な反論材料を準備します。
不合理な点については、毅然とした態度で論理的に反論することが重要です。
Q: 簿外債務の存在を、DDが始まる前に自ら開示するべきでしょうか?
A: 非常に悩ましい問題ですが、私の意見としては「信頼できる専門家に相談の上、適切なタイミングと方法で誠実に開示すること」を推奨します。
意図的に隠すことは、後で発覚した場合に買い手との信頼関係を著しく損ない、表明保証違反などでより大きな問題になりかねません。
事前にリスクを開示することで、誠実な経営者であるという印象を与え、交渉を有利に進められる可能性すらあります。
Q: DDの費用は誰が負担するのですか?
A: DDにかかる費用は、調査を依頼する買い手側が負担するのが一般的です。
ただし、売り手側も、指摘事項への対応や膨大な資料準備などで、多くの時間的・人的コストがかかることは認識しておく必要があります。
また、指摘事項の分析のために売り手側で弁護士や会計士に依頼すれば、その費用は当然売り手負担となります。
Q: 専門家に相談したいのですが、どのタイミングで誰に相談すれば良いですか?
A: M&Aを検討し始めた初期段階で、私のような特定の金融機関や仲介会社に属さない、中立的な立場のコンサルタントに一度相談し、全体像と潜在的なリスクを把握することをお勧めします。
その上で、DDで具体的な問題が指摘された際は、その内容に応じて弁護士(法務)、公認会計士(財務・税務)、社会保険労務士(労務)など、その分野のトップクラスの専門家と連携して対処していくのが最善の策です。
まとめ
デューデリジェンスで想定外の問題が発覚することは、M&Aのプロセスにおいて日常茶飯事です。
重要なのは、それをパニックや絶望の種と捉えるのではなく、自社と真摯に向き合い、買い手との相互理解を深める絶好の機会とすることです。
問題の本質を冷静に分析し、信頼できる専門家チームと連携しながら、誠実な対話を通じて解決策を探る。
このプロセスこそが、単なる売買取引を超えた「納得感のあるM&A」の実現に繋がります。
人生の大きな決断に臨む経営者の皆様にとって、本記事で解説した視点と具体的な対処法が、荒波を乗り越えるための羅針盤となることを心から願っています。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。


