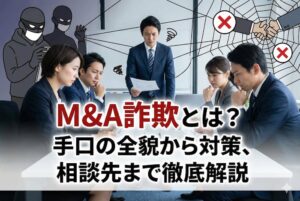中規模M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)とは?5億円超案件で特に重要な理由
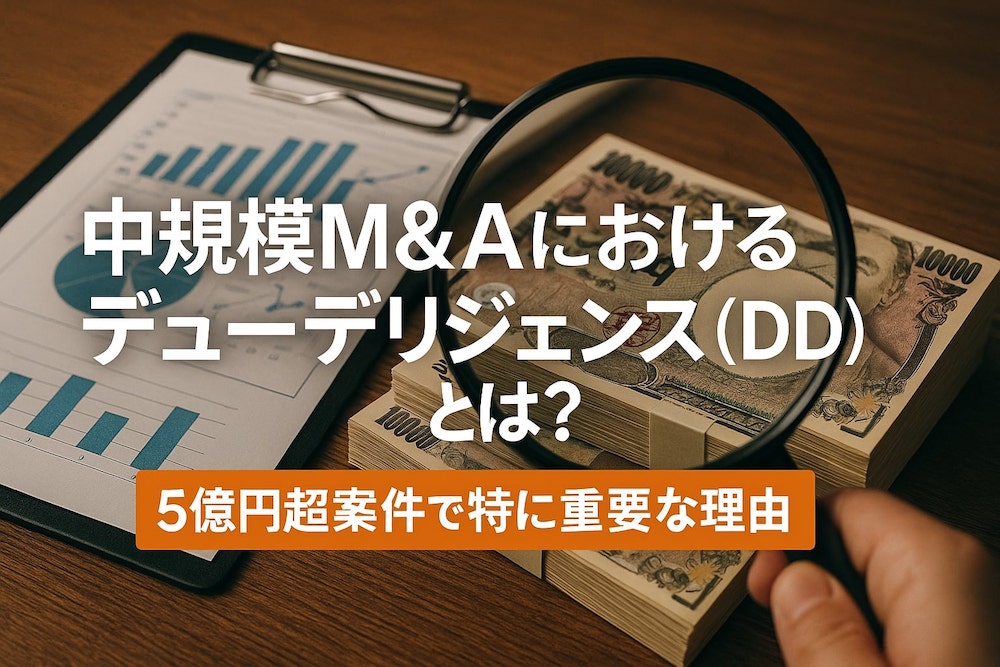
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの高橋 健一です。
M&Aのプロセスが進行し、買い手候補との基本合意に至った後、経営者の皆様が向き合うことになるのが「デューデリジェンス(DD)」です。
日本語では「買収監査」と訳されるため、「企業の隅々まで調査され、粗探しをされるのではないか」「何か問題が見つかったら破談になるのでは」と不安を感じる方も少なくありません。
しかし、DDは決してネガティブなプロセスではありません。
これは、自社の価値を客観的に評価してもらい、買い手との信頼関係を築くための重要な機会なのです。
特に、取引金額が5億円を超える中規模M&Aにおいては、その重要性が飛躍的に高まります。
本記事では、私が多くの経営者様を支援してきた経験に基づき、DDの本質、5億円超の案件で特に重要となる理由、そして売り手経営者としてどう向き合い、準備すべきかを、特定の専門家の立場に偏らない中立的な視点から徹底的に解説します。
そもそもデューデリジェンス(DD)とは何か?
DDは「粗探し」ではなく「企業の健康診断」
では、デューデリジェンスとは、具体的に何を指すのでしょうか。
DDとは、買い手がM&Aを実行するにあたり、対象企業の価値やリスクを適正に把握するために行う調査活動全般を指します。
これは、買い手にとっては当然の権利であり、合理的な投資判断を行うために不可欠なプロセスです。
売り手の経営者様にとっては、自社の強みや課題を客観的なデータで示し、買い手に正しく会社を理解してもらうための「企業の健康診断」と捉えるのが最も実態に近いでしょう。
このように、DDはM&Aの後半、基本合意と最終契約の間で行われる重要なステップなのです。
DDの結果がM&Aに与える影響
DDの結果は、その後のM&Aの行方を大きく左右します。
調査で発見された事項は、最終的な譲渡価格の調整(減額)や、契約条件の見直しに繋がることがあります。
場合によっては、M&Aのスキーム〈※手法。株式譲渡や事業譲渡など〉の変更や、最悪の場合、取引の中止(ディールブレイク)に至る可能性もゼロではありません。
だからこそ、DDに対して誠実に向き合い、適切に準備することが、M&Aの成功に直結するのです。
なぜ「5億円超」のM&AでDDは特に重要になるのか?
取引規模が大きくなるほど、DDの重要性は増していきます。
私が「M&A 5億の扉」の専門家として関わる案件でも、この傾向は顕著です。
その理由は、主に4つあります。
理由1:取引金額の大きさがもたらすリスクの増大
第一に、投資の失敗が許されない金額になるからです。
5億円という金額は、多くの買い手企業にとって、会社の将来を左右しかねない大規模な投資です。
そのため、投資判断の精度を極限まで高めるべく、より慎重で、広く、深い、網羅的なDDが実施される傾向にあります。
買い手の立場からすれば、金額が大きくなるほど、わずかな見落としが将来的に巨額の損失に繋がるリスクを警戒します。
M&Aを駅伝のタスキリレーに例えるなら、DDは次の走者(買い手)が安心して走り出せるよう、タスキ(会社)の状態を徹底的に確認する作業と言えるでしょう。
理由2:経営の複雑性と潜在リスクの顕在化
第二に、事業規模に比例して、潜在的なリスクが複雑化・増加するためです。
企業価値が5億円を超える規模になると、個人経営的な状態から組織的な経営へと移行しているケースが多くなります。
それに伴い、財務諸表には直接現れないリスクが格段に増加します。
- 簿外債務:会計帳簿に記載されていない債務。未払い残業代や退職給付引当金の不足などが典型例です。
- 偶発債務:現時点では債務ではないが、将来特定の条件が満たされると債務になる可能性のあるもの。過去の取引に関する訴訟リスクや、他社の債務保証などが該当します。
私が担当したある製造業のケースでは、DDの過程で過去の製品に対する損害賠償請求のリスクが発覚し、最終価格に影響を与えました。
こうした潜在リスクは、DDという「健康診断」によってはじめて顕在化することが多いのです。
理由3:属人的経営からの脱却と事業継続性の検証
第三の理由は、事業の「再現性」が厳しく問われるからです。
この規模の企業では、依然として創業者や特定の役員・従業員への依存度が高い、いわゆる「属人的経営」のケースが散見されます。
買い手が最も懸念することの一つは、「キーパーソンが退職した後も、この事業は本当に回っていくのか?」という点です。
ビジネスDDでは、この事業継続性(再現性)が厳しく評価されます。
- 組織体制は整っているか?
- 業務はマニュアル化されているか?
- 特定の営業担当者に顧客が集中していないか?
これらの点が、M&A後の事業計画を左右する重要な論点となります。
理由4:売り手経営者の「納得感」ある着地のために
最後に、これは売り手経営者様にとって非常に重要な点です。
DDは、ご自身の「納得感」を醸成するプロセスでもあります。
DDを通じて、自社の強みと弱みが、会計士や弁護士といった専門家の客観的な視点で評価されます。
これにより、最終的に提示される譲渡価格や契約条件に対して、「なぜこの評価になったのか」という根拠が明確になります。
DDは、ご自身が人生をかけて築き上げてきた会社の価値を、買い手に正しく、論理的に伝えるための最終プレゼンテーションの場でもあるのです。
このプロセスを真摯に経ることで、単なる金額以上の「納得感」を持って、大切な会社を次の担い手に託すことができるようになります。
DDの主な種類と「経営者は何を見られるか」
では、具体的にどのような「健康診断」が行われるのでしょうか。
DDは多岐にわたりますが、ここでは主要なものをご紹介します。
財務DD:会社の財産と収益力は正しいか
公認会計士や税理士が担当し、決算書の数字の裏付けを取る調査です。
- 決算書の内容は正確か、粉飾はないか
- 異常な取引や、役員との不透明な資金移動はないか
- 将来の収益計画に妥当性はあるか
経営者としては、過去の会計処理の根拠や、特定の年度だけ利益が突出している理由などを、明確に説明できる準備が求められます。
法務DD:法的な地雷は埋まっていないか
弁護士が担当し、法的なリスクを洗い出します。
- 定款や株主総会議事録は適切に作成・保管されているか
- 顧客や取引先との契約書に不利な条項はないか
- 事業に必要な許認可は正しく取得・更新されているか
- 潜在的な訴訟リスクはないか
特に中小企業で見落としがちなのが、株式の所在(名義株など)や契約書の不備です。
これらはディールブレイクに直結しかねない重大な問題となることがあります。
ビジネスDD:事業の将来性と競争力はあるか
M&Aアドバイザーや経営コンサルタントが担当します。
- 事業モデルの強みと弱みは何か
- 市場におけるポジションやシェアはどうか
- 競合他社との差別化要因は何か
- 顧客基盤は安定的か
ここは、買い手が最も知りたい「M&Aによってどのような相乗効果(シナジー)が期待できるか」を伝える重要な機会です。
自社の事業の魅力を、客観的なデータと共にアピールする場となります。
その他(人事・ITなど)のDD
企業の特性に応じて、追加のDDが行われることもあります。
- 人事DD → 従業員の労働条件や未払い残業代などの労務リスクを調査します。
- IT DD → 基幹システムが古すぎないか、情報セキュリティ体制は万全かなどを調査します。
これらの調査を通じて、買い手は企業の全体像を立体的に把握していくのです。
【売り手の心得】DDを乗り切るための3つの準備
ここまで読んで、「準備が大変そうだ」と感じられたかもしれません。
しかし、ポイントを押さえれば、過度に恐れる必要はありません。ここでは、DDを乗り切るための3つの準備をご紹介します。
心構え:誠実な情報開示が信頼を生む
最も重要なのは、誠実な姿勢です。
自社にとって不利な情報であっても、隠したり、ごまかしたりせずに正直に開示してください。
不利な情報を早い段階で開示することは、買い手との信頼関係を築く上で不可欠です。
もし後から隠していた事実が発覚した場合、買い手からの信頼を失うだけでなく、「表明保証違反」として損害賠償を請求されるリスクさえあります。
「情報こそが経営者の武器」ですが、それは誠実さとセットであって初めて意味をなすのです。
資料準備:先を見越した資料整理を
次に、物理的な準備です。
DDでは膨大な資料の提出を求められます。
事前に準備を進めておくことで、DDのプロセスをスムーズに進めることができます。
- 決算書・税務申告書(過去3〜5期分)
- 月次試算表
- 重要な契約書一覧(賃貸借、リース、販売代理店契約など)
- 従業員名簿、就業規則、賃金台帳
- 許認可証、登記簿謄本
- 株主名簿、議事録一式
近年では、これらの資料を「VDR(仮想データルーム)」〈※オンライン上で安全に情報を共有するためのプラットフォーム〉にアップロードして共有するのが一般的です。
早めに専門家と相談し、資料の整理に着手しましょう。
専門家との連携:一人で抱え込まない
最後に、決して一人で抱え込まないでください。
DDの質問は、財務・法務・税務・ビジネスと多岐にわたり、その一つ一つが専門的です。
信頼できるM&Aアドバイザーや顧問税理士、弁護士と事前に連携し、想定される質問や論点を整理しておくことが極めて重要です。
専門的な質問には専門家が対応する体制を整えることで、経営者であるあなたは、本来注力すべき「最終的な経営判断」に集中することができます。
よくある質問(FAQ)
Q: DDの費用は誰が負担するのですか?
A: 原則として、DDを依頼する買い手側がその費用を全額負担します。
ただし、売り手側が交渉を有利に進めるためなどに、事前に自社の状況を把握する「セルサイドDD」を行う場合は、その費用は売り手が負担します。
Q: DDの期間はどれくらいかかりますか?
A: 対象企業の規模や調査範囲によりますが、5億円規模のM&Aの場合、一般的には1ヶ月〜2ヶ月程度です。
この期間、売り手側は迅速な情報提供が求められるため、事前の資料準備が鍵となります。
Q: DDで問題が見つかったら、M&Aは必ず破談になりますか?
A: 必ずしも破談になるわけではありません。
発見されたリスクの重要度に応じて、①譲渡価格の減額交渉、②最終契約書に売り手の表明保証を追加する、③リスクを解消する具体的な措置を講じる、といった形で対応することが大半です。
もちろん、事業の根幹を揺るがすような重大な問題(ディールブレイカー)が発見された場合は、破談に至ることもあります。
Q: 顧問税理士にDDの対応をすべて任せても大丈夫ですか?
A: 重要なご質問です。
顧問税理士の先生は会社の経理・税務には精通していますが、M&AのDDは非常に特殊な知見を要します。
特に、法務DDやビジネスDDは専門外の領域です。
M&Aの経験が豊富なアドバイザーを司令塔とし、必要に応じて各分野の専門家(弁護士など)と連携して対応する「チーム体制」を組むことが、経営者様の利益を守る上で最も重要です。
Q: どこまで情報開示をすればよいのでしょうか?
A: 基本的には、買い手から合理的な範囲で要求された情報は、すべて誠実に開示する必要があります。
意図的に重要な情報を隠した場合、後に契約違反として損害賠償を請求されるリスクがあります。
どの情報をどこまで開示すべきか、範囲に不安がある場合は、必ずM&Aアドバイザーに相談してください。
まとめ
デューデリジェンスは、5億円を超える規模のM&Aを成功させるための避けては通れない、そして最も重要なプロセスの一つです。
それは単なる「監査」や「粗探し」ではありません。
自社の価値を買い手に正しく伝え、双方が納得できる条件で未来へ進むための「対話」の機会に他ならないのです。
経営者の皆様には、DDを過度に恐れることなく、誠実な姿勢で臨んでいただきたいと思います。
そのためには、信頼できる中立的な専門家をパートナーとして選び、早い段階から準備を進めることが不可欠です。
この記事が、皆様のM&Aという重要な決断の一助となり、納得感のある未来への扉を開くきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。