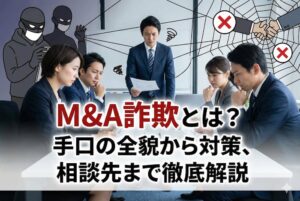M&Aの表明保証違反リスクにどう備える?表明保証保険の補償範囲と注意点
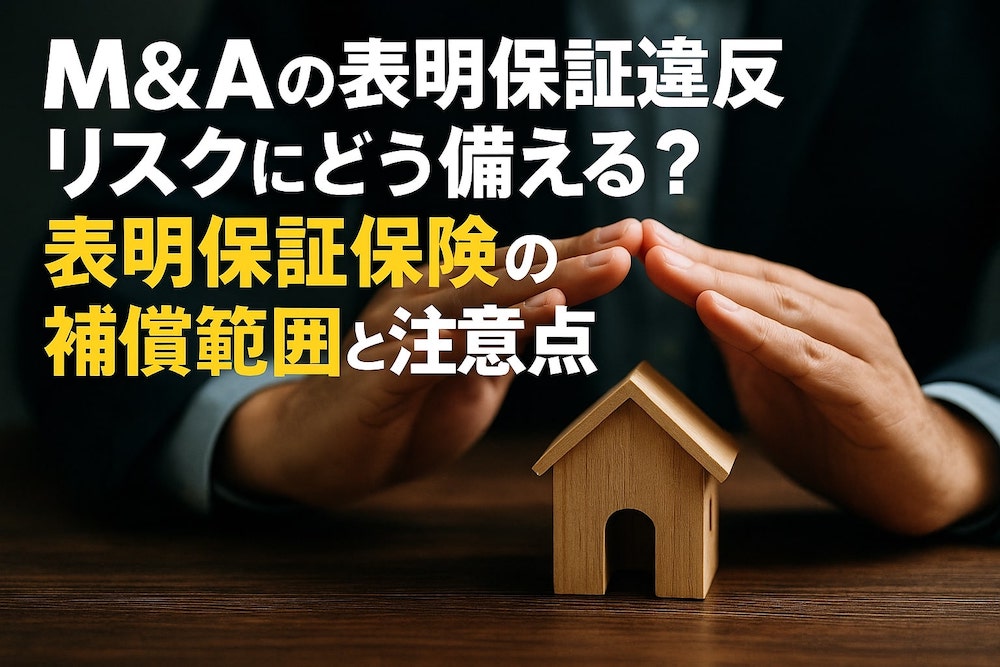
M&Aの最終契約段階で、多くの経営者が「表明保証」という見えにくいリスクに直面します。
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの高橋 健一です。
私は特定の金融機関や仲介会社に属さない立場から、これまで多くの経営者様のご相談に乗ってきました。
その中で特に多いのが、M&A成立後の「万が一」に対する不安です。
とりわけ売り手の経営者にとって、表明保証違反は、手にしたはずの会社売却代金を失いかねない、非常に深刻なリスクとなり得ます。
本記事では、このリスクから経営者を守るための選択肢である「表明保証保険」について、その仕組みから費用、そして企業価値5億円規模の中小M&Aにおける賢い活用法まで、完全に中立的な立場から徹底解説します。
そもそもM&Aの「表明保証」とは?売り手経営者が知るべき基本
ではまず、M&Aの交渉大詰めで必ず登場する「表明保証」とは一体何なのでしょうか。
なぜ「保証」が必要なのか?デューデリジェンスの限界
M&Aのプロセスでは、買い手側が売り手企業の価値やリスクを精査する「デューデリジェンス(DD)」〈買収監査〉を実施します。
しかし、DDは万能ではありません。
限られた時間と情報の中では、企業が抱えるすべてのリスクを洗い出すことは、現実的に不可能なのです。
金融機関時代、私もDDでは見抜けなかった問題がM&A成立後に発覚し、トラブルに発展するケースを目の当たりにしてきました。
そこで、このDDの限界を補完するために、売り手側が「私が開示した情報や会社の状況は、真実かつ正確です」と、買い手に対して法的に約束する、これが「表明保証」の役割です。
いわば、売り手経営者による“お墨付き”と言えるでしょう。
デューデリジェンスについては以下の記事もご覧ください。
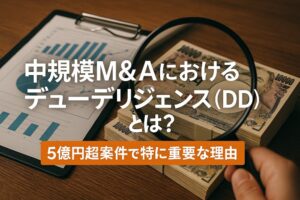
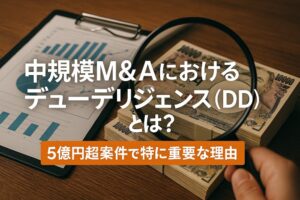
売り手経営者は何を「表明」し「保証」するのか?
では、具体的に何を表明し、保証する必要があるのでしょうか。
中小企業のM&Aで特に重要となる項目には、以下のようなものが挙げられます。
- 財務に関する事項:財務諸表が適正に作成されており、すべての負債が計上されていること(簿外債務の不存在)。
- 法務に関する事項:事業に必要な許認可を全て取得しており、法令違反がないこと。また、訴訟や紛争を抱えていないこと。
- 労務に関する事項:未払残業代が存在せず、従業員との間で重大な労務トラブルがないこと。
- 税務に関する事項:過去の税務申告が適正に行われており、追徴課税のリスクがないこと。
- 知的財産に関する事項:事業に必要な特許権や商標権を正当に保有しており、第三者の権利を侵害していないこと。
私がコンサルティングで特に注意を促すのは、「過去の慣習」に起因する見落としです。
例えば、先代から続く取引先との口約束や、長年なあなあにしてきたサービス残業など、悪意なくとも表明保証違反に該当しうる項目は、経営者が思う以上に潜んでいるものです。
表明保証違反が発覚した際の深刻なリスク
「もし表明保証違反が見つかったら、どうなるのか?」
これは経営者として最も気になるところでしょう。
そのリスクは、金銭的なものと精神的なものの双方に及びます。
損害賠償請求:手にした売却代金が奪われる可能性
表明保証違反が発覚した場合、買い手は売り手に対して、契約に基づき損害賠償や補償を請求できます。
例えば、私が過去に関わったケースに近い架空の事例を考えてみましょう。
【事例】製造業A社のケース
- M&A取引価額: 5億円
- 発覚した違反: M&A成立後、買い手が労務環境を精査したところ、過去3年間にわたる大規模な未払残業代(約3,000万円)の存在が発覚。
- 結果: 買い手は表明保証違反(労務に関する事項)を根拠に、売り手である元経営者に対し3,000万円の損害賠償を請求。元経営者は、引退後の生活資金として計画していた売却代金から、この賠償金を支払わざるを得なくなりました。
最悪の場合、M&Aで得た資金の大部分を失う可能性もゼロではないのです。
この金銭的リスクの大きさを、まず正しく認識することが重要です。
交渉の長期化と精神的負担
金銭的なダメージに加え、見落とされがちなのが精神的な負担です。
違反をめぐる買い手との交渉は、弁護士を交えた専門的かつ長期にわたるものになりがちです。
M&Aを終え、ようやく肩の荷が下りて新たな人生を歩み始めようとした矢先に、過去の会社の問題で再び心労を重ねることになる。
私の父も中小企業を経営していましたが、引退後は穏やかに過ごしてほしいと願うのが家族の想いでしょう。
この「見えないコスト」が、ハッピーリタイアを脅かす可能性があることも、ぜひ知っておいていただきたいと思います。
リスク対策の切り札「表明保証保険(R&W保険)」とは?
こうした深刻なリスクから売り手経営者を守るための有効な手段が、「表明保証保険(R&W保険)」です。
表明保証保険の基本的な仕組み
表明保証保険とは、その名の通り、M&A成立後に表明保証違反が発覚し、売り手が買い手に対して負うべき経済的な損害を補償してくれる保険商品です。
- M&A成立後に表明保証違反が発覚。
- 買い手が売り手(または保険会社)に損害賠償を請求。
- 売り手の代わりに、保険会社が買い手へ補償金を支払う。
この保険があることで、売り手は万が一の事態に備え、売却代金を差し押さえられるといったリスクを回避できるのです。
誰が加入し、誰が保険金を受け取るのか?
表明保証保険には、主に2つのタイプが存在します。
- 売り手用保険:売り手が保険に加入。買い手へ損害賠償を行った後、その金額を保険会社から受け取る。
- 買い手用保険:買い手が保険に加入。表明保証違反による損害が発生した場合、買い手が直接保険会社から保険金を受け取る。
近年の中小M&Aでは、交渉をスムーズに進めるため、買い手が費用を負担して「買い手用保険」に加入するケースが実務上は大半を占めています。
買い手にとっても、売り手の資力に関わらず確実に補償を受けられるメリットがあるためです。
【売り手・買い手別】表明保証保険のメリット・デメリットを徹底比較
では、この保険を活用することのメリットとデメリットを、売り手・買い手双方の視点から整理してみましょう。
売り手経営者のメリット:安心して会社を託せる「クリーンイグジット」
売り手にとっての最大のメリットは、M&A後の偶発的な損害賠償リスクから解放されることです。
これにより、手にした売却代金を、引退後の生活資金や次の事業への投資に、心置きなく充てることができます。
これを「クリーンイグジット」と呼びます。
また、表明保証違反リスクに備えて売買代金の一部を一定期間、第三者に預託する「エスクロー制度」の設定が不要になったり、条件が緩和されたりするケースもあります。
結果として、売却代金を早期に全額回収できる可能性も高まるのです。
買い手のメリット:交渉の円滑化とリスクヘッジ
一方、買い手にとっては、万が一の際に売り手の資力(支払い能力)を心配することなく、保険会社から確実に補償を確保できる点が大きな安心材料となります。
また、M&A後も事業運営のために元経営者との良好な関係を維持したい場合、個人に直接的な賠償請求をするという精神的なハードルを避けられるメリットもあります。
こうした買い手側のメリットが、結果として取引価格の減額要求を和らげるなど、交渉を有利に進める材料になることもあるのです。
共通のデメリットと注意点:保険料と免責事項
もちろん、良いことばかりではありません。
最大のデメリットは、当然ながら保険料というコストが発生する点です。
そして最も注意すべきは、すべての違反が補償されるわけではない、という事実です。
保険契約には必ず「免責事項」が存在します。
例えば、売り手が意図的に隠していた事実(詐欺)や、DDの段階で既に発覚していたリスクなどは、補償の対象外となるのが一般的です。
私は独立した立場だからこそ強調しますが、保険は万能薬ではありません。
「保険に入るから大丈夫」と安易に考えるのは禁物です。
気になる費用は?表明保証保険の保険料と手続きの流れ
「実際に保険を検討するとなると、費用はどれくらいかかるのか?」
これは最も現実的な疑問だと思います。
保険料の相場観:5億円規模のM&Aならいくらか?
一般的に、表明保証保険の保険料は、補償される上限金額の1%〜3%程度が目安とされています。
例えば、取引価額5億円のM&Aで、表明保証違反リスクに備えて補償上限額を1億円に設定したとしましょう。
この場合、保険料は 100万円〜300万円 程度がひとつの目安となります。
かつては最低保険料が1,000万円以上と、大企業向けの高額な商品しかありませんでした。
しかし近年は、M&A市場の裾野の広がりに伴い、中小企業向けに最低保険料を50万円程度からに設定した商品も登場しており、利用のハードルは着実に下がっています。
加入までの手続きと期間
保険加入の手続きは、M&Aの交渉プロセスと並行して進めるのが一般的です。
大まかな流れは以下の通りです。
- 概算見積もり依頼:M&Aアドバイザー等を通じて保険会社(または保険ブローカー)に打診。
- 引受審査:DD報告書や株式譲渡契約書のドラフトなどを提出し、保険会社がリスクを評価。
- 保険契約締結:補償内容や免責事項を交渉し、M&Aの最終契約と同時に保険契約も締結。
特に②の引受審査から契約交渉には、数週間から1ヶ月半程度 を要することがあります。
そのため、M&Aの最終段階になってから慌てて検討するのではなく、交渉の中盤、DDが始まったくらいのタイミングで検討を開始することをお勧めします。
中小M&Aの経営者が表明保証保険を検討すべき3つのケース
では、あなたの会社の場合、表明保証保険は検討に値するのでしょうか。
私がコンサルタントとして、特に保険の活用を積極的にお勧めする3つのケースをご紹介します。
ケース1:潜在的な簿外債務リスクが高い業種
DDだけでは把握しきれない偶発債務のリスクが、他の業種に比べて高いと想定される場合です。
例えば、以下のような業種・特徴を持つ企業が該当します。
- 労働集約型のサービス業:多数の従業員を抱え、未払残業代のリスクが潜在している。
- 建設業・不動産業:過去の施工に関する瑕疵担保責任や、土壌汚染のリスクがある。
- IT・ソフトウェア業:多数の外部委託先との契約関係が複雑で、知的財産権の侵害リスクがある。
こうしたリスクを経営者ご自身が懸念されている場合、保険は有効な選択肢となります。
ケース2:売却後の資金をすぐに活用したい場合
引退後の生活資金、ご家族への資産承継、あるいは新たな事業への挑戦など、M&Aで得た売却代金をすぐに確定させ、安心して活用したいというニーズが強い経営者には、保険は大きな精神的な安心をもたらします。
将来の賠償リスクに備えて、売却代金の一部を何年間も手を付けずに置いておく…という心理的な制約から解放される価値は、金銭以上に大きいかもしれません。
ケース3:買い手との交渉を有利に進めたい場合
これは少し戦略的な使い方です。
交渉の過程で、買い手側が表明保証違反のリスクを非常に強く懸念しているとします。
その結果、取引価格の大幅な減額を要求されたり、極端に厳しい補償上限額を求められたりして、交渉が膠着状態に陥ることがあります。
このような場面で、売り手側から「保険の活用」を提案するのです。
「保険料の一部をこちらで負担するので、この保険でリスクをカバーするのはどうだろうか」と持ちかけることで、買い手の不安を和らげ、交渉の突破口を開くことができます。
これは私が実際の現場でもアドバイスすることがある、実践的なテクニックの一つです。
よくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様からよくいただくご質問にお答えします。
Q: 表明保証保険に入れば、デューデリジェンスは手抜きでも大丈夫ですか?
A: いいえ、全く逆です。
保険会社は、買い手が質の高いデューデリジェンスを実施していることを、保険引受の前提条件とします。
DDが不十分だと判断されれば、保険に加入できないか、保険料が非常に高くなる可能性があります。
保険はあくまでDDを「補完」するものであり、「代替」するものではないとご理解ください。
Q: どんな表明保証違反でも補償の対象になりますか?
A: なりません。
保険契約には必ず「免責事項」が定められています。
例えば、売り手が意図的に隠していた事実(詐欺)、契約時にすでに認識していた違反、年金や退職金の積立不足、サイバー攻撃に関するリスクなどは一般的に補償対象外となります。
契約前に、弁護士などの専門家と免責範囲をしっかり確認することが極めて重要です。
Q: 保険料は売り手と買い手、どちらが負担するのが一般的ですか?
A: ケースバイケースですが、近年は買い手が負担する例が多く見られます。
買い手にとってはリスクヘッジのメリットが大きく、交渉を円滑に進めるための「取引コスト」と考えることができるからです。
ただし、売り手側の希望で加入する場合や、交渉によって双方が分担する場合もあります。
Q: 5億円未満の小規模なM&Aでも利用できますか?
A: はい、利用可能です。
先述の通り、かつては大規模なM&Aが中心でしたが、近年は中小企業向けの表明保証保険商品が増えており、利用のハードルは下がっています。
取引規模に応じた保険料や補償内容のプランが提供されていますので、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
Q: 保険に加入するかどうか、誰に相談すれば良いですか?
A: まずは、あなたのM&AをサポートしているM&Aアドバイザーや仲介会社に相談するのが第一歩です。
彼らは保険会社とのネットワークを持っていることが多いです。
ただし、その専門家が特定の保険商品を強く勧めてくる場合は、少し立ち止まる勇気も必要です。
私のような独立系のコンサルタントや弁護士など、中立的な立場の専門家にセカンドオピニオンを求めることも、納得のいく意思決定のためには非常に有効な手段です。
まとめ
M&Aにおける表明保証違反は、売り手経営者にとって決して他人事ではない、現実的なリスクです。
表明保証保険は、そのリスクをコントロールし、あなたが心から「納得感のあるM&A」を実現するための、非常に有効な選択肢となり得ます。
しかし、それは万能薬ではなく、コストや免責事項も存在する諸刃の剣でもあります。
最も重要なのは、専門家の意見を鵜呑みにするのではなく、本記事で得たような公平な情報を「武器」として、ご自身の会社の状況やM&A後のライフプランと照らし合わせ、主体的に必要性を判断することです。
この記事が、あなたが大切に育ててきた会社の未来を守るための一助となれば、これに勝る喜びはありません。
最終的な判断に迷われた際は、いつでも私のような中立的な専門家にご相談ください。
あなたの会社の成功を心から願っています。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。