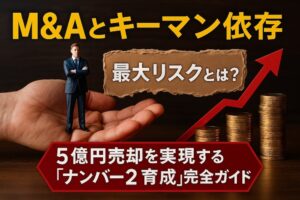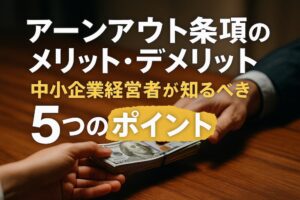【完全解説】M&Aの種類を全て解説:5億円超案件で知っておくべき手法と選択基準

5億円を超える規模のM&Aは、経営者にとって人生を左右する重要な決断です。
しかし、その手法は多岐にわたり、どの選択が自社にとって最適かを見極めるのは容易ではありません。
本記事では、特定の金融機関や仲介会社に属さない完全に中立な立場のM&Aコンサルタントである私が、売り手である経営者の視点に立ち、各M&A手法の特徴から「5億円超の案件で知っておくべき選択基準」までを徹底解説します。
なお、2025年8月には経済産業省から「中小M&A市場改革プラン」が公表され、国全体として中小企業のM&Aを後押しする動きが加速しています。
この記事を読めば、複雑なM&A手法の全体像を理解し、専門家の話に流されることなく、自社の未来にとって最良の選択をするための確かな判断軸を持つことができます。
M&A手法の全体像:まずは3つの分類で理解する
では、複雑に見えるM&A手法をどう整理すればよいのでしょうか?
まずは「関係性の深さ」という軸で、全体像を3つのカテゴリーに分けて理解することから始めましょう。
これらM&Aを含む事業承継全般については、中小企業庁が定める「事業承継ガイドライン」で詳細な指針が示されています。
買収・合併・提携の違い
M&Aは広義には「Mergers(合併) & Acquisitions(買収)」の略ですが、実務上は「資本提携」まで含めて語られることが多く、これらは関係性の深さが異なります。
買収
買い手企業が、売り手企業の経営権(通常は株式の過半数)を取得する手法です。売り手企業は買い手企業の子会社となりますが、法人格は維持されます。
合併
2つ以上の会社が契約によって1つの会社になる手法です。一方の会社がもう一方を吸収する「吸収合併」が一般的で、消滅する会社の法人格はなくなります。
提携
経営権の移転は伴わず、企業同士が業務や資本で協力関係を築く手法です。第三者割当増資などがこれにあたります。
5億円規模の中堅・中小企業のM&Aでは、後継者不在による事業承継などを目的とするケースが非常に多いため、会社の経営権を完全に移転させる「買収」が圧倒的な中心となります。
友好的買収と敵対的買収
ニュースなどで耳にする「敵対的買収」という言葉に、不安を感じる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
これは、買収される側の経営陣の同意を得ずに、株式市場などを通じて一方的に買収を仕掛ける手法です。
しかし、ご安心ください。
株式が非公開であるほとんどの中小企業M&Aでは、経営者の同意なしに買収を進めることは不可能です。
したがって、これからお話しするM&Aは、すべて売り手と買い手の合意に基づいて進められる「友好的買収」が前提となります。
組織再編行為との関係性
少し専門的な話になりますが、M&Aで用いられる手法のうち、「合併」「会社分割」「株式交換」などは、会社法で定められた〈組織再編行為〉に該当します。
これらは、会社組織の骨格を変える法律行為であり、株主総会の特別決議や債権者保護手続きなど、厳格なプロセスが求められます。
なぜこの話をするかというと、後ほど解説する手法が、どのレベルの法律行為に該当するかを知っておくことで、手続きの複雑さや専門家の必要性をイメージしやすくなるからです。
【最重要手法】株式譲渡:中小企業M&Aの王道
では、ここから具体的な手法を見ていきましょう。
まず絶対に押さえておくべきは、中小企業M&Aの王道である「株式譲渡」です。
株式譲渡の仕組みと特徴
株式譲渡とは、売り手企業の株主が保有する株式を、買い手企業(または個人)に売却することで、会社の経営権を移転させる手法です。
多くの専門機関の調査でも、中小企業のM&Aにおいて最も多く用いられる手法であり、その割合は全体の大多数を占めると言われています。
その理由は、後述するメリットにある通り、手続きが他の手法に比べて圧倒的にシンプルだからです。
売り手経営者から見た株式譲渡のメリット
手続きが簡便
株主と買い手の間で株式譲渡契約を結び、株主名簿を書き換えるのが基本です。会社自体は存続するため、事業に必要な許認可や取引先との契約、従業員の雇用契約などを個別に引き継ぐ必要がありません。
譲渡対価を個人で受け取れる
オーナー経営者が株主である場合、譲渡対価は経営者個人に直接支払われます。
税率が有利になる場合が多い
個人が受け取った譲渡益(譲渡価額から取得費と手数料を引いたもの)にかかる税金は、所得税・住民税などを合わせて20.315%の分離課税です。これは、他の所得とは合算されずに計算されます。
従業員や取引先への影響が少ない
会社の経営者が変わるだけで、会社組織そのものは維持されます。そのため、事業運営への影響を最小限に抑えることが可能です。
売り手経営者から見た株式譲渡のデメリット
会社を丸ごと譲渡する
株式を譲渡するということは、資産だけでなく負債やリスクもすべて引き継がれることを意味します。帳簿に載っていない〈簿外債務〉や将来起こりうる訴訟リスクなども対象となるため、買い手は詳細なデューデリジェンス(買収監査)を行います。
保証や担保の解除に手間がかかる
経営者が会社の借入金に対して個人保証をしていたり、個人資産を担保に入れていたりする場合、M&A成立後にそれらを解除するための交渉が別途必要になります。
5億円超の案件における株式譲渡の高橋視点でのポイント
5億円規模の案件で株式譲渡を選択する場合、特に2つの点に注意が必要です。
株主の集約
1つ目は「株主の集約」です。
創業から時間が経っている会社では、親族や元役員などに株式が分散しているケースが稀にあります。
株式譲渡は、原則として全株式の譲渡を目指すため、事前に株主全員の同意を取り付け、手続きを一本化しておくことが交渉をスムーズに進める鍵となります。
売却後の資産管理
2つ目は「売却後の資産管理」です。
5億円という大きな対価を個人で受け取ることになります。これは、経営者としてのリタイア後の生活、いわば「セカンドライフ」の設計を考える絶好の機会です。
譲渡益にかかる税金は前述の通りですが、2025年以降、極めて所得の高い層に対しては実質的な税負担が増す税制改正も議論されています。
【特定事業の売買】事業譲渡:ノンコア事業の切り離しや事業再生で活用
次に、株式譲渡とよく比較される「事業譲渡」について見ていきましょう。
これは、会社の経営権ではなく「事業」そのものを売買する手法です。
事業譲渡の仕組みと特徴
事業譲渡とは、会社が営む事業の一部または全部を、他の会社に譲渡する手法です。
最大の特徴は、譲渡する資産や負債、契約、従業員などを個別に選別できる点にあります。
例えば、「A事業に関連する工場、機械、従業員、ブランドは譲渡するが、本社ビルとB事業は手元に残す」といった柔軟な取引が可能です。
売り手経営者から見た事業譲渡のメリット
不採算事業のみを売却できる
「選択と集中」の戦略として、ノンコア事業や不採算事業を切り離し、得た資金を主力事業に再投資することができます。
会社自体は手元に残る
特定の事業を譲渡しても、会社(法人格)は存続します。経営を続けながら、事業ポートフォリオを再構築したい場合に有効です。
売り手にとってのリスク遮断
譲渡対象を個別に選ぶため、買い手に引き継がない事業に関する偶発債務などのリスクを売り手側で遮断できます。
売り手経営者から見た事業譲渡のデメリット
手続きが煩雑
資産や負債、契約を個別に移転させるため、膨大な手間がかかります。取引先との契約は全て巻き直しが必要になり、従業員も買い手企業と再雇用契約を結ぶ必要があります。不動産があれば登記移転も必要です。
許認可の再取得が必要
事業に必要な許認可は、原則として買い手が新たに取得し直さなければなりません。
税負担が重くなる可能性がある
譲渡の対価は会社が受け取ります。その譲渡益には法人税(実効税率約30~34%)がかかります。さらに、その利益を経営者個人が受け取る際には、配当や役員退職金として所得税がかかるため、二重の課税となる可能性があります。
消費税の課税対象となる
建物や機械、のれん(営業権)といった課税資産の譲渡には消費税がかかります。ただし、土地や有価証券、売掛金などは非課税です。
5億円超の案件における事業譲渡の高橋視点でのポイント
5億円規模の企業が複数の事業を展開している場合、この事業譲渡は〈カーブアウト〉(事業切り出し)戦略として非常に有効な選択肢となります。
私が現場で見たある老舗メーカーのケースでは、長年続けてきた祖業が赤字でしたが、近年始めた新規事業が好調でした。
この会社は、祖業を同業他社に事業譲渡することで従業員の雇用を守りつつ、得た資金で好調な新規事業に集中投資し、見事なV字回復を遂げました。
買い手にとっても、必要な事業だけを取得でき、簿外債務などのリスクを遮断できるメリットは大きいです。
しかし、売り手経営者として最も心を砕くべきは「従業員のケア」です。
事業譲渡では、従業員は一度退職し、買い手企業と再雇用契約を結ぶ「転籍」という形になります。
給与や待遇、企業文化の変化に対する従業員の不安を払拭するため、買い手と協力し、丁寧な説明とコミュニケーションを尽くすことが、M&A成功の絶対条件と言えるでしょう。
【組織再編で活用】その他のM&A手法
株式譲渡と事業譲渡が中小企業M&Aの二大手法ですが、他にも知っておくべき手法が存在します。
これらは主に大企業やグループ内での組織再編で使われますが、5億円規模のM&Aでも特定の状況下で選択肢となり得ます。
合併(吸収合併・新設合併)
複数の会社を一つの法人格に統合する手法です。
グループ会社を整理統合する際などには有効ですが、独立した企業同士のM&Aでは、権利義務の調整や人事制度の統合など、手続きが非常に煩雑になるため、5億円規模の案件で選択されることは稀です。
会社分割(吸収分割・新設分割)
特定の事業を他の会社に承継させる手法で、事業譲渡と似ています。
大きな違いは、事業譲渡が資産や契約を「個別に」移転させるのに対し、会社分割は事業に関する権利義務を「包括的に」承継できる点です。
これにより、取引先との契約巻き直しや従業員の転籍同意が原則不要となり、手続きを簡素化できる場合があります。
また、一定の要件(税制適格要件)を満たせば、譲渡益への課税を繰り延べられるという税務上のメリットもありますが、この要件が非常に複雑なため、高度な専門知識を持つ税理士や弁護士との連携が不可欠です。
株式交換・株式移転
どちらも、ある会社を100%子会社化(完全親子会社関係を創設)する際に用いられる手法です。
特に、買い手が上場企業で、買収の対価として現金の代わりに自社の株式を交付するようなケースで活用されます。
売り手企業の株主は、対価として買い手企業の株式を受け取ることになります。
第三者割当増資(資本提携)
これは、会社の経営権そのものを譲渡するのではなく、特定の第三者(買い手)に対して新株を発行し、資本を受け入れる手法です。
買い手は一部の株主となり、両社は協力関係を強化します。
本格的なM&Aの前に、まずは業務提携や資本提携から関係を始めたい、という場合に有効な選択肢です。
「いきなり会社を売るのは…」と考える経営者にとって、M&Aへの第一歩となる可能性を秘めています。
【高橋健一が解説】5億円超のM&Aで最適な手法を選ぶための選択基準
ここまで様々な手法を見てきましたが、結局、自社にとってはどれが最適なのでしょうか?
ここでは、私がいつも経営者の方にお伝えしている「4つの判断軸」をご紹介します。
1. 目的から考える:会社を丸ごと譲るか、一部を譲るか
これが最も根源的な問いです。
- 後継者不在で、会社と従業員の未来をすべて託したい → 会社を丸ごと譲る「株式譲渡」が第一候補です。
- 複数の事業があり、特定の事業に集中したい → 一部を譲る「事業譲渡」や「会社分割」が選択肢になります。
- 会社は手元に残し、経営を続けたい → 同様に「事業譲渡」が考えられます。
まずはM&Aによって何を達成したいのか、その目的を明確に言語化することが出発点です。
2. 税金から考える:誰が対価を受け取り、税負担をどう最適化するか
税金は、手元に残る現金を大きく左右する重要な要素です。
- 株式譲渡:対価は株主個人が受け取り、譲渡益に約20%の税金がかかります。
- 事業譲渡:対価は会社が受け取り、譲渡益に約30~34%の法人税がかかります。
単純比較すれば株式譲渡の方が税率上有利に見えます。
しかし、事業譲渡で得た資金を役員退職金として受け取ることで、税負担を軽減できる場合もあります。
このあたりは会社の状況や経営者のライフプランによって最適解が異なるため、必ずM&Aに強い税理士に相談し、シミュレーションを行うべきです。
3. 手続きの煩雑さから考える:従業員・取引先への影響はどうか
M&Aは、数字だけの話ではありません。
長年会社を支えてくれた従業員や取引先への影響を最小限にしたい、と考えるのは経営者として当然の想いです。
- 株式譲渡:株主が変わるだけなので、雇用契約や取引契約はそのまま維持されます。手続きは比較的シンプルです。
- 事業譲渡:従業員の転籍や取引先との契約巻き直しが発生し、手続きは非常に煩雑になります。
従業員の雇用維持を最優先事項とするならば、原則として雇用がそのまま引き継がれる株式譲渡の方が、心理的な負担は少ないと言えるでしょう。
4. 買い手の意向を考慮する:買い手が何を取得したいのか
M&Aは交渉であり、相手がいる話です。
買い手側の視点を理解することも、最適な手法を選択し、交渉を有利に進める上で不可欠です。
例えば、買い手が売り手企業のブランドや技術力は欲しいものの、潜在的な債務リスク(簿外債務など)を引き継ぐことを懸念している場合、彼らは事業譲渡を望むかもしれません。
私が金融機関にいた頃、融資先のM&Aで買い手側のアドバイザーが、徹底して簿外債務のリスクを洗い出し、最終的に株式譲渡から事業譲渡へスキーム変更を提案したケースがありました。
売り手として希望の手法を軸にしつつも、買い手のニーズを汲み取り、代替案を準備しておく柔軟な姿勢が、良好な着地点を見出すための鍵となります。
M&A手法の選択が「専門家選び」に与える影響
ここまでお話ししてきた手法の選択は、実は「誰にM&Aを相談するか」という専門家選びにも直結する重要な問題です。
仲介会社が得意な手法、FAが得意な手法
中小企業M&Aの専門家は、大きく「M&A仲介会社」と「FA(ファイナンシャル・アドバイザー)」に分かれます。
M&A仲介会社
売り手と買い手の間に入り、中立的な立場で成約を目指します。中小企業M&Aで最も一般的な株式譲渡案件を数多く手掛けており、幅広いネットワークを持っています。
FA
売り手か買い手のどちらか一方の代理人として、依頼者の利益最大化を目指します。会社分割のような複雑な組織再編や、価格交渉がシビアになる案件で、その専門性を発揮します。
つまり、比較的シンプルな株式譲渡であれば多くの仲介会社が対応可能ですが、税務メリットを狙った会社分割など、複雑なスキームを検討するなら、高度な知識を持つFAや、M&Aに精通した弁護士、公認会計士、税理士といった専門家のチームアップが不可欠になるのです。
なぜ、手法の検討前に専門家と話すのが重要なのか
「どの手法が良いか決めてから専門家に相談しよう」と考える経営者の方がいますが、私は逆だと考えています。
初期段階でこそ、特定の専門家タイプに偏らず、複数の選択肢を提示できる専門家と話すべきです。
なぜなら、初期段階で「うちは株式譲渡しかない」と決めつけてしまうと、実は事業譲渡の方が高く売れる可能性や、会社分割の方が税務上有利になる可能性を見過ごしてしまうかもしれないからです。
私の信条は「専門家選びがM&Aの成否を分ける」です。
父が経営者だったこともあり、経営者の孤独な決断を数多く見てきました。
だからこそ、あなたの会社の状況を深く理解し、あらゆる手法のメリット・デメリットを中立的に比較検討してくれる、信頼できるパートナーを見つけることが何よりも重要なのです。
よくある質問(FAQ)
Q: 中小企業のM&Aで最も多く使われる手法は何ですか?
A: 株式譲渡が最も一般的で、全体の大多数を占めると言われています。手続きが比較的シンプルで、会社を一体として引き継げるため、特にオーナー経営者一人が大半の株式を保有する中小企業に適しています。
Q: 株式譲渡と事業譲渡の最大の違いは何ですか?
A: 最大の違いは「何を売るか」です。株式譲渡は「会社そのもの(経営権)」を売るのに対し、事業譲渡は会社の「事業の一部または全部」を売ります。その結果、対価を受け取る人(株主か会社か)、税金の種類、手続きの複雑さが大きく異なります。
Q: 5億円規模のM&Aだと、どの手法が一番多いのでしょうか?
A: 私の経験上、5億円規模でも後継者不在などを理由とする事業承継目的が多いため、やはり「株式譲渡」が圧倒的に多いです。ただし、複数の事業を持つ企業が「選択と集中」を進めるために「事業譲渡」を選択するケースも確実に増えています。
Q: 負債が多いのですが、それでもM&Aは可能ですか?
A: はい、可能です。株式譲渡の場合は負債も買い手に引き継がれますが、その分、売却価格(株価)が調整されます。事業譲渡であれば、負債を引き継がずに優良な事業だけを売却するという選択肢もあります。
金融機関は企業の将来性も評価しますので、負債額だけで諦める必要は全くありません。
Q: M&Aの手法は誰が最終的に決めるのですか?
A: 最終的には売り手と買い手の合意によって決まります。しかし、売り手である経営者が主体的に「自社にとっての最適解は何か」を考え、専門家と相談しながら交渉の初期段階で方針を固めておくことが極めて重要です。
相手の言いなりになるのではなく、自社の希望を明確に伝えることで、交渉の主導権を握ることができます。
まとめ
本記事では、5億円超のM&Aを検討する経営者の皆様へ、独立系コンサルタントの視点から各種M&A手法とその選択基準を解説しました。
株式譲渡や事業譲渡といった代表的な手法から、より複雑な組織再編まで、それぞれにメリット・デメリットがあります。
最も重要なのは、自社のM&Aの目的を明確にし、税金や手続き、従業員への影響などを総合的に考慮して、最適な手法を見極めることです。
そして、その選択は信頼できる専門家選びと密接に結びついています。
本記事で得た知識を「判断軸」として、ぜひ納得のいくM&Aの第一歩を踏み出してください。
情報こそが、経営者であるあなたの最大の武器となるはずです。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。