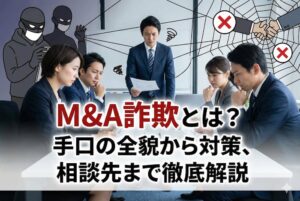「従業員の生活を守りたい」M&Aで社員の雇用と待遇を守る交渉術
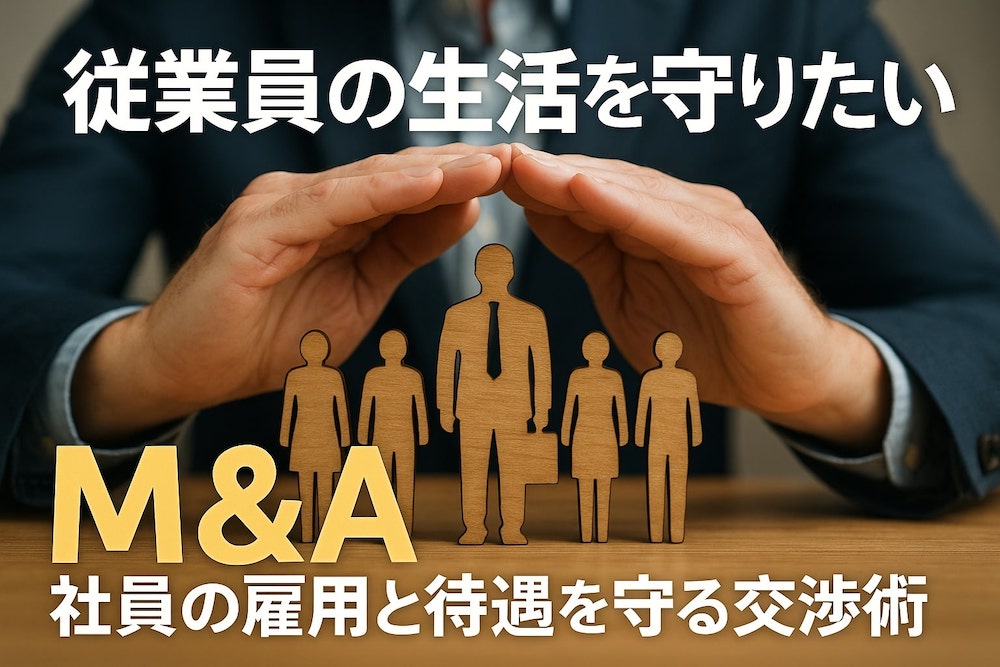
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの、高橋 健一です。
人生を賭けて育ててきた会社を、第三者に託す。
M&Aという決断を下す経営者の胸には、事業の成長への期待とともに、「長年苦楽を共にしてきた従業員の生活を、断じて守り抜きたい」という強い想いが宿っているはずです。
私の父も中小企業を経営しており、従業員を「家族」と呼び、その生活に深い責任を感じていました。
だからこそ、その想いは単なる感傷ではないと、私は断言できます。
従業員という最も重要な資産を守り、その価値を買い手に正しく伝えることこそ、M&Aを成功に導く鍵なのです。
本記事では、私が大手金融機関や独立後の現場で培ってきた知見を基に、その想いを実現するための具体的な「交渉術」を徹底解説します。
法的な建前論だけでなく、買い手の本音を見抜き、従業員の未来を守るための実践的な知恵と戦略をお伝えします。

なぜM&Aで「従業員の雇用維持」が最重要課題なのか
感情論ではない、企業価値を守るための合理的な理由
まず、経営者の皆様に強くお伝えしたいことがあります。
それは、「従業員を守りたい」という想いは、単なる温情主義ではなく、M&Aの成功に不可欠な、極めて合理的な経営判断であるということです。
理由は大きく3つあります。
人材流出の危険性
第一に、人材の流出は企業価値そのものを毀損するからです。
特に中小企業においては、従業員一人ひとりが持つ技術、ノウハウ、そして顧客との信頼関係が、事業の根幹を成しています。
M&Aを機に彼らが退職してしまえば、買い手は「魂の抜けた器」を高いお金で買うことになりかねません。
これは買い手にとっても、売り手にとっても、最悪のシナリオです。
円滑な事業引継ぎ
第二に、円滑な事業引継ぎ〈PMI:Post Merger Integration〉に不可欠だからです。
M&Aは契約して終わりではありません。
むしろ、その後の統合プロセスこそが成功の鍵を握ります。
従業員の協力なくして、事業の円滑な引継ぎはあり得ません。
彼らのモチベーションを維持することが、M&A後の成長を左右するのです。
納得感のあるM&Aの実現
そして第三に、経営者ご自身が「納得感のあるM&A」を実現するためです。
たとえ高値で売却できたとしても、従業員が不幸になってしまっては、本当に「良いM&Aだった」と胸を張れるでしょうか。
創業者の想いを守り、従業員の未来に道筋をつけること。
それこそが、経営者として最後に果たすべき、最も重要な責務だと私は考えます。
M&Aスキームによる雇用契約の扱いの違い【基礎知識】
では、具体的に従業員の雇用は法的にどう扱われるのでしょうか。
ここで、M&Aの代表的な2つの手法〈スキーム〉による違いを理解しておくことが、交渉の出発点となります。
1. 株式譲渡
これは、会社のオーナー(株主)が保有する株式を買い手に売却する手法です。会社そのものは存続し、株主が変わるだけです。
そのため、従業員と会社の雇用契約は、原則としてそのまま買い手に包括的に承継されます。
労働条件も維持され、従業員の個別同意も必要ありません。
従業員の雇用を守るという観点では、最も安定したスキームと言えるでしょう。
2. 事業譲渡
こちらは、会社の事業の一部または全部を、モノや権利のように切り出して売却する手法です。
この場合、雇用契約は自動的には引き継がれません。
買い手が従業員の雇用を継続するには、従業員一人ひとりから個別の同意を得て、新たに雇用契約を結び直す必要があります。
つまり、買い手は引き継ぐ従業員を選別できるのです。
この違いが、後の交渉戦略に大きく影響してくることを覚えておいてください。
【実践編】従業員の雇用と待遇を守り抜くための交渉術5選
ここからは、いよいよ本題である実践的な交渉術です。
私が現場で経営者の方々と共に実践してきた、従業員を守り抜くための5つの戦略をご紹介します。
交渉術1:初期段階で「雇用維持」を取引の絶対条件として提示する
交渉の成否は、初動で決まると言っても過言ではありません。
では、いつ「従業員の雇用維持」を切り出すべきか。答えは、M&Aプロセスの最も初期の段階です。
これは、買い手に対する強力なメッセージとなります。
「もし従業員を単なるコストとしか見なさないのであれば、この話は最初からなかったことにしてください」という意思表示です。
これにより、人材を大切にしない買い手候補を初期段階でふるいにかける「スクリーニング機能」を果たします。
誠実な買い手であれば、この条件を尊重し、交渉の前提としてくれるはずです。
交渉術2:従業員の価値を「定性」と「定量」で可視化する
交渉のテーブルで、「従業員を大切にしてほしい」と感情的に訴えるだけでは、百戦錬磨の買い手には響きません。
必要なのは、「彼らがいなければ、この事業価値は維持できません」という揺るぎないロジックです。
そのために、従業員の価値を「見える化」する準備が不可欠です。
【定量データ】
- 従業員リスト(勤続年数、役職、保有資格など)
- スキルマップ(誰が、どの技術・ノウハウを持っているか)
- 顧客担当者リスト(誰が、どの重要顧客との関係を築いているか)
- 離職率の推移(人材が定着していることの証明)
【定性データ】
- 独自の技術や製造ノウハウ(特定の従業員しか持たない暗黙知)
- 顧客からの信頼を示すエピソードや感謝の手紙
- チームワークの良さや独自の企業文化を示す具体例
これらの資料を丁寧に作成し、企業概要書の一部として提示することで、交渉は「お願い」から「提案」へと変わります。
「この人材こそが、貴社がM&Aで手に入れる真の価値です」と、論理的に訴えるのです。
交渉術3:最終契約書に「雇用維持条項(ロックアップ)」を盛り込む
口約束ほど当てにならないものはありません。
交渉で勝ち取った条件は、必ず法的な拘束力を持つ最終契約書〈DA:Definitive Agreement〉に明記させることが鉄則です。
具体的には、以下のような「雇用維持条項」を盛り込むことを目指します。
【条項例】
「買い手は、本件M&Aのクロージング日より最低〇年間、対象会社の従業員(パート・アルバイトを含む)を、本契約締結日時点と実質的に同等以上の労働条件(給与、賞与、退職金制度、福利厚生を含む)で雇用を維持するものとし、本人の同意なく勤務地を強制的に変更しない。」
この「〇年間」という期間は、一般的に2〜3年で設定されることが多いです。
私が金融機関で担当したある製造業の案件では、熟練工の技術承継が事業の生命線であったため、「キーパーソン5名の5年間雇用維持」を絶対条件とし、これを勝ち取った結果、M&A後の事業も順調に成長しました。
この条項は、買い手にとっても事業継続リスクを低減するメリットがあるため、強力な交渉カードとなり得ます。
交渉術4:買い手候補の「企業文化」と「人材観」を徹底的に見極める
契約書は、いわば最後の砦です。
しかし、それだけでは従業員の「働きがい」や「安心感」までは守れません。
最も重要なのは、そもそも「従業員を大切にする」という価値観を持った買い手を選ぶことです。
トップ面談の際には、ぜひ経営者ご自身の言葉で、こう問いかけてみてください。
「貴社にとって、人材とはどのような存在ですか?」
「これまでM&Aをされた経験があれば、その後の従業員の処遇について教えてください」
その答えの熱量や具体性から、相手の「人材観」が透けて見えます。
また、客観的なデータとして、買い手企業の従業員定着率や平均勤続年数、労務関連の訴訟の有無などを確認することも有効です。
契約書にサインする前に、あなたの従業員を安心して託せる相手かどうか、その企業文化と人柄を徹底的に見極めてください。
交渉術5:価格交渉で譲歩してでも、従業員の待遇維持を勝ち取る戦略
M&Aの条件交渉は、多くの場合トレードオフの関係にあります。全てを100%勝ち取ることは難しいのが現実です。
そこで、経営者としての最後の決断が問われます。
例えば、買い手から、
「希望売却価格を満額支払うのは難しい。しかし、従業員の雇用と待遇は3年間完全に保証する」
という提案があったとします。
一方で、別の買い手は、
「希望価格に1億円上乗せする。ただし、雇用維持の約束は1年しかできない」
と言っている。
あなたなら、どちらを選びますか?
ここに、絶対的な正解はありません。
経営者ご自身の売却益を多少譲歩してでも、従業員の未来を優先するという選択肢は、極めて尊い経営判断です。
ご自身が「何を最も大切にしたいのか」というM&Aの軸を明確に持つことが、後悔のない決断に繋がります。
従業員の不安を煽らない「情報開示」のタイミングと伝え方
最適なタイミングは「最終契約締結後」が原則
従業員にM&Aの事実をいつ伝えるべきか。これは非常にデリケートな問題です。
結論から言うと、情報開失の最適なタイミングは「最終契約の締結後、株式や事業の引渡し(クロージング)直後」が原則です。
なぜなら、それ以前の不確定な段階で情報が漏れると、従業員の間に不安や憶測が広がり、通常業務に支障をきたすだけでなく、最悪の場合、M&Aの情報が外部に漏れて破談になるリスクさえあるからです。
ただし、役員や事業責任者など、M&Aのプロセスに協力が不可欠なキーパーソンには、秘密保持契約を結んだ上で、基本合意後など、より早い段階で相談が必要になるケースもあります。
経営者自身の言葉で「未来志向」のメッセージを伝える
いよいよ従業員に説明する日。その場には買い手の担当者にも同席してもらいましょう。
そして、何よりも大切なのは、必ず売り手である経営者ご自身の言葉で、直接語りかけることです。
伝えるべきは、「会社を売った」という過去の話ではありません。
M&Aが「身売り」や「敗北」ではなく、会社のさらなる成長と、従業員一人ひとりにとってのより良い未来、新たなキャリアの機会に繋がる「未来志向の選択」であったことを、誠心誠意、伝えるのです。
買い手の強み(資本力、販路、技術力など)を具体的に挙げ、「このパートナーと組むことで、我々だけでは実現できなかったこんな未来が開ける」と、ポジティブなメッセージを語ってください。
あなたの真摯な言葉と態度は、必ず従業員の心に届き、不安を希望に変える力となるはずです。
よくある質問(FAQ)
Q: M&A後、給与や退職金、有給休暇の扱いはどうなりますか?
A: スキームによって異なります。株式譲渡の場合は、原則として労働条件はすべて引き継がれます。
給与や有給休暇はもちろん、退職金制度もそのまま承継されるのが基本です。
一方で事業譲渡の場合は、買い手と新たに雇用契約を結ぶため、交渉が重要になります。
特に退職金の扱いについては、①譲渡時に売り手である貴社が功労金などの形で一度精算する、②将来支払うべき退職金相当額を買い手に引き継いでもらう、といった方法があります。
いずれにせよ、最終契約書で「退職金制度の承継」やその具体的な扱いを明確に定めておくことが不可欠です。
Q: 転勤や部署異動を命じられる可能性はありますか?
A: 可能性はゼロではありません。
就業規則に「業務の都合により転勤や配置転換を命じることがある」と定められていれば、法的には可能です。
だからこそ、前述の交渉術3で解説した通り、最終契約書に「主要な従業員の勤務地を当面変更しない」といった条項を盛り込むことが重要になります。
特に、地域に根差した事業の場合、この点は買い手にとっても事業価値を維持する上でキーとなるため、比較的、交渉しやすいポイントの一つです。
Q: 従業員がM&Aに反対し、退職してしまったらどうすればよいですか?
A: 残念ながら、全ての従業員の理解を得られないケースも起こり得ます。
重要なのは、経営者であるあなたが、誠心誠意、従業員の雇用を守るために全力を尽くして交渉したという事実を、正直に伝えることです。
その上で、最終的に会社を去るという決断をした従業員の意思も尊重する必要があります。
また、そうした事態を最小限に抑えるため、買い手側にも、M&A後に従業員の不安を払拭するための面談や対話の場(タウンホールミーティングなど)を設けてもらうよう、事前に約束を取り付けておくことが大切です。
Q: パートやアルバイトの雇用も守られますか?
A: 守るべきです。交渉のテーブルに乗せるべきは、正社員だけではありません。
パートやアルバイトの方々もまた、長年事業を支えてくれた重要な戦力です。
交渉の初期段階で提示する条件に、「非正規雇用者を含む全従業員の雇用維持」を明確に含めましょう。
「従業員」という言葉を使う時、そこに雇用形態の区別はありません。
Q: 買い手は本当に「雇用維持の約束」を守ってくれるのでしょうか?
A: 最終契約書に盛り込まれた条項は、法的な拘束力を持ちます。
万が一、正当な理由なく約束が破られれば、契約違反として損害賠償等を請求することも可能です。
しかし、私が最も重要だと考えるのは、契約書という「最後の砦」に頼る前に、そもそも「従業員を大切にする」という価値観を持った誠実な買い手を選ぶことです。
契約はあくまでルールですが、企業文化や経営者の人柄は、そのルールをどう運用するかを決めます。
交渉術4で述べた「逆DD」を徹底し、相手の本質を見極めることこそが、最も確実な担保となるのです。
まとめ
従業員の生活を守るM&Aは、決して理想論ではありません。
それは、正しい知識と戦略、そして何よりも経営者の強い意志があれば実現可能な、極めて現実的な目標です。
本記事で解説した「交渉術」は、そのための武器です。
M&Aのプロセスでは、時に厳しい判断が求められます。
しかし、交渉の軸に「従業員の未来」という一本の太い柱を据えることで、自ずと進むべき道は見えてくるはずです。
あなたが人生を賭けて築き上げてきた大切な会社と、それを支えてくれた従業員全員にとって、最良の未来を切り拓く。
この記事が、その一助となることを心から願っています。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。