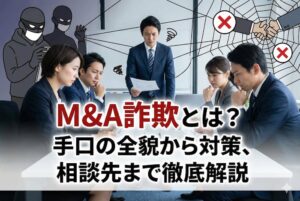M&A契約書の基本:「秘密保持契約(NDA)」を5億円超案件で結ぶ際の注意点
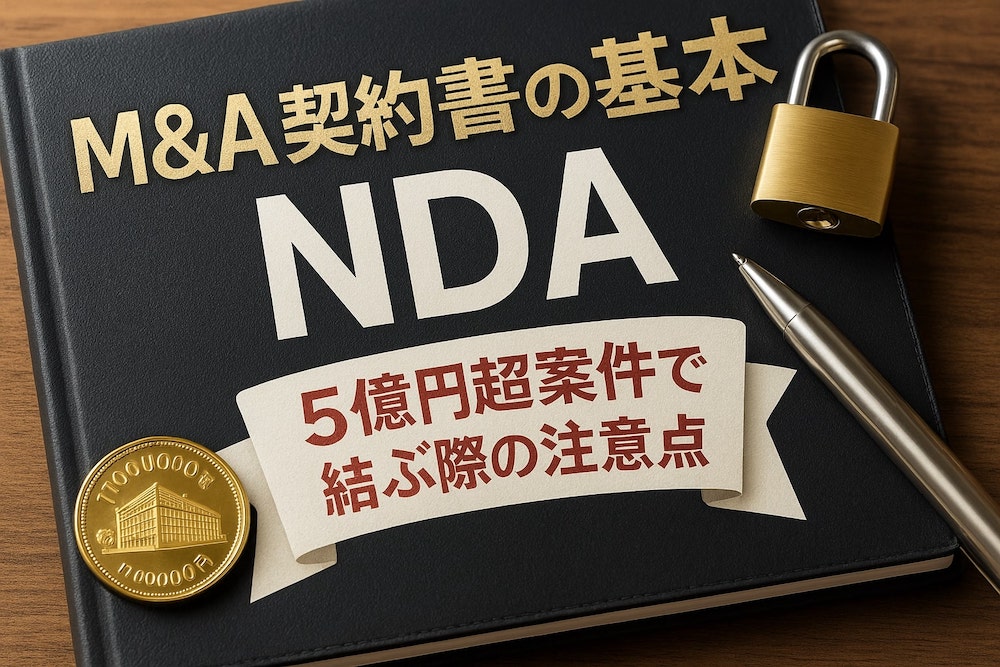
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの高橋健一です。
5億円を超える規模のM&Aは、会社にとって未来を左右する重大な経営判断です。
その成否を分ける最初の関門が、買い手候補との間で締結する「秘密保持契約(NDA)」に他なりません。
近年、後継者不足などを背景にM&Aの件数は増加の一途をたどっており、2024年度には過去最多の4,704件に達するなど、その活用はもはや特別な経営戦略ではなくなりました。
しかし、この活況の裏で、私は多くの経営者様からご相談をいただく中で、安易にNDAへ署名してしまい、後々の交渉で不利な立場に立たされたケースを目の当たりにしてきました。
M&Aを検討している事実そのものが漏れるだけで、従業員の動揺や取引先との関係悪化を招きかねません。
本記事では、独立した中立的な立場から、特に5億円超のM&Aにおいて、経営者が自ら会社を守るためにNDAのどこに注目し、どう交渉すべきか、その戦略的チェックポイントを具体的に解説します。
これは単なる書式の解説ではありません。
経営者の皆様が「情報」という武器を手に、納得のいくM&Aを実現するための羅針盤です。
なぜ「5億円超」のM&AではNDAが特に重要なのか?
近年、日本のM&A市場は急速に拡大しており、2024年には過去最多の4,700件に達しました。
しかし、純資産5億円を超える大型案件は全体のわずか5.6%(34件)に過ぎません。
この希少性こそが、5億円超M&AにおけるNDAの重要性を物語っています。
上図が示すように、5億円超の案件は量的には少数ですが、その1件1件が企業の命運を左右する
重大な取引となります。だからこそ、情報管理の徹底が不可欠なのです。
では、なぜ特に「5億円超」という規模のM&Aで、NDAの重要性が格段に増すのでしょうか。
それは、この規模のディール〈取引〉に特有のリスクが存在するからです。
会社の根幹を揺るがす情報漏洩リスク
5億円以上の価値がつく企業は、それ相応の「宝」を持っています。
それは、独自の製造技術や特許、長年かけて築き上げた強固な顧客基盤、そして詳細な財務情報や人事情報など、企業の競争力の源泉そのものです。
もしこれらの情報が漏洩すれば、どうなるでしょうか。
競合に模倣されたり、主要な取引先が離反したりと、事業価値そのものが大きく毀損〈きそん〉する恐れがあります。
交渉の相手は「交渉のプロ」である可能性
この規模のM&Aになると、買い手候補はM&A経験が豊富な大手企業や、M&Aを専門とする投資ファンドである場合が多くなります。
彼らは、いわば「交渉のプロ」です。
日々、数多くのM&A案件を手掛けており、法務部門や顧問弁護士と連携し、自社に有利な契約書を作成することに長けています。
彼らが提示するNDAは、一見すると標準的な書式に見えるかもしれません。
しかし、その中には、買い手側に有利な条項が巧みに潜んでいる可能性があります。
知識なくして、彼らと対等に渡り合うことは極めて困難と言わざるを得ません。
関与するステークホルダーの増加と管理の複雑性
M&Aの検討が進むと、情報は経営者一人の胸の内には収まらなくなります。
信頼できる役員はもちろん、デューデリジェンス〈買収監査〉の過程では、経理部長や人事部長といった一部の従業員、さらには顧問会計士、税理士、弁護士など、情報を共有する範囲は必然的に広がっていきます。
企業の規模が大きければ大きいほど、関与するステークホルダー〈利害関係者〉は増え、情報管理の難易度は格段に上がります。
だからこそ、最初のNDAで「誰まで情報を開示できるのか」「開示先にも同等の義務を課せるのか」を厳密に定めておくことが、情報漏洩という最大のリスクを防ぐための生命線となるのです。
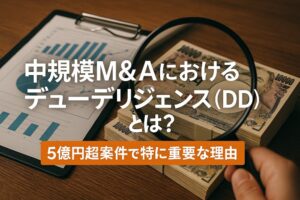
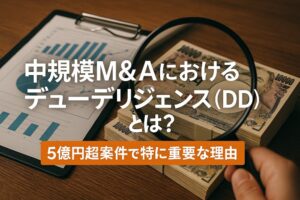
【経営者のためのNDA読解術】契約書が届いたら、まず確認すべき10の急所
買い手候補からNDAのドラフトが送られてきたら、どこから手をつければよいのでしょうか。
ここでは、難解な法律用語を経営者目線で「翻訳」し、最低限確認すべき10の急所を解説します。
1. 「秘密情報」の定義:自社の”宝”は守られる範囲に含まれているか?
まず確認すべきは、「何が秘密情報にあたるのか」を定める定義条項です。
この定義が曖昧だったり、範囲が狭すぎたりすると、自社が最も守りたい”宝”が保護の対象外となってしまうリスクがあります。
- 「本件取引の検討に関連して、甲(売り手)が乙(買い手)に開示する一切の情報」といった包括的な表現があるか。
- それに加え、「財務、技術、人事、顧客、ノウハウ、経営戦略に関する情報を含むが、これらに限定されない」のように、重要な情報が具体的に例示されているか。
- 口頭で開示した情報も、後から書面で「秘密情報」と指定すれば対象となる、といった手続きが定められているか。
2. 「目的」の限定:M&A検討以外の目的で情報を使われないか?
なぜ情報を開示するのか、その「目的」を明確に限定することは、不正利用を防ぐための最重要項目です。
特に、買い手候補が同業他社の場合、この条項がなければ、あなたの会社の機密情報が彼らの営業活動や事業戦略に流用されかねません。
- 情報の利用目的が「本M&Aの検討および交渉のため」に明確に限定されているか。
- これ以外の目的での利用を固く禁じる文言があるか。
3. 「開示の範囲」:情報は誰まで共有されるのか?
開示した秘密情報は、買い手企業の誰まで共有されてしまうのでしょうか。
この範囲をコントロールできなければ、情報漏洩のリスクは一気に高まります。
- 情報の開示先が「本件取引の検討に直接関与する必要のある役員、従業員、弁護士、会計士等の専門家」などに限定されているか。
- 買い手がこれらの者に情報を開示する際、その者に対しても「本契約と同等の秘密保持義務を課す」という条項があるか。これは必須の項目です。
4. 「秘密保持義務の期間」:いつまで情報を守ってもらえるのか?
契約書には「有効期間」が定められていますが、これと「秘密保持義務が続く期間」は別物である点に注意が必要です。
M&Aが不成立に終わった後、すぐに情報保護の義務がなくなってしまっては意味がありません。
- NDA自体の有効期間は、交渉期間を想定した「1年〜3年」程度が一般的です。
- それとは別に、交渉が終了した後も秘密保持義務が存続する「サバイバル条項」があるかを確認してください。この存続期間は、情報の重要性にもよりますが、「3年〜5年」程度を要求するのが一般的です。
5. 「情報の返還・破棄義務」:交渉が終われば情報は消去されるか?
交渉が不成立に終わった場合、開示した資料やそのコピーが相手の手元に残り続けるのは、気分の良いものではありません。
将来的なリスクを断ち切るためにも、情報の返還・破棄は明確に義務付けておくべきです。
- 交渉終了時、売り手の要求に応じて、開示した全ての秘密情報(電子データやコピーを含む)を「速やかに返還または破棄する」義務が定められているか。
- 破棄した場合、その事実を証明する「破棄証明書」の提出を求める権利が記載されているか。
6. 「損害賠償」:違反時のペナルティは妥当か?
万が一、契約違反によって情報が漏洩した場合のペナルティを定めておくことは、何よりの抑止力になります。
ただ、実際に漏洩によって生じた「損害額」を裁判で立証するのは、極めて難しいのが現実です。
- 契約違反があった場合の損害賠償義務が明記されているか。
- 損害額の立証の難しさに備え、「違約金」として具体的な金額(例:金500万円)を定める交渉も選択肢の一つです。金額の多寡よりも、この条項があること自体の抑止力効果が重要です。
7. 「独占交渉権」:知らないうちに他の候補と会えなくされていないか?
これは、私が最も強く警告したい項目の一つです。
NDAはあくまで秘密を守るための契約であり、この段階で特定の1社としか交渉できなくなる「独占交渉権」を安易に与えるべきではありません。
- NDAの条文の中に「独占交渉権」や、他の第三者との接触を禁じるような文言が含まれていないか。
- もし含まれていれば、それは基本合意書(LOI)の段階で交渉すべき項目であるため、削除を強く要求してください。これを飲むことは、自ら競争の機会を放棄するに等しい行為です。


8. 「従業員の引き抜き禁止(勧誘禁止条項)」:人材流出のリスクはないか?
M&Aの検討過程で、買い手はあなたの会社の優秀な人材、特にキーパーソンとなる従業員の情報を知ることになります。
交渉が不調に終わった途端、そのキーパーソンに買い手が接触し、引き抜こうとするリスクに備える必要があります。
交渉中および交渉終了後、一定期間(例:1〜2年)、売り手の従業員に対して「直接・間接を問わず、勧誘、雇用勧誘、または雇用しない」ことを約束させる「Non-solicitation条項」の追加を検討してください。これは会社の人的資本を守る重要な防衛策です。
9. 「管轄裁判所」:万一の紛争、どこで戦うことになるのか?
万が一、契約を巡って紛争が生じた場合、どの裁判所で裁判を行うかを定めるのが「合意管轄」条項です。
これが買い手の本社所在地など、自社から遠く離れた場所に指定されていると、訴訟になった際の負担が非常に大きくなります。
合意管轄裁判所が、自社の本店所在地を管轄する裁判所、あるいは利便性の高い「東京地方裁判所」や「大阪地方裁判所」に指定されているか。不利な指定になっている場合は、修正を求めましょう。
10. 「協議事項」:誠実な対話の窓口は確保されているか?
契約書は万能ではありません。
どうしても定めのない事態や、条文の解釈に疑義が生じることは起こり得ます。
その際に、一方的な解釈ではなく、話し合いで解決する道を残しておくことが重要です。
- 「本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決する」といった趣旨の協議条項があるか。
- これは、形式的な契約関係を超え、相手方との信頼関係を築く上でも大切な一文となります。
買い手提示の雛形は疑ってかかれ!売り手が不利にならないための交渉術
ここまで10の急所を見てきましたが、これらを元にどうやって交渉すればよいのでしょうか。
ここでは、より実践的なアドバイスをお伝えします。
なぜM&A専門弁護士によるレビューが不可欠なのか
M&A仲介会社やFA〈ファイナンシャル・アドバイザー〉も、NDA締結をサポートしてくれます。
しかし、彼らの専門はあくまでディールを成立させることであり、法律の専門家ではありません。
NDAは、法的な権利と義務を定める極めて重要な「契約書」です。
特に5億円を超える規模の案件では、将来起こりうるあらゆるリスクを想定し、法的な観点から契約書を精査する必要があります。
これを惜しんで数万円〜数十万円の弁護士費用を節約した結果、数億円規模の損害や機会損失に繋がるリスクを考えれば、M&Aに精通した弁護士によるレビューは、必要不可欠な「保険」であり「投資」であると、私は断言します。
「これは弊社の標準書式でして…」への切り返し方
いざ修正を依頼すると、買い手の担当者から「これは弊社の標準書式でして、修正は難しいです」といった反応が返ってくることがよくあります。
ここで引き下がってはいけません。
私の父も中小企業の経営者でしたが、いつも「交渉は対等な立場でやるもんだ」と口にしていました。
その精神で、次のように切り返してみてください。
「ご提示ありがとうございます。もちろん、貴社を信頼しております。信頼しているからこそ、お互いにとって万一のリスク要因を完全に取り除き、安心して本件の検討に集中できる環境を整えたいと考えております。つきましては、弊社の顧問弁護士とも相談の上、双方にとってより公平で安全な形となるよう、いくつか修正のご相談をさせていただけますでしょうか。」
高圧的ではなく、あくまで「前向きな検討のため」という姿勢で、論理的に交渉することが肝要です。
費用を惜しむことが最大のコストになる
繰り返しになりますが、M&Aの初期段階で専門家への費用を惜しむことは、結果的に最大のコストを生む可能性があります。
NDAのレビューにかかる弁護士費用は、一般的に数万円から数十万円程度です。
この投資を怠ったために、不利な条項を見逃し、数千万円、数億円の事業価値を守る機会を失うことになれば、それこそ本末転倒です。
最初のボタンを正しくかける。
そのために必要なコストは、未来への投資だと考えてください。
よくある質問(FAQ)
Q: 仲介会社から「この雛形で問題ない」と言われましたが、信じて良いですか?
A: 仲介会社はM&A取引の専門家ですが、法律の専門家ではありません。
彼らの目的は取引を円滑に進めることであり、法務リスクの精査が主眼ではない場合があります。
5億円超の重要な取引においては、必ずM&A専門の弁護士によるセカンドオピニオンを得ることを強く推奨します。
これは仲介会社を疑うということではなく、役割分担の問題です。
Q: 秘密保持契約に違反された場合、本当に損害賠償を請求できるのですか?
A: 請求自体は可能です。
しかし、先述の通り、情報漏洩によって生じた「損害額」を具体的に立証することは非常に困難な場合があります。
そのため、事前に違約金条項を設けるなどの対策が有効になります。
何よりも、違反させないための抑止力としてNDAを機能させることが最も重要です。
Q: 複数の買い手候補と、同時にNDAを締結しても問題ありませんか?
A: 問題ありません。
むしろ、より良い条件の相手を見つけるためには、複数の候補と並行して交渉を進めるのが一般的です(これをコンペ形式と呼びます)。
ただし、その際は各社と締結するNDAに「独占交渉義務」が含まれていないか、必ず確認してください。
Q: 従業員には、どのタイミングでM&Aの話をすべきでしょうか?
A: M&Aを検討している事実は、経営の根幹に関わる最重要機密です。
情報漏洩は従業員の不安を煽り、士気の低下や人材の流出を招き、事業に深刻な影響を与えます。
NDAを締結した段階では、まだごく一部の役員(場合によっては経営者一人のみ)に限定すべきです。
従業員への開示は、M&Aが成約する直前、あるいは成約後が一般的です。
Q: NDAと基本合意書(LOI/MOU)の違いは何ですか?
A: NDAは、本格的な交渉に入る前に交わす「秘密を守る」ための契約です。
一方、基本合意書〈Letter of Intent / Memorandum of Understanding〉は、ある程度の交渉が進んだ段階で、その時点での買収価格やスケジュール、今後の進め方といった基本的な条件を確認・合意するために交わすものです。
通常、独占交渉権や秘密保持義務などを除き、法的拘束力はありません。
締結のタイミングも目的も全く異なるものとご理解ください。
まとめ
5億円超のM&Aにおける秘密保持契約(NDA)は、単なる手続き書類ではありません。
それは、経営者であるあなたが人生をかけて築き上げてきた会社の価値と、従業員の未来を守るための「最初の城壁」です。
買い手から提示された書面に安易に署名するのではなく、この記事で解説した10のチェックポイントを元に、自社の状況に合わせて主体的に内容を検討し、必要であれば臆せず交渉してください。
そして、この重要な局面では、信頼できるM&A専門の弁護士を「味方」につけることをためらわないでください。
最初のボタンを正しくかけることが、納得のいくM&Aを実現するための、最も確実な一歩となるのです。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。