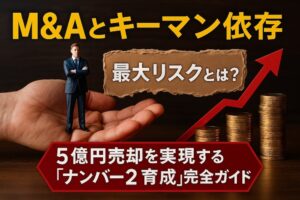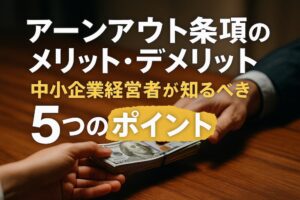M&Aとは?会社売却を成功させるために知っておくべき基礎知識

M&Aや会社売却と聞くと、自分とは無関係な大企業の世界の話だと思っていませんか。
しかし近年、後継者不在の問題解決や企業の新たな成長戦略として、中小企業にとってM&Aは極めて身近で現実的な選択肢となっています。
この記事では、会社売却を成功させるために不可欠な基礎知識を、売り手である経営者の視点から分かりやすく解説します。
特定の仲介会社やFA〈ファイナンシャル・アドバイザー〉の立場に偏らない公平な情報こそが、あなたの会社にとって最良の決断を下すための武器となります。
本記事を読めば、M&Aの全体像を掴み、成功への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
M&Aとは何か?~経営者のための基本~
M&Aは「合併と買収」の総称
では、そもそもM&Aとは何なのでしょうか。
M&Aとは、英語の “Mergers and Acquisitions” の略称です。直訳すると「合併と買収」となりますが、難しく考える必要はありません。
一言でいえば、会社の経営権を他の会社や個人に引き継ぐこと、とシンプルに捉えてください。
これには、株式の売買だけでなく、事業の一部だけを売却するなど、様々な手法が含まれます。
なぜ今、中小企業のM&Aが注目されるのか?
「最近、M&Aという言葉をよく聞くようになった」
そう感じている経営者様も多いのではないでしょうか。
その背景には、日本が抱える深刻な社会問題があります。
それは、「後継者不在」の問題です。
私の父も小さな町工場を経営していましたが、後を継ぐ者がおらず、事業の将来に頭を悩ませていました。
黒字経営で技術力があっても、担い手がいなければ会社は未来へ進めません。
こうした状況を解決する有効な手段として、M&Aによる第三者への事業承継が国からも推奨され、急速に普及しているのです。
会社売却は「終わり」ではなく「新たな始まり」
会社を売却すると聞くと、どこか寂しい響きを感じるかもしれません。
しかし、私が現場で見てきた多くのM&Aは、決してネガティブなものではありませんでした。
むしろ、会社と従業員の未来を守り、経営者自身が次のステージに進むためのポジティブな経営戦略なのです。
ある老舗の食品メーカーでは、大手企業の傘下に入ることで新たな販路と開発資金を得て、長年の夢だった海外展開を実現させました。
M&Aは会社の歴史の終わりではなく、新たな成長への扉を開く「始まり」でもあるのです。
【経営者視点】会社売却(M&A)のメリット・デメリット
M&Aを検討する上で、その光と影を正しく理解しておくことは極めて重要です。
売り手(経営者)にとっての5つのメリット
まずは、経営者様が享受できる主なメリットを見ていきましょう。
- 後継者問題の解決:血縁や社内に後継者がいなくても、会社の存続が可能になります。
- 創業者利益の獲得:会社を現金化し、引退後の生活資金や新規事業への投資資金を確保できます。
- 従業員の雇用維持:多くの場合、従業員の雇用は買い手企業に引き継がれ、生活を守ることができます。
- 個人保証からの解放:金融機関からの借入に対する経営者の個人保証や担保を解消できるケースがほとんどです。
- 事業の成長・発展:大手企業の傘下に入ることで、自社だけでは難しかった大きな成長が期待できます。
知っておくべき3つのデメリットと対策
一方で、当然ながらリスクも存在します。
事前に把握し、対策を講じることが肝心です。
- 希望条件で売却できるとは限らない:
- リスク:自社が考える価値と、買い手が評価する価値に乖離があることは珍しくありません。
- 対策:客観的な企業価値評価を行い、自社の強み(技術、顧客基盤など)を言語化・資料化しておくことが重要です。
- 従業員や取引先への影響:
- リスク:経営方針の変更により、企業文化が合わず従業員が離職したり、取引条件が見直されたりする可能性があります。
- 対策:買い手候補を選ぶ際に、自社の企業文化や理念を尊重してくれる相手かどうかを慎重に見極める必要があります。
- 情報漏洩のリスク:
- リスク:M&Aの検討が外部に漏れると、従業員の動揺や取引先の不安を招きかねません。
- 対策:情報管理を徹底し、信頼できる専門家と秘密保持契約を結んだ上で慎重に進めることが不可欠です。
M&Aの代表的な手法(スキーム)を分かりやすく解説
M&Aにはいくつかの手法〈スキーム〉がありますが、中小企業M&Aでは主に2つの手法が使われます。
最も一般的な「株式譲渡」とは?
これは、会社の株式を売買することで、経営権を丸ごと買い手に引き継ぐ手法です。中小企業M&Aの9割以上がこの株式譲渡で行われます。
手続きが比較的シンプルで、会社はそのまま存続するため、従業員の雇用や取引先との契約も原則として維持されるのが特徴です。
特定の事業だけを売却する「事業譲渡」
これは、会社そのものは手元に残しつつ、特定の事業部門だけを切り出して売却する手法です。
例えば、複数の事業を持つ会社が、不採算事業だけを整理したい場合や、主力事業に経営資源を集中させたい場合などに有効です。
ただし、資産や契約を個別に移転する必要があるため、株式譲渡に比べて手続きが煩雑になる傾向があります。
その他の手法(会社分割、株式交換など)
その他にも、会社を分割して承継させる「会社分割」や、自社の株式を対価に相手の会社を子会社化する「株式交換」など、様々な手法が存在します。
これらは主に組織再編や比較的規模の大きなM&Aで用いられるため、まずは「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つを基本として押さえておけば十分でしょう。


会社売却(M&A)の基本的な流れと期間
では、実際にM&Aはどのようなプロセスで進むのでしょうか。期間の目安とともに見ていきましょう。
STEP1:準備段階(3ヶ月~)
ここはM&Aの成否を分ける最も重要なフェーズです。
まず、「なぜM&Aをするのか」「何を達成したいのか」という目的を明確にします。
次に、この長い旅路を伴走してくれる信頼できる専門家を選定します。
そして、自社の企業価値がどの程度なのかを客観的に評価〈企業価値評価〉してもらいます。
私が現場で見てきた中で、焦ってこの準備段階を疎かにした結果、不利な条件で契約してしまったケースは少なくありません。
まさに「急がば回れ」です。
STEP2:交渉段階(3ヶ月~6ヶ月)
準備が整うと、いよいよ買い手候補を探し始めます。
専門家が作成した匿名の企業概要書〈ノンネームシート〉で候補先を探し、関心を示した企業と秘密保持契約を結んだ上で、より詳細な企業情報〈インフォメーション・メモランダム〉を開示します。
その後、経営者同士のトップ面談を経て、条件が合えば「基本合意契約」を締結します。
基本合意後、買い手側による詳細な企業調査、デューデリジェンス〈買収監査〉が行われます。
これは会社の健康診断のようなもので、財務・法務・事業などのリスクが徹底的に調査されます。
STEP3:最終契約・実行段階(1ヶ月~)
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な条件交渉を行います。
双方が合意に至れば、「最終契約書」を締結し、株式や代金の受け渡し〈クロージング〉を実行します。
これでM&Aは成立しますが、本当のスタートはここからです。
M&A成立後、両社が円滑に融合するための統合プロセス〈PMI:Post Merger Integration〉が成功して初めて、M&Aは真の成功と言えるのです。


【最重要】M&Aの専門家選びで成否が決まる
ここまでM&Aの全体像を解説してきましたが、最も重要なメッセージはここにあります。
なぜ専門家のサポートが不可欠なのか?
M&Aは、法務・税務・会計といった高度な専門知識の総合格闘技です。経営者様が本業の傍ら、これら全てに対応するのは現実的ではありません。
私が金融機関時代に見た失敗例の多くは、専門家選びに起因するものでした。
例えば、知識が不十分な専門家に依頼したため、後から多額の税金が発生することが判明したケースなどです。
適切な専門家は、複雑なプロセスにおける羅針盤であり、経営者の利益を守る盾となるのです。
M&Aの相談先:それぞれの特徴と役割
では、誰に相談すればよいのでしょうか。
それぞれの特徴を中立的な視点で解説します。
M&A仲介会社
売り手と買い手の間に入り、中立的な立場でマッチングと交渉を支援します。幅広いネットワークが魅力です。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)
売り手か買い手のどちらか一方の代理人となり、利益の最大化を目指します。
銀行・証券会社
主に取引のある顧客向けにM&Aサービスを提供します。安心感がありますが、紹介先が系列内に限られることもあります。
税理士・弁護士
顧問先のM&Aを支援するケースが増えています。ただし、M&Aの実務経験が豊富かどうかは個別に確認が必要です。


「仲介」と「FA」の決定的な違いとは?
特に混同されがちなのが「仲介」と「FA」です。これは決定的に違います。
M&A仲介は「不動産仲介」のように、売り手と買い手の間に立ちます。双方から手数料を得るため、構造的に利益が相反する〈利益相反〉可能性があります。


一方、FAは「弁護士」のように、完全にあなたの味方です。あなたの利益を最大化するためだけに動きます。
どちらが良いという話ではなく、会社の規模や状況、交渉方針によって最適な選択は異なります。
この違いを理解した上で、どちらの形態が自社に合っているかを考えることが重要です。
信頼できる専門家を見極める3つのポイント
最後に、私が提唱する「経営者のための専門家選定基準」をお伝えします。
1. 実績や専門分野の確認
「自社と同じ業種や規模のM&Aを手掛けた実績はありますか?」と具体的に質問しましょう。
2. 料金体系の透明性
成功報酬の計算方法(レーマン方式など)について、「報酬の計算ベースは株式価値ですか?それとも負債を含めた移動総資産ですか?」と確認してください。これで支払額が大きく変わります。
3. 担当者との相性
最終的には「人」です。あなたの会社の歴史や従業員への想いを真摯に受け止め、尊重してくれる担当者かを見極めてください。
よくある質問(FAQ)
Q: 会社を売却するのに、どれくらいの費用がかかりますか?
A: M&A専門家への報酬が主です。
着手金、中間金、成功報酬などがあり、料金体系は様々です。
特に成功報酬は「レーマン方式」という計算方法が一般的で、取引額5億円以下の部分は5%といった料率が設定されています。
契約前に必ず複数の専門家から見積もりを取り、料金体系を比較検討することが重要です。
Q: 自分の会社がいくらで売れるのか、どうすれば分かりますか?
A: 企業の価値を算定する「企業価値評価」によって目安を知ることができます。
評価方法には純資産を基準にする方法や、将来の収益力を基準にする方法など複数あります。
ただし、これはあくまで目安です。
最終的な売却価格は、買い手との交渉や、技術力・ブランドといった数字に表れない「見えない価値」も加味されて決まります。
Q: 会社を売却したら、従業員の雇用はどうなりますか?
A: 多くのM&Aでは、従業員の雇用は維持されることが最終契約の条件に含まれます。
買い手にとっても、事業を支える人材は貴重な財産だからです。
むしろ、買い手企業の傘下に入ることで福利厚生が充実するなど、待遇が改善されるケースも少なくありません。
従業員の将来を最優先に考えることが、良いM&Aの絶対条件です。
Q: 会社を売却することを、いつ従業員や取引先に伝えればよいですか?
A: 情報管理はM&Aにおいて最も神経を使う部分です。
一般的には、最終契約が締結される直前か、締結後に伝えるのがセオリーです。
不適切なタイミングでの情報漏洩は、従業員の離反や取引の停止に繋がる致命的なリスクがあります。
開示のタイミングと方法は、必ず専門家と慎重に協議して決めてください。
Q: M&Aの交渉が始まったら、断ることはできますか?
A: はい、最終契約を締結するまでは断ることが可能です。
特に「基本合意契約」の段階では、独占交渉権などを除き、法的な拘束力がない場合がほとんどです。
私が常に経営者様にお伝えしているのは、「納得感」が何よりも大切だということです。
条件が合わなければ、勇気をもって交渉を中断する決断も必要です。
まとめ
本記事では、会社売却を検討し始めた経営者の皆様に向けて、M&Aの基礎知識を網羅的に解説しました。
重要なのは、M&Aが単なる会社の売買ではなく、従業員や取引先、そして経営者自身の未来を左右する重要な経営戦略であると理解することです。
そして、その成否は、どの専門家をパートナーに選ぶかに大きくかかっています。
特定の立場に偏らない公平な情報を武器に、ご自身の会社にとって最も納得感のある選択をしてください。
元金融機関、そして今は完全に中立な専門家として、私は経営者が適切な情報に基づいて最良の意思決定を下せるよう、これからも支援を続けていきます。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。