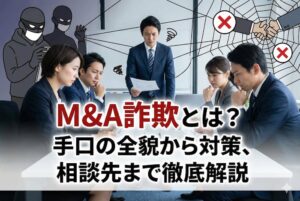キーマン条項(ロックアップ)とは?M&A専門家が期間、メリット・デメリット、注意点を徹底解説
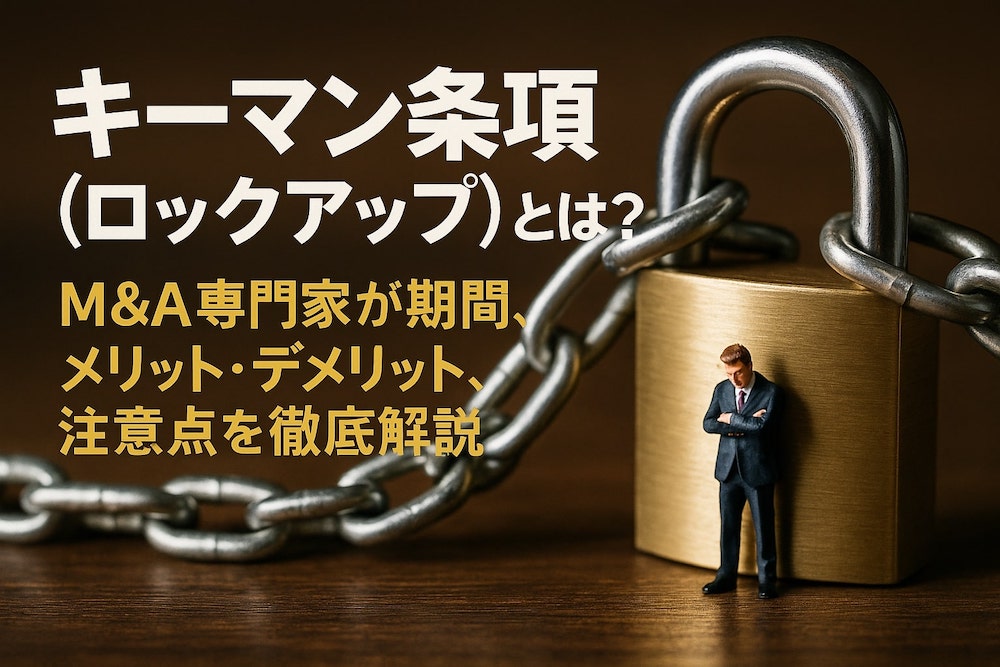
M&Aを決断された経営者の皆様が、最終契約を前に最も気になることの一つが「M&A後のご自身の処遇」ではないでしょうか。
その中心的な論点となるのが「キーマン条項(ロックアップ)」です。
これは、M&A後も一定期間、会社に残り事業の引継ぎをサポートすることを約束する条項ですが、期間や報酬、業務範囲の交渉はM&Aの成否を分けるほど重要です。
本記事では、特に5億円規模のM&Aを目指す売り手経営者の視点から、キーマン条項の基本から、金融機関出身者だからこそ語れるリアルな交渉術、注意点までを徹底的に解説します。
キーマン条項(ロックアップ)とは?M&Aにおける目的を専門家が解説
では早速、キーマン条項の核心に迫っていきましょう。
この条項は、一体誰のために、何のために存在するのでしょうか?
なぜキーマン条項が必要なのか?買い手の本音
結論から申し上げると、キーマン条項は、買い手にとって「買収した事業の価値が損なわれないようにするための保険」のようなものです。
買い手は、貸借対照表に載っている資産だけを買っているのではありません。
むしろ、経営者にしか分からないノウハウや長年かけて築き上げた取引先との信頼関係、そして組織に根付いた文化といった「目に見えない資産」にこそ、大きな価値を見出しているのです。
金融機関時代、私は買い手企業のデューデリジェンス〈買収監査〉に何度も立ち会いましたが、彼らが最も恐れているのは、M&Aの直後に創業社長が退任し、これらの無形資産が失われてしまうことでした。
キーマンの離脱が引き金となり、他の優秀な従業員の連鎖退職を招き、事業が根幹から崩壊してしまう。
これは、M&A後の統合プロセス〈PMI〉における典型的な失敗パターンなのです。
つまり買い手は、事業そのものだけでなく、「社長の頭の中と人脈」にも対価を支払っているのです。
だからこそ、その価値をスムーズに移転させるために、キーマンである社長に一定期間残ってほしいと強く願うわけです。
売り手にとってのキーマン条項の位置づけ
一方で、売り手である経営者の皆様にとって、この条項はどのように捉えるべきでしょうか?
もちろん、一定期間の拘束を受けるという側面はあります。
しかし、私はこれを単なる「縛り」ではなく、戦略的に活用すべき「交渉カード」の一つだと考えています。
なぜなら、キーマン条項に合意することは、円滑な事業承継を実現し、大切に従業員や取引先に安心感を与えるという重要な役割を果たすからです。
「社長が残ってくれるなら安心だ」という雰囲気は、M&A後の混乱を最小限に抑え、事業の安定的な成長に繋がります。
さらに、これは売却価格の増額要因にもなり得ます。
私が以前支援したある製造業のケースでは、後継者不在に悩む老舗企業でしたが、社長が「3年間は私が責任をもって引き継ぎます」と約束したことで、買い手からの信頼が格段に高まり、当初の提示額から10%以上高い価格での売却に成功しました。
このように、キーマン条項はご自身のM&A後の自由と、会社の未来や売却条件を天秤にかける、極めて戦略的な交渉事項なのです。
【売り手・買い手別】キーマン条項のメリット・デメリットを徹底比較
物事には必ず両面性があります。
キーマン条項も例外ではありません。
ここでは、売り手と買い手、双方の立場からメリット・デメリットを整理し、交渉の全体像を掴んでいきましょう。
売り手経営者が享受できるメリット
まず、売り手である皆様が享受できる最大のメリットは、やはり「より有利な条件を引き出せる可能性」です。
売却価格の向上
先ほどの例のように、キーマンの残留は買い手にとって明確な付加価値であり、価格交渉における強力なカードとなります。
円満な事業承継の実現
ご自身が心血を注いで育てた会社が、M&A後もスムーズに運営され、成長していく姿を見届けることができます。これは何物にも代えがたい精神的な満足感に繋がります。
従業員・取引先への責任
「会社を売って終わり」ではなく、引継ぎまで責任を持つ姿勢を示すことで、従業員の雇用維持や取引先との関係継続に繋がり、周囲からの信頼を維持できます。
売り手経営者が直面するデメリットとリスク
一方で、光が強ければ影も濃くなります。
デメリットとリスクも正しく理解しておく必要があります。
自由の制約
最も大きなデメリットは、M&A後も一定期間、会社に拘束されることです。すぐに新しい事業を始めたい、あるいは悠々自適の引退生活を送りたいと考えている経営者にとっては、大きな足枷となり得ます。
立場の変化とモチベーション維持の難しさ
これが、私が現場で見てきた中で最も多くの経営者が直面する壁です。
昨日まで「オーナー経営者」として全ての意思決定を行っていた方が、明日からは「雇われる立場」の役員になる。稟議書やレポーティングが求められ、これまで鶴の一声で決めていたことが、会議で否定されることもある。
この環境の変化に耐えられず、モチベーションを維持することが難しくなるケースは決して少なくありません。
買い手側のメリット・デメリット
交渉を有利に進めるには、相手の立場を理解することが不可欠です。
買い手側のメリット・デメリットも見ておきましょう。
メリット
事業の継続性を担保し、買収価値の毀損リスクを最小化できること。これに尽きます。キーマンから事業の機微や暗黙知を引き継ぐことで、PMIを成功に導くことができます。
デメリット
キーマンのモチベーション低下リスクを抱えることになります。また、想定以上の役員報酬や退職金が発生するコストリスクも考慮しなければなりません。売り手経営者が「お飾り」の役員になってしまい、高額な報酬だけが発生する状態は、買い手にとっても避けたい事態なのです。
このように、双方のメリット・デメリットを理解することで、お互いの妥協点が見えやすくなります。
キーマン条項の「期間」はどのくらい?相場と交渉のポイント
では、具体的にロックアップの期間はどのくらいが一般的なのでしょうか?
これは最もご質問が多い点の一つです。
一般的な期間の相場は1年~3年
多くのM&A専門サイトが示す通り、実務上の期間の相場は「1年~3年」がひとつの目安となります。
- 1年: 事業内容が比較的シンプルで、後任への引継ぎが短期間で完了する場合。
- 2~3年: 経営者への依存度が高い事業や、特殊な技術・ノウハウの承継に時間が必要な場合。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。
企業の規模や事業の複雑性、後継者の有無などによって期間は大きく変動します。
5億円規模のM&Aにおけるリアルな期間設定
私が専門とする企業価値5億円規模の中小企業M&Aに絞ってお話しすると、もう少し解像度が上がります。
この規模の会社は、良くも悪くも創業者である社長への依存度が非常に高い傾向があります。
俗にいう「属人化」です。
そのため、買い手としては事業の円滑な引き継ぎのために、最低でも2年、できれば3年のロックアップを求めてくるケースが非常に多いのが実態です。
中小企業白書のデータ[1]を見ても、事業承継後も先代経営者の多くが何らかの形で会社に関与し続けていることが分かります。これは、引継ぎには相応の時間が必要であることの裏付けとも言えるでしょう。
期間を交渉する際の戦略的アプローチ
買い手から「3年」と提示された場合でも、鵜呑みにする必要は全くありません。
「期間の短縮」と「売却価格の維持・向上」を両立させるための交渉は十分に可能です。
重要なのは、代替案とセットで交渉することです。
例えば、以下のようなアプローチが考えられます。
後継者の存在をアピールする
「No.2である〇〇専務にほとんどの業務を移譲済みですので、私自身は1年で十分引き継げます」と、優秀な後継者の存在を具体的に示す。
業務のマニュアル化を提示する
「主要な業務は全てマニュアル化・標準化を進めています。この資料があれば、引継ぎはスムーズに進みます」と、属人性を排除する努力をアピールする。
顧問契約を代替案とする
「代表取締役としてのロックアップは1年とさせていただき、その後2年間は顧問として週1日の稼働でサポートするのはいかがでしょうか」と、関与度合いを段階的に下げる提案をする。
ただ「短くしてほしい」と要求するのではなく、買い手の不安を払拭する合理的な根拠を示すことが、交渉を成功に導く鍵となります。
キーマン条項における「報酬」の考え方と交渉術
期間と並んで重要なのが、ロックアップ期間中の「報酬」です。
これはM&A後の生活設計だけでなく、モチベーションを維持するための重要なインセンティブとなります。
役員報酬の基準と決め方
M&A後の役員報酬は、一般的に「M&A前の役員報酬額」をベースに、買い手企業の報酬体系とのバランスを考慮して決定されます。
交渉の場で提示すべきは、客観的な根拠です。
「これまでこれくらい貰っていたから」という主張だけでは不十分です。
ご自身の業務内容、責任範囲、そしてM&A後の会社への貢献度を具体的に言語化し、報酬額の妥当性を論理的に説明する必要があります。
アーンアウト条項との組み合わせで報酬最大化を狙う
ここで、より高度な交渉術として「アーンアウト条項」の活用をご紹介します。
M&A実行後の一定期間内に、売上高や利益などの予め定めた経営目標を達成した場合、売り主が買い主から追加の対価を受け取ることができる契約条項。
これは、M&A後の業績に応じて追加の売却代金が支払われる仕組みです。
例えば、「ロックアップ期間中の2年間で、EBITDA〈税引前利益に支払利息、減価償却費を加算した利益〉を年率10%成長させたら、追加で〇〇円支払う」といった契約を結びます。
このアーンアウト条項をキーマン条項と組み合わせることで、売り手にとっては「目標達成のインセンティブ」となり、高いモチベーションを維持しやすくなります。
そして、目標を達成すれば当初の売却価格以上のリターンを得ることも可能です。
買い手にとっても、買収後の業績と連動するためリスクが低く、双方にとってメリットのある仕組みと言えます。
ただし、目標設定の指標(売上なのか、利益なのか)や達成条件を巡ってトラブルになるケースもあるため、契約内容の精査には細心の注意が必要です。
【M&A専門家が教える】キーマン条項を契約書に盛り込む際の重要注意点
交渉がまとまったら、最後は契約書への落とし込みです。
口約束は意味を成しません。
ここでは、後々のトラブルを避けるために、契約書で必ず確認すべき3つの重要ポイントを解説します。
業務範囲と権限を明確に定義する
「M&A後も社長として事業の引継ぎを行う」といった曖昧な表現は非常に危険です。
「社長」という肩書は同じでも、オーナー社長と雇われ社長では権限が全く異なります。
- 具体的な業務内容: 何を担当し、何を担当しないのか。
- 役職とレポートライン: 誰に報告し、誰から指示を受けるのか。
- 決裁権限: いくらまでの金額を、誰の承認なしに決裁できるのか。
これらの点を可能な限り具体的に契約書に明記することが、M&A後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐ最大の防御策です。
私が過去に見た失敗例では、業務範囲が曖昧だったために、本来想定していなかった雑務まで押し付けられ、疲弊してしまった元オーナー社長がいらっしゃいました。
善意の離職者条項(Good Leaver/Bad Leaver)とは?
もし、ロックアップ期間中にご自身の病気や家族の介護など、やむを得ない事情で退任せざるを得なくなったらどうなるでしょうか?
その場合に備えるのが「Good Leaver/Bad Leaver条項」です。
- Good Leaver(善意の離職者): 死亡、重大な疾病、会社の都合による解任など、本人に責任のない理由での退任。
- Bad Leaver(悪意の離職者): 横領などの不正行為、重大な契約違反、正当な理由なき辞任など。
契約書に「Good Leaver条項」を盛り込むことで、やむを得ない事情で退任する場合に、違約金などのペナルティを課されることなく、円満に契約を終了できる可能性が生まれます。
これは専門家でなければ見落としがちな、非常に重要なリスク管理の視点です。
競業避止義務の範囲と期間を確認する
ロックアップとセットで定められることが多いのが「競業避止義務」[2]です。
これは、ロックアップ期間中および終了後の一定期間、同業種での事業を行うことを制限する条項です。
買い手からすれば当然の要求ですが、売り手はその範囲と期間が妥当であるか、慎重に確認する必要があります。
- 期間: 会社法では原則20年と定められていますが、実務上は2~5年程度で交渉するのが一般的です。
- 範囲(地域・業種): 「日本全国で、全てのIT関連事業を禁止する」といった広すぎる制限は、不当に職業選択の自由を奪うものとして、無効と判断される可能性があります。
ご自身のセカンドキャリアを不当に縛られることがないよう、弁護士などの専門家を交えて、契約書の文言を精査することが不可欠です。
よくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様からよくいただく質問にお答えします。
Q: キーマン条項(ロックアップ)を拒否することはできますか?
A: 結論として、拒否することは可能です。
しかし、買い手からの信頼が大きく損なわれ、売却価格が大幅に引き下げられたり、最悪の場合、交渉そのものが決裂したりするリスクを覚悟する必要があります。
私の見解としては、全面的に拒否するのではなく、これまで解説してきたように「期間」「報酬」「業務範囲」といった条件を、ご自身が納得できる水準まで粘り強く交渉するアプローチが現実的です。
Q: ロックアップ期間中に退職した場合、ペナルティはありますか?
A: はい、契約違反となり、買い手から損害賠償を請求される可能性があります。
だからこそ、前述した「Good Leaver条項」を契約に盛り込み、やむを得ない事情での退任に備えることが非常に重要なのです。
リスクを未然に防ぐことこそ、専門家の重要な役割だと考えています。
Q: キーマンは経営者だけが対象ですか?
A: いいえ、経営者だけとは限りません。
例えば、特殊な技術を持つ開発責任者や、大口取引先との関係を一人で担っている営業部長など、その人がいなくなると事業の継続が困難になる人物は誰でもキーマンになり得ます。
誰をキーマンとしてロックアップの対象に含めるかは、M&Aの交渉における重要な論点の一つです。
Q: M&A仲介会社やFAは、キーマン条項の交渉でどのような役割を果たしますか?
A: 彼らは、売り手と買い手の間に立ち、双方の希望を調整し、現実的な落としどころを探る「調整役」を担います。
ただし、ここで注意が必要です。
M&A仲介会社は双方の利益を最大化しようとしますが、FA〈ファイナンシャル・アドバイザー〉は、売り手か買い手、どちらか一方の利益を最大化するために動きます。
ご自身がどちらの専門家と契約しているのかを理解し、彼らの知見を最大限に活用することが重要です。
中小企業庁もガイドラインで支援機関の役割を定めており、経営者自身が賢く専門家を選ぶ時代になっています。
まとめ
キーマン条項(ロックアップ)は、単なる「M&A後の縛り」ではありません。
それは、売り手経営者が長年かけて築き上げてきた会社の価値を、次の担い手へ正しく引き継ぎ、ご自身の貢献に見合った正当な対価を得るための、極めて重要な「戦略的ツール」です。
期間、報酬、業務範囲、そして契約書の細かな条文。
これらを曖昧なままにせず、時にはM&Aアドバイザーや弁護士といった専門家と緊密に連携しながら、一つひとつ丁寧に交渉を重ねていく。
そのプロセスこそが、「納得感のあるM&A」の実現に不可欠なのです。
本記事で得た知識が、皆様にとって強力な武器となることを願っています。
買い手と対等な立場で交渉に臨み、ご自身の輝かしいキャリアの、次なる素晴らしい扉を開いてください。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。
参考文献
[1] 第1節 事業承継・M&A
[2] 競業避止義務の明確化について