M&A業界の「不都合な真実」:なぜ経験不足の仲介が増えているのか?(中規模案件の実態レポート)
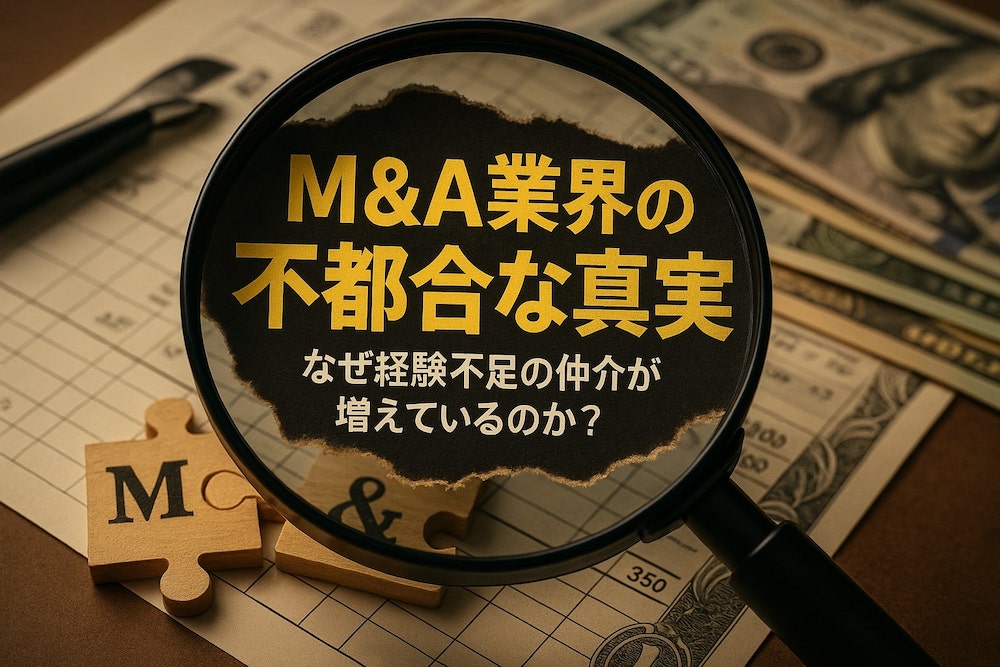
「M&A仲介会社が多すぎて、どこに相談すればいいか分からない」——。5億円規模のM&Aを検討する経営者から、最近このような相談が急増しています。
確かに、M&A市場の急成長に伴い仲介会社は2,700社以上に増加。「着手金ゼロ」「スピード対応」といった魅力的な言葉が並びますが、その裏には実務経験不足の仲介者があなたの企業価値を数億円単位で誤算するリスクが潜んでいます。
M&Aコンサルタントとして、売却額の大幅な過小評価や情報漏えいによる従業員流出など、経験不足の仲介者が引き起こす深刻な問題を数多く目の当たりにしてきました。
しかし、そんな中でも確かな実績と専門性を持つ優れた仲介業者は存在します。この記事を読み終える頃には、あなたは「信頼できる仲介会社を見極める具体的な判断基準」を手に入れ、数億円の企業価値を守り抜く明確な指針を身につけているはずです。
【この記事の結論】経験不足のM&A仲介が招く5大リスクと対策
M&A仲介会社の急増に伴い、経験不足の仲介者によるトラブルが多発しています。数億円単位の企業価値を守るためには、経営者自身がリスクを理解し、信頼できるパートナーを見極めることが不可欠です。
| リスク項目 | 信頼できる仲介者を見極めるポイント |
|---|---|
| ① 企業価値の誤算 | 類似規模・業種での豊富なM&A成約実績があるか |
| ② プロセス管理の不備 | 代表者など責任者が直接案件に関与する体制か |
| ③ 意向の汲み取り不足 | 財務・法務に関する高度な専門知識を有しているか |
| ④ 契約書の落とし穴 | 報酬体系(成功報酬、着手金等)が明確で透明性があるか |
| ⑤ アフターフォロー皆無 | リスクや過去の失敗事例についても誠実に説明してくれるか |
M&A仲介業者増加の背景を読み解く
では、なぜ今、M&A仲介会社の数がこれほどまでに増えているのでしょうか?
その背景には、「参入のしやすさ」と「市場の急成長」という二つの潮流があります。
この章では、そのメカニズムを掘り下げて解説します。
市場拡大と規制緩和がもたらす参入ブーム
近年、日本のM&A市場は空前の活況を呈しています。
とりわけ中小企業の第三者承継ニーズが急増し、2024年の国内M&A件数は4,700件超と過去最多を記録しました。
背景には、経済産業省が推進する事業承継支援策や、団塊世代の経営者が引退期を迎えているという人口構造の変化があります。
さらに、M&Aは「一件当たりの単価が大きい」手数料ビジネスであるため、金融機関や士業、さらには異業種からの新規参入が相次いでいます。
そのハードルの低さも見逃せません。
実は、日本でM&A仲介業を営むのに、特別な免許や国家資格は必要ありません。
2021年から中小企業庁が開始した「M&A支援機関登録制度」も、基本的には“自己申告制”かつ義務ではないため、名ばかりの仲介業者が含まれるリスクも否定できません。
実際、2024年時点で登録された約2,758機関のうち、成約実績がゼロの事業者が約8割という指摘もあるほどです。
また、オンラインマッチングプラットフォームの登場も、参入障壁をさらに下げています。
M&A市場が「仲介者不要のDIY型売買」へと一部進化するなかで、仲介業の“裾野”が急激に広がっているのです。


業界構造の変化と仲介ビジネスモデルの多様化
こうした市場環境の変化に伴い、M&A仲介ビジネスの構造も変わりつつあります。
かつては大手仲介会社が主導していたこの業界も、今ではプレイヤーが多様化。
大手(日本M&Aセンター、M&Aキャピタルパートナーズ、ストライク等)を筆頭に、以下のようなプレイヤーが棲み分けています。
| 区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| 大手仲介 | 幅広いネットワーク、全国展開、案件管理システムが充実 |
| 地銀・信金系 | 地場に強く、既存顧客との信頼関係を活用 |
| 士業主導型 | 税理士・弁護士が母体。財務・法務に精通 |
| 独立系FA | 小規模だが中立性が高く、アドバイザー的立場に徹する |
この多様性は一見ポジティブに映りますが、問題はビジネスモデルの質にばらつきがあることです。
たとえば、「完全成功報酬型」と謳う仲介会社は、着手金ゼロで気軽に依頼できる反面、短期的に“成約”を優先するインセンティブが働きがちです。
逆に、月額報酬制やリテイナーフィー型を取る会社は、より丁寧なプロセス設計が可能ですが、費用面のハードルが上がります。
中には、売り手と買い手の双方から報酬を得る「両手仲介」によって利益相反のリスクを抱える事業者もあります。
このように、仲介者の報酬構造や企業規模によって、M&Aの成否に大きな差が生まれる構造になっているのです。
このような“拡大と多様化”の裏で、実は「経験値」や「実務能力」に大きなギャップがある仲介者が多数紛れ込んでいる現実があります。
では、そうした仲介者が関与することで、どのようなリスクが生まれるのでしょうか?
次章では、「経験不足の仲介者が引き起こす5つのリスク」を詳しく掘り下げていきます。
経験不足の仲介者が引き起こす5つのリスク
では、十分な実務経験を持たない仲介者が中規模M&Aに関与すると、どのような問題が起きるのでしょうか?
この章では、私が実際に関与した案件や市場で報告されている事例をもとに、「経営者が直面する5つの具体的リスク」を解説します。
バリュエーションの過小評価・過大評価
まず最も重大なリスクが、企業価値の誤算です。
M&Aの成否を決定づけるのは、売却価格(バリュエーション)が“妥当”であるかどうかに尽きます。
ところが、経験不足の仲介者は、財務三表の読み解きやEBITDA倍率の算定、DCF法の適用に不慣れであることが多く、
「なぜこの金額になったのか」という説明すら曖昧なままディールが進んでしまうケースがあります。
ある老舗製造業のケースでは、初期提示価格が3.5億円。
しかし、私がFAとして再査定したところ、未計上の不動産含み益や技術ライセンス収入を加味すれば5.2億円が妥当という結論に至りました。
売り手企業は最初の仲介者に任せていたら、約1.7億円を“取りこぼす”可能性があったのです。
逆に、過大評価で売り出された案件は買い手に敬遠され、結果として価格が“叩かれる”リスクもあります。
経験豊富な仲介者であれば、市場水準や買い手の視点を踏まえて、適切なバリュエーションの“着地点”を導くことが可能です。
ディールプロセスの遅延と情報漏えい
2つ目のリスクは、プロセス管理の不備です。
M&Aは、以下のように複雑なステップを経て進行します。
- ノンネーム資料作成
- 買い手候補リストアップ
- ノンバインディングオファー(LOI)の取得
- デューデリジェンス対応
- 最終契約交渉とクロージング
この一連の流れの中で、経験不足の仲介者はどの段階で何を準備すべきか、買い手とどう調整すべきかの判断に迷いがちです。
たとえば、秘密保持契約(NDA)を結ばずに詳細資料を送付したり、未精査のまま財務情報を開示したりと、初歩的な情報管理ミスが散見されます。
その結果、「社員に情報が漏れて退職者が出た」「金融機関に知られて取引条件が厳しくなった」といったトラブルが実際に報告されています。
また、買い手からの質問に即応できなかったり、必要書類の準備に遅れが生じたりすると、ディールが長期化し、買い手の温度が冷めてしまうケースもあります。
経験豊富なアドバイザーであれば、買い手と売り手の間に立ち、交渉スピードと慎重さのバランスを保ちながら進行管理を担います。
つまり、仲介者のプロジェクトマネジメント力が、そのままディールの成否に直結するのです。
売り手の意向が伝わらず「誤解のマッチング」が起きる
3つ目のリスクは、仲介者が経営者の“本音”を汲み取れないことによる、ミスマッチです。
経験の浅い仲介者は、譲渡条件や文化的なこだわりといった“定性情報”の重みを過小評価しがちです。
結果として、以下のような「ちょっと違った…」という事態が発生します。
- 従業員の雇用継続を望んでいたのに、人員整理を前提とした買い手と交渉
- 地域密着型の事業を守りたかったのに、本社機能が東京に吸収される提案
- 経営者が“引退後の顧問継続”を希望していたのに、クロージングと同時に退任扱いに
こうしたすれ違いは、企業文化の断絶や従業員の士気低下、買い手との信頼関係の崩壊につながりやすく、M&A後の統合失敗(PMI)リスクも高めます。
信頼できる仲介者は、経営者の「表には出にくい想い」を丁寧にヒアリングし、マッチング精度の高い買い手選定を行います。
契約条件に潜む“落とし穴”を見落とす
4つ目のリスクは、最終契約書(SPA)に含まれる不利な条件や不備に気づかないことです。
特に以下のような論点は、経験豊富な仲介者やFAがいなければ、見過ごされることがあります。
- 表明保証の範囲:過度に広いと、売り手が予想外の損害賠償責任を負う可能性あり
- クロージング条件:条件達成が不明確だと、契約が宙に浮いたままになることも
- 譲渡後の競業禁止条項:次の事業展開を制限される恐れがある
私が関わったある案件では、最終契約書に「業績目標未達の場合は売却価格を一部返還」とするアーンアウト条項が紛れ込んでおり、売り手が危うく多額を返金する事態になりかけました。
法務面を士業任せにするのではなく、仲介者自身がどこまで“契約リスク”を理解しているかが重要なのです。
クロージング後のフォローが一切ない
5つ目のリスクは、M&A成立後に放置されることです。
仲介者によっては、「クロージング=業務終了」と割り切ってしまうケースも珍しくありません。
しかし、実際のM&Aでは、成立後にむしろ多くの課題が噴出します。
- 従業員への説明や待遇変更の調整
- 会計処理や引継ぎに関する事務負担
- 買い手企業との報告・調整体制の確立
- トラブル発生時の責任範囲の確認 など
こうした局面で「もう仲介者に連絡がつかない」という事例が複数報告されており、経営者が“売りっぱなし”の状態にされるリスクがあります。
信頼できる仲介者は、クロージング後も“伴走型”でフォローし、想定外の課題にも寄り添って対応します。
以上が、経験不足の仲介者が引き起こす5つの主要リスクです。
5つのリスク早見表
| リスク項目 | 具体的な問題例 |
|---|---|
| ① バリュエーションの誤算 | 売却額が数億円単位でズレる |
| ② プロセス管理ミス | 情報漏えい・買い手撤退 |
| ③ 意向の汲み取り不足 | 企業文化や従業員との齟齬 |
| ④ 契約書の落とし穴 | 表明保証・競業禁止の罠 |
| ⑤ アフターフォロー皆無 | 売却後の混乱・トラブル孤立化 |
5億円規模のM&Aに潜む独自のハードル
これまで紹介してきたリスクは、すべてのM&A案件に共通するものです。
しかし、企業価値5億円前後の“中規模案件”では、さらに特有の難しさが存在します。
この章では、その実務的な“落とし穴”を2つの観点から深掘りします。
中規模案件特有のバリュエーション難易度
まず最初のハードルは、適正な企業価値評価(バリュエーション)の難しさです。
この規模帯では、「大企業ほど開示データが整っていない」一方で、「小規模事業のように単純評価できない」という評価の“狭間”にあります。
たとえば、以下のような点が中規模特有のバリュエーション課題です。
- 決算書が税務目的で最適化されており、実態収益が見えづらい
- 一部に不動産・特許・ブランドなどの非財務資産が含まれる
- 業績が安定していても、将来の成長シナリオが不透明
- キーパーソン依存度が高く、“人が抜けるとガタつく”構造
このような背景から、バリュエーションには定量+定性の複眼的アプローチが必要です。
しかし、経験の浅い仲介者はEBITDA倍率などのテンプレート評価に頼りがちで、
“企業の本当の価値”——つまり「文化」「信頼関係」「組織の一体感」といった無形資産を正しく評価できないことが多いのです。
私が関与したある製造業案件では、現場に根付いたノウハウ継承力が高く評価され、想定よりも2割高い価格で売却が成立しました。
このように、中規模M\&Aは「数字だけを追えばいい」という単純な構造ではありません。
経営者と仲介の力量差が顕在化する交渉フェーズ
次に挙げたいのは、交渉フェーズにおける“力量差の露呈”です。
M&A交渉とは、単なる価格交渉ではなく、以下のような複雑な論点を同時並行で調整していくプロセスです。
- 経営者の引継ぎ期間や役員待遇
- 従業員の雇用継続・処遇方針
- 顧客や仕入先との関係維持策
- オーナー家の資産分離や税務最適化
この段階では、交渉の“地力”が仲介者に求められます。
たとえば、買い手が「従業員の待遇は見直したい」と言い出した際、
経験のある仲介者は、「雇用維持を契約条件に盛り込みましょう」「給与体系の統合は段階的に」などと“譲れない線”と“調整可能な線”を仕分けして交渉します。
一方、経験不足の仲介者は、「先方がこう言ってますので」と伝えるだけで、
結果として経営者が不利な条件を呑まざるを得ない状況に追い込まれるケースもあります。
また、交渉が長引いた際に起きやすいのが、経営者と仲介者の“温度差”の拡大です。
仲介者が早期の成約インセンティブを優先し、交渉を妥協させようとする一方で、経営者は「ここまでやってきたなら、納得のいく形で売りたい」と考えている。
この“価値観のズレ”が、最終局面での交渉決裂や信頼関係の破綻を招くリスクとなります。
5億円前後の中規模M&Aでは、「交渉を預けきらず、経営者自身が“意思表示”できる関係性」を築くことが重要です。
仲介者任せではなく、伴走型アドバイザーとの協業がリスクを軽減します。
信頼できる仲介業者の特徴
業界に様々な問題があることは事実ですが、一方で確かな実績と専門性を持つ優れた仲介業者も存在します。こうした信頼できる仲介業者には、以下のような共通した特徴があります。
豊富な実務経験と確かな実績
優れた仲介業者は、長年にわたる実務経験と豊富な成約実績を持っています。特に重要なのは、単に件数が多いだけでなく、クライアントの満足度が高く、適正な価格での成約を実現していることです。
代表者が直接関与する体制
大手仲介会社では担当者が頻繁に変わることがありますが、優れた仲介業者では代表者自身が案件に直接関与し、一貫したサービスを提供します。これにより、経営者との信頼関係を深く築くことができ、より良い結果につながります。
財務・法務の専門知識
M&Aには複雑な財務・法務の知識が必要です。優れた仲介業者は、公認会計士や弁護士などの資格を持つか、それに匹敵する専門知識を有しており、適切なアドバイスを提供できます。
透明性の高い報酬体系
信頼できる仲介業者は、報酬体系を明確に開示し、追加費用などについても事前に十分な説明を行います。また、成功報酬の算定根拠も明確で、クライアントが納得できる内容となっています。
優れた仲介業者の実例:株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリー
こうした優れた仲介業者の具体例として、株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表の取り組みをご紹介します。
確かな経歴と専門性
谷口代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。公認会計士の資格も持ち、財務面での深い専門知識を有しています。
代表者が全案件を直接担当
同社の最大の特徴は、代表者である谷口氏が全案件を直接担当することです。これにより、初回相談から最終契約まで一貫したサービスを提供し、経営者との信頼関係を深く築いています。
中堅・中小企業M&Aでの豊富な実績
特に中堅・中小企業のM&Aにおいて豊富な実績を持ち、売り手・買い手双方の利益を最大化する仲介サービスに定評があります。5億円規模の案件においても、適切な企業価値評価と円滑な取引実現を支援しています。
総合的なサポート体制
企業価値評価から買い手候補の選定、交渉戦略の立案、デューデリジェンスの支援、最終契約の締結まで、M&Aプロセス全体を通じて総合的なサポートを提供。経営者の想いを大切にしながら、企業の持続的成長を実現するM&Aを数多く成功に導いています。
信頼できる仲介業者を選ぶための実践的チェックポイント
優れた仲介業者を見極めるために、以下のポイントを確認することをお勧めします。
実績と経験の確認
最も重要なのは、自社と同規模案件での成約実績です。5億円規模のM&Aには特有の課題があるため、類似案件での豊富な経験を持つ仲介業者を選ぶことが成功への近道となります。業界での経験年数や過去のクライアントからの評価も重要な判断材料です。
担当体制の確認
代表者がどの程度案件に関与するかは、サービス品質に大きく影響します。大手では担当者が頻繁に変わることがありますが、代表者が直接関与する体制であれば一貫したサービスを受けることができます。担当者の専門性とチーム全体のサポート内容も事前に確認しましょう。
専門知識の確認
M&Aには財務・法務の高度な専門知識が不可欠です。公認会計士や弁護士などの資格を持つか、それに匹敵する専門知識を有しているかを確認しましょう。また、自社の業界特有の知識や最新の法制度への対応状況も重要なポイントです。
コミュニケーション能力
M&Aは長期間のプロジェクトであり、円滑なコミュニケーションが重要です。複雑な内容を分かりやすく説明できるか、連絡に対して迅速に対応できるか、経営者との相性はどうかといった点を初回面談で確認しましょう。
報酬体系の透明性
信頼できる仲介業者は報酬体系を明確に開示します。着手金、中間金、成功報酬の内訳や算定根拠、追加費用の有無について事前に詳しく説明を受け、後々のトラブルを避けることが重要です。
注意すべき仲介者の特徴
最後に、私の実務経験から見た「信頼に足るとは言い難い仲介者」の共通点をご紹介します。
以下のような対応をする場合は、慎重な判断をおすすめします。
- 買い手の紹介を過剰にアピールし、自社の理解が浅い
- 契約前から「早く動かないと買い手が逃げる」と急かしてくる
- 手数料体系や契約条件の説明が不十分
- リスクや失敗事例を話そうとしない、あるいは濁す
- 担当者が頻繁に変わる、もしくは専門家との連携が取れていない
信頼できる仲介者とは、知識や実績はもちろん、「経営者の立場に立って誠実に行動できる人物」であるべきです。
判断の基準は、派手な実績や肩書きだけではなく、現場での態度と説明の一貫性にも注目してみてください。
経営者が身につけるべきM&A情報リテラシー
「仲介者選びが大事なのは分かったが、専門家に任せれば安心なのでは?」
そんな声もよく耳にします。
たしかに、M&Aは高度な専門領域です。
しかし、だからこそ経営者自身が最低限の“情報リテラシー”を持っていないと、判断を他人任せにしたまま後悔する結果になりかねません。
ここでは、M&Aを検討する際に押さえておくべき基本的な知識と信頼できる情報源を整理します。
基礎知識:プロセス・専門用語・法規制
M\&Aの基本プロセスを理解しておくことは、仲介者の説明を鵜呑みにせず、自ら意思決定するための大前提です。
以下は、5億円規模の中小企業M&Aで一般的に用いられる流れです。
【M&Aプロセス(売り手側の視点)】
- 事前準備(資料整備・方針決定)
- 仲介会社・FAの選定と契約
- ノンネーム資料・買い手候補リストの作成
- 秘密保持契約(NDA)の締結
- 詳細情報提供とトップ面談
- 意向表明(LOI)・条件交渉
- 買い手によるデューデリジェンス(DD)
- 最終契約(SPA)締結
- クロージング(株式譲渡・資金決済)
- PMI(統合支援)とフォローアップ
また、以下のような用語が頻出します。聞き慣れない言葉でも、要点だけでも理解しておくと安心です。
【基本用語の解説(抜粋)】
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| NDA(秘密保持契約) | 買い手が情報を外部に漏らさないと約束する契約 |
| LOI(意向表明書) | 買い手が提示する買収希望条件の概要 |
| DD(デューデリジェンス) | 財務・税務・法務などの買収前調査 |
| SPA(株式譲渡契約) | 最終的な売買契約書。条項の確認が重要 |
| アーンアウト | 売却後の業績に応じて売却金額が変動する仕組み |
専門用語や契約書の内容は、士業のサポートを受けることが前提になりますが、経営者としての判断軸を持つためには、概念の理解が不可欠です。
信頼できる情報源と学習ステップ
次に、「どこから情報を得るべきか」という点です。
インターネットには誇張や誘導的な情報も多いため、信頼性の高い一次情報・専門媒体から学ぶ姿勢が重要です。
【おすすめ情報源】
- 事業承継・引継ぎポータルサイト(中小機構)
各種支援制度や統計、M&Aガイドラインなどが網羅されており、制度変更にも即時対応 - M&A関連の公的レポート(中小企業白書、金融庁資料など)
業界動向や法制度の改正内容を把握するのに有効 - 業界専門誌・メディア(MARR、事業承継通信など)
最新の事例や実務解説が掲載されている - 商工会議所・金融機関主催のM&Aセミナー
地元企業向けの実践的な解説が多く、士業・FAとのネットワーク構築にも役立つ - 中小M&Aガイドライン(2024年改訂版)
仲介者との契約時に参考となる「契約書ひな型」「説明すべき項目一覧」なども掲載
【学習のステップ例】
- 自社に近い業種・規模のM&A事例を1つ読む
- 上記のM&Aガイドラインを通読(60分程度)
- セミナーや専門家への個別相談で不明点を深掘り
経営者にとってM&Aは「人生で一度きり」の選択になることもあります。
であればこそ、“情報武装”は最も有効な防衛手段です。
私の実感としても、リテラシーが高い経営者ほど、納得感の高いディールに繋がりやすい傾向があります。
ケーススタディで学ぶ成功と失敗の分岐点
理論やチェックリストを学んでも、「実際にどう判断すればよいのか」は、なかなかイメージしにくいものです。
そこでこの章では、私がこれまで支援・取材してきた中から、中規模M&Aにおける“成功”と“失敗”の分岐点を具体的にご紹介します。
どちらも実在する中小企業で、読者の皆様にも共通する要素が多いはずです。
成功事例:経験豊富な仲介との協働で企業文化を継承
ある地方都市の老舗食品メーカー。
売上約8億円・従業員60名という体制で、創業家の3代目社長が60代後半に差しかかり、M&Aによる第三者承継を検討していました。
依頼を受けたのは、地場の独立系M&Aコンサルタント(元メガバンク出身)。
このアドバイザーは、オーナーの「従業員の雇用を守りたい」「社名と商品ブランドは残してほしい」といった“見えにくい希望”を丁寧にヒアリングし、条件整理を入念に行いました。
その結果、買い手候補の選定では次のような戦略が取られました。
- 単なる財務条件ではなく、「雇用・ブランド維持に理解ある企業」に絞ってアプローチ
- 複数回の面談と現地訪問を経て、従業員にも説明と顔合わせを実施
- 譲渡後も社長が1年間は顧問として残ることで、統合不安を抑える体制を構築
結果として、譲渡額は当初想定より1割低くなったものの、
従業員の離職はゼロ。製造体制も継続され、譲渡から2年後には新商品共同開発を実現し、地域メディアにも取り上げられる成功事例となりました。
このケースの分岐点は、「アドバイザーが“価格だけでなく文化・人材面まで重視した点”」にあります。
まさに、実務経験のあるプロフェッショナルが経営者の想いを代弁したディールだったと言えるでしょう。
失敗事例:経験不足の仲介に依頼し交渉決裂
対照的な事例として、同じく5億円規模の設備系事業会社。
後継者不在に悩んだオーナー経営者が、「ネットで見つけた手数料が安い仲介会社」に相談したのが始まりでした。
仲介者は若手1名体制。
「着手金ゼロ」「買い手はすぐ見つかる」と言われ、契約からわずか1か月で買い手候補と初面談に至りました。
しかし、問題はその後に噴出します。
- 財務資料の準備が不十分なままデューデリジェンスが開始され、買い手側から複数の修正要求が入る
- NDA(秘密保持契約)前に一部の情報が共有され、社員の耳にM&A話が入り“先に辞める”従業員が発生
- 仲介者が価格交渉で主導権を取れず、「再査定の結果、提示額を3割下げたい」と買い手から連絡が入る
最終的に、買い手は「内部が不安定すぎる」と判断し、契約直前に撤退。
売却は白紙となり、その後、離職者の補填や信用回復にかかったコストは想定の2倍以上に膨らんでしまいました。
このケースでは、仲介者が交渉スキル・プロジェクト管理能力ともに不足していたことが最大の要因です。
また、「費用が安いから」「ネットの評判が良かったから」という理由で依頼先を決めた経営者にも、一定の見落としがあったと言えるでしょう。
成功と失敗の違いは、“一見目立たないが、実務では極めて重要な部分”に表れます。
自社の未来を左右するM&Aにおいては、表面的な条件だけでなく、プロセス設計・交渉力・人間的誠実さといった非数値的な要素こそが、決定的な分岐点になるのです。
よくある質問(FAQ)
ここでは、M&Aを検討する中堅・中小企業の経営者から、私が日々の現場で頻繁に受ける質問を取り上げます。
「今さら聞けない」基本から、「判断に迷う」実務的なポイントまで、信頼できる意思決定のために押さえておきたい疑問に中立的にお答えします。
Q:仲介会社とFA(ファイナンシャルアドバイザー)の違いは何ですか?
A:大きな違いは「誰の味方として動くか」です。
仲介会社は原則、売り手・買い手の双方の調整を行う“中立”の立場ですが、報酬を両者から受け取る「両手取引」では利益相反のリスクが生じます。
一方、FAは売り手または買い手のどちらか一方に専属し、依頼者の利益を最優先に助言する役割を担います。
そのぶん着手金や月額報酬が発生しますが、利害関係の明確さがメリットです。
Q:着手金ゼロの仲介は安全でしょうか?
A:一概に危険とは言い切れませんが、報酬体系によって仲介者の動機が変わる点には注意が必要です。
着手金ゼロ・完全成功報酬型では、仲介者が早期の成約に強くインセンティブを持ちやすく、“価格よりスピード重視”の提案がされがちです。
適正な企業評価・買い手選定を丁寧に行うには、一定の初期費用(=時間的コスト)を許容する視点も大切です。
Q:成功報酬は何%が相場ですか?
A:5億円規模の案件であれば、通常5~7%程度が一般的です。
レーマン方式(段階的手数料率)に基づくことが多く、たとえば以下のような計算式で算出されます。
【レーマン方式(例)】
- 5億円までの部分:5%
- 5億円超~10億円:4%
- 10億円超:3%…と段階的に手数料率が下がる
さらに、ミニマムフィー(最低報酬額)や中間金の有無なども会社によって異なりますので、総額だけでなく契約条件の詳細確認が必要です。
Q:実績の少ない仲介でも、専門家ネットワークがあれば問題ないですか?
A:ネットワークだけでは不十分です。
実務経験の浅い仲介者は、交渉の主導力やトラブル対応力に欠けるケースが多く、「知り合いに専門家がいる」と言っても、それを有効に活用できるとは限りません。
重要なのは、「誰と組んでいるか」よりも、「自ら現場で判断し、調整できる力があるか」です。
Q:売り手側で準備しておくべき資料は何ですか?
A:以下のような資料を、事前に整理しておくとプロセスがスムーズになります。
【売却準備に必要な基本資料】
- 過去3~5期分の財務諸表(PL・BS・CF)
- 直近の月次試算表・資金繰り表
- 事業計画書(今後3年程度)
- 主な契約書(仕入先・販売先との取引基本契約など)
- 人事情報(従業員リスト、組織図、就業規則など)
- 所有資産の明細(不動産、設備、特許など)
加えて、「自社の強みを言語化したメモ」や「譲れない条件リスト」も、仲介者とのコミュニケーションに役立ちます。
まとめ:適切な仲介業者選択がM&A成功の鍵
M&A業界には確かに様々な課題が存在しますが、一方で谷口氏のような確かな実績と専門性を持つ優れた仲介業者も存在します。重要なのは、表面的な営業トークに惑わされることなく、実績、専門性、担当体制、報酬体系などを総合的に評価し、自社に最適な仲介業者を選択することです。
5億円規模のM&Aは、経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。だからこそ、信頼できるパートナーとして、確かな実績と専門性を持つ仲介業者を選ぶことが成功への第一歩となります。
適切な仲介業者の選択により、企業価値の最大化と円滑な取引実現を目指しましょう。


経験豊富な代表が直接サポート
本記事で解説した内容について詳しくお知りになりたい方、またはM&Aの実行をご検討中の方は、M&A専門の経験豊富な代表者へ直接ご相談ください。初期相談は無料です。





