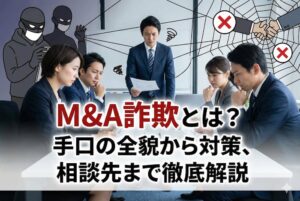M&Aの企業概要書(IM)とは?目的、記載内容、M&Aプロセスでの役割を解説

M&Aのプロセスにおいて、買い手候補があなたの会社を本格的に評価する最初のステップ、それが「企業概要書(インフォメーション・メモランダム:IM)」の提示です。
これは、いわば会社の価値を伝えるための「公式なプレゼンテーション資料」であり、その質がM&Aの成否や売却価格を大きく左右します。
近年、後継者不在の問題解決や成長戦略の一環として、中小企業のM&Aは過去最高水準で推移しています。
しかし、多くの経営者がその重要性を十分に理解しないまま、専門家に任せきりにしてしまうケースも少なくありません。
本記事では、大手金融機関で数々のM&Aに携わり、現在は完全に中立な立場で中小企業を支援する専門家として、私、高橋が企業概要書(IM)の基本から、経営者自身が知っておくべきチェックポイントまで、分かりやすく解説します。
M&Aの企業概要書(IM)とは?買い手の判断を左右する重要書類
ではまず、「企業概要書(IM)とは何か?」という基本から押さえていきましょう。
これはM&Aを検討する上で最も基本的な書類の一つです。
企業概要書(IM)の基本的な定義
企業概要書とは、その名の通り、売り手企業の詳細情報を網羅的にまとめた資料のことです。
英語では「Information Memorandum」と呼ぶため、頭文字をとって「IM(アイエム)」という略称で呼ばれるのが一般的です。
このIMには、事業内容、財務状況、組織体制、将来の事業計画といった、買い手候補がM&Aを本格的に検討するために必要な情報が数十ページにわたって詳細に記載されます。
買い手は、このIMを読んで初めて、あなたの会社が投資対象として魅力的かどうかを判断し、初期的な企業価値評価〈バリュエーション〉を行うのです。
まさに、買い手の第一印象を決定づける、極めて重要な書類と言えます。
IMとノンネームシートの決定的な違い
M&Aのプロセスには、IMの他にも「ノンネームシート」という書類が登場します。
この二つの違いを理解しておくことは非常に重要です。
ノンネームシート
M&Aの初期段階で、買い手候補に「このような会社が売却を検討していますが、興味はありますか?」と打診するために使われる匿名の資料です。
業種、事業エリア、売上規模といった、企業名が特定できない範囲の限定的な情報のみが記載されます。
企業概要書(IM)
ノンネームシートを見て関心を示した買い手候補と、秘密保持契約〈NDA:Non-Disclosure Agreement〉を締結した後に初めて開示される、詳細かつ機密性の高い資料です。
社名はもちろん、財務の詳細や取引先情報など、企業の根幹に関わる情報が含まれます。
M&Aのプロセスを「お見合い」に例えるなら、ノンネームシートが「簡単なプロフィール」だとすれば、IMは「詳細な釣書(つりがき)」と言えるでしょう。
なぜ企業概要書(IM)は重要なのか?M&Aにおける3つの目的
「なぜ、わざわざ手間をかけて詳細なIMを作成する必要があるのでしょうか?」
これは、多くの経営者様が抱く素朴な疑問です。
IMには、主に3つの重要な目的があります。
目的1:買い手候補への正確な情報提供と検討促進
最大の目的は、買い手候補がM&Aの検討を進める上で必要な情報を、網羅的かつ正確に伝えることです。
買い手は日々多くの案件情報を目にしています。
情報が断片的であったり、分かりにくかったりする案件は、検討の優先順位が下がってしまうのが現実です。
質の高いIMは、買い手が初期的な企業価値評価や自社とのシナジー効果をスムーズに検討することを可能にし、真剣な検討のテーブルに乗せるための「入場券」の役割を果たします。
目的2:自社の魅力と価値の最大化アピール
IMは、単なる情報の羅列ではありません。
自社の強み、成長性、独自の技術やノウハウといった「数字に表れない企業価値」を買い手に効果的にアピールするための、重要なマーケティングツールです。
例えば、長年地域に根ざしてきたことによる強固な顧客基盤や、熟練の職人技、あるいは従業員の結束力の高さといった要素は、財務諸表だけでは伝わりません。
私の父も小さな町工場を経営していましたが、帳簿には載らない「社員の家族構成まで把握している温かい社風」こそが最大の強みでした。
こうした無形の価値を、IMの中でストーリーとして語ることが、買い手の心を動かし、評価を高める上で極めて重要になるのです。
目的3:M&Aプロセスの効率化と円滑な進行
質の高いIMは、その後のプロセスを円滑に進めるための土台となります。
事前に詳細な情報が整理されていれば、買い手からの基本的な質問が減り、質疑応答の時間を短縮できます。
また、その後のデューデリジェンス〈DD:買収監査〉と呼ばれる詳細調査のフェーズにおいても、IMがしっかり作られていると、買い手は安心して調査を進めることができます。
これは、売り手・買い手双方の負担を軽減し、交渉をスムーズに進める潤滑油のような効果をもたらすのです。
企業概要書(IM)の具体的な記載内容【買い手が注目するポイント】
では、IMには具体的にどのような内容が記載されるのでしょうか。
ここでは、主要な項目と、私が金融機関時代に買い手側として注目していたポイントを交えて解説します。
会社概要(エグゼクティブサマリー)
会社の基本情報(社名、沿革、株主構成、事業拠点など)をまとめた、IMの冒頭部分です。
買い手はまずこのサマリーを数分で読み、「自社の成長戦略と合致するか」「M&Aの目的とフィットするか」といった戦略的なフィット感を瞬時に見極めます。
会社の歴史や理念を簡潔にまとめ、買い手の興味を引くための「つかみ」として非常に重要です。
事業内容とビジネスモデル
「どのような事業を行い、どのように収益を上げているのか」を具体的に説明する、IMの中核部分です。
製品・サービスの特徴、主要な顧客層、販売チャネル、収益構造などを記載します。
私が現場で見てきた優れたIMでは、取引の流れやサービス提供のプロセスが図式化されており、業界に詳しくない買い手でも直感的にビジネスモデルを理解できる工夫がなされていました。
組織・従業員に関する情報
役員構成、組織図、従業員数、平均年齢、勤続年数、資格保有者数などを記載します。
買い手は、M&A後の組織統合〈PMI:Post Merger Integration〉を常に意識しています。
キーパーソンとなる役員や従業員が誰なのか、組織の強みはどこにあるのかをこのセクションで把握し、M&A後に事業が円滑に運営できるかをイメージします。
財務状況(過去3〜5期分)
過去数年分の損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)といった財務諸表を掲載します。
ここで中小企業M&Aにおいて特に重要なのは、単なる数字の羅列で終わらせないことです。
例えば、業績が大きく変動した期があれば、その背景(例:大型設備投資、取引先の倒産など)を補足説明する必要があります。
また、役員報酬の調整や節税目的の保険料など、決算書上の利益と会社の「実力」が異なるケースは少なくありません。
こうした「実態収益力」を明確にするための補足説明〈正常収益力分析〉を丁寧に行うことが、買い手からの信頼を得て、適正な評価を受けるための鍵となります。
将来の事業計画
今後の成長戦略や具体的なアクションプラン、そしてそれに基づいた将来の収支予測を示します。
はっきり言って、買い手が最も重視するのがこの部分です。
彼らは「過去」ではなく「未来」に投資するからです。
「市場の成長性」「新サービスの投入計画」「販路拡大の具体策」など、客観的なデータに基づいた、説得力のある成長ストーリーを描けるかが腕の見せ所です。
M&A(譲渡)の理由と希望条件
後継者不在、事業の選択と集中、創業者利益の獲得など、会社を譲渡する理由を誠実に記載します。
譲渡理由は、買い手がM&Aの背景を理解し、共感を得るための重要な要素です。
ある老舗企業のケースでは、「従業員の雇用と、先代から受け継いだ技術を守ってくれる相手に託したい」という誠実な想いが買い手の心を打ち、非常に円滑な交渉につながりました。
ネガティブな理由であっても隠さず伝える姿勢が、信頼関係の構築につながります。
M&AプロセスにおけるIMの役割と流れ
IMがM&Aプロセス全体の中で、どのタイミングで登場し、どのような役割を果たすのかを時系列で見ていきましょう。
1. 専門家との契約とIM作成準備
まず、M&A仲介会社やFA〈ファイナンシャル・アドバイザー〉といった専門家とアドバイザリー契約を締結します。
そして、IMを作成するために必要な資料(決算書、会社案内、組織図、許認可証など)の収集を開始します。
専門家選びについては以下の記事も参考になります。


2. ノンネームシートによる打診
専門家が、あなたの会社のIMから企業名を特定できない情報だけを抜粋し、「ノンネームシート」を作成します。
このノンネームシートを基に、幅広い買い手候補企業へ初期的な関心を確認します。
3. 秘密保持契約(NDA)の締結
ノンネームシートを見て、さらに詳しい情報を知りたいと希望した買い手候補と、秘密保持契約(NDA)を締結します。
これにより、買い手候補は開示された情報をM&A検討以外の目的で使用しない法的な義務を負います。
4. 企業概要書(IM)の開示と質疑応答
NDA締結後、いよいよIMを買い手候補に開示します。
ここからが、本格的な検討のスタートです。
買い手はIMを精査し、不明点や追加で確認したい事項について質問してきます(Q&Aセッション)。
5. デューデリジェンス(DD)と最終交渉へ
IMの内容に納得し、M&Aに前向きな買い手は、基本的な条件を提示した上で、デューデリジェンス(DD)へと進みます。
DDでは、弁護士や会計士などの専門家が、IMに記載された情報が正確であるかを詳細に調査します。
このDDを経て、最終的な買収価格や契約条件の交渉が行われます。
【経営者必見】IM作成・開示で失敗しないための注意点
IMはM&Aの成否を左右する重要な書類だからこそ、その取り扱いには細心の注意が必要です。
ここでは、経営者自身が必ず押さえておくべき4つの注意点を解説します。
誇張や虚偽の記載は絶対に避ける
会社を少しでも良く見せたいという気持ちは分かります。
しかし、事実と異なる情報や、過度に楽観的な見通しを記載することは絶対に避けるべきです。
なぜなら、IMの記載内容は、後のデューデリジェンス(DD)で徹底的に検証されるからです。
もし虚偽が発覚すれば、買い手からの信頼は一瞬で失われ、最悪の場合、交渉は破談となります。
正確性こそが、信頼の第一歩です。
自社の弱みやリスクも誠実に開示する
どんな優良企業にも、弱みや課題、潜在的なリスクは存在するものです。
例えば、「特定の大口取引先に売上の多くを依存している」「キーマンとなる技術者が高齢である」といった情報です。
こうしたネガティブな情報を隠すのではなく、誠実に開示することが、逆に買い手からの信頼を高めます。
さらに、「リスクへの対策案も併記する」ことができれば、経営陣の管理能力の高さを示す絶好の機会にもなります。
例えば、「取引先依存のリスクに対し、現在新規顧客を複数開拓中です」と伝えられれば、買い手は安心するでしょう。
専門家に任せきりにせず、経営者自身が内容を必ず確認する
IMはM&Aの専門家が作成を主導することがほとんどです。
しかし、だからといって「専門家に任せておけば大丈夫」と考えるのは非常に危険です。
最終的な内容の責任を負うのは、あくまで売り手であるあなた自身です。
専門家が作成したドラフトを鵜呑みにせず、隅々まで目を通してください。
特に、ご自身の言葉でしか語れない「創業の想い」や「経営理念」「事業の将来ビジョン」がきちんと反映されているか、そして何より、事実と異なる記載がないかを徹底的に確認することが重要です。
情報管理を徹底し、漏洩を防ぐ
IMは、会社の内部情報が詰まった「機密情報の塊」です。
この情報が万が一、従業員や取引先、競合他社に漏洩すれば、どうなるでしょうか。
従業員の間に不安が広がり、優秀な人材が離職してしまうかもしれません。
取引先が「この会社は先行きが不安だ」と判断し、取引を縮小するかもしれません。
情報漏洩は、M&Aが成立する前に、あなたの会社の事業価値そのものを大きく損なうリスクがあるのです。
IMの開示先はNDAを締結した相手に限定し、社内での資料の取り扱いにも細心の注意を払う必要があります。
よくある質問(FAQ)
最後に、経営者の皆様からよくいただくご質問にお答えします。
Q: 企業概要書(IM)の作成は誰に依頼すれば良いですか?
A: 一般的には、契約したM&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)が作成を主導します。
ここで重要なのは、専門家のタイプによってIMの質や切り口が異なる可能性がある点です。
例えば、売り手と買い手の間に立つ仲介会社は客観的な事実を重視する傾向があり、売り手側の代理人であるFAは、より戦略的に魅力をアピールする構成を採ることがあります。
どちらが良いというわけではありません。
大切なのは、自社のビジネスや強みを深く理解し、丁寧にヒアリングしてくれるパートナーを選ぶことです。
Q: IMの作成にはどれくらいの期間と費用がかかりますか?
A: 企業の規模や事業の複雑さにもよりますが、資料収集から完成まで、通常1〜2ヶ月程度の期間を見ておくと良いでしょう。
費用については、IM作成単体で料金が発生することは稀です。
多くの場合、M&Aアドバイザリー契約の「着手金」や「月額報酬」に作成費用が含まれています。
中小企業M&Aにおける着手金の相場は、無料の会社から、数十万~200万円程度が一般的です。
契約前に料金体系をしっかり確認することが重要です。
Q: 買い手はIMのどこを一番重視しますか?
A: 私が金融機関で買い手側のM&Aを担当していた経験から申し上げると、特に重視するのは次の3点です。
- 事業の将来性(事業計画): M&Aによってどのような成長が見込めるか。
- 自社とのシナジー効果(ビジネスモデル): 自社の事業と組み合わせることで、1+1が3になるような効果が期待できるか。
- 財務の健全性と実態収益力(財務状況): 安定したキャッシュフローを生み出せるか、簿外債務などのリスクはないか。
特に、M&A後の成長ストーリーを具体的な根拠と共に示せることが最も重要です。
Q: 中小企業のM&Aでも、立派なIMは必要ですか?
A: はい、絶対に必要です。
むしろ、中小企業にこそIMは不可欠だと私は考えています。
なぜなら、中小企業の本当の価値は、決算書だけでは決して伝わらないからです。
長年培ってきた技術力、地域での信頼、特定のニッチ市場での高いシェア、そして何より経営者であるあなたの想い。
こうした無形の価値をIMでしっかりと「言語化」し「見える化」することこそが、大企業にも負けない適正な評価を得るための唯一の道なのです。
Q: IMに記載すべきでない情報はありますか?
A: 基本的には、買い手の判断に必要な情報はすべて誠実に開示するべきです。
ただし、現段階で開示すると事業運営に直接的な支障をきたす可能性のある、極めて機微な情報(例:開発中の新製品に関する詳細すぎる技術情報など)については、専門家と相談の上、開示の範囲やタイミングを慎重に判断する必要があります。
まずはDDの前の段階では概要に留め、より交渉が進んだ段階で追加開示するといった対応が考えられます。
まとめ
企業概要書(IM)は、M&Aの成否を左右する、まさに「会社の価値を伝える最初のプレゼンテーション」です。
その目的は、買い手に正確な情報を提供し、自社の魅力を最大限に伝え、円滑な交渉の土台を築くことにあります。
記載内容は多岐にわたりますが、特に事業の将来性や、財務諸表には表れない自社ならではの強みを、客観的な根拠と共に示すことが重要です。
M&Aという会社の未来を決める重大な経営判断において、専門家に任せきりにするのではなく、経営者自身がIMに込められたメッセージを深く理解し、内容を主体的に確認すること。
それが、心から納得のいくM&Aを実現するための、そして何より、大切に育ててきた会社と従業員を守るための鍵となります。
この記事が、あなたの会社の価値を未来へ繋ぐための一助となれば幸いです。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。