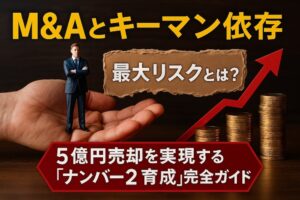アーンアウト条項のメリット・デメリット|中小企業経営者が知るべき5つのポイント
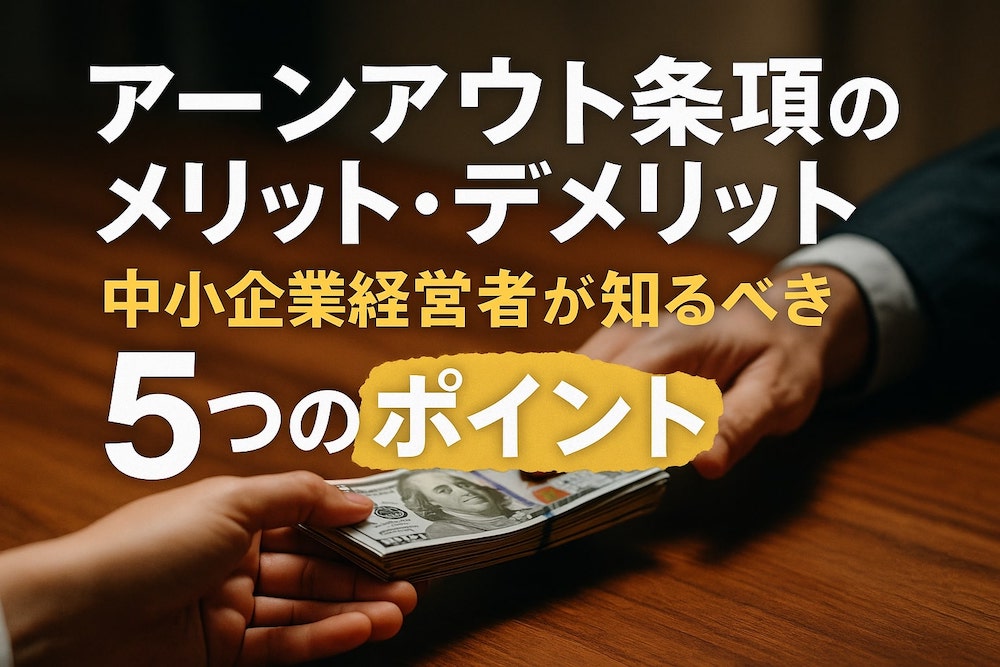
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの高橋健一です。
「M&A 5億の扉」の外部専門家として、今回は中小企業のM&Aで耳にする機会が増えた「アーンアウト条項」について、徹底的に掘り下げていきます。
これは、会社の将来性を評価に反映させ、売り手にとってはより高い売却価格を実現できる可能性がある一方、買い手にとっては高値掴みのリスクを抑えられる、いわば「未来への期待値を価格にする」仕組みです。
しかし、私が現場で見てきた中で、このアーンアウトはまさに「諸刃の剣」です。
安易に契約に盛り込むと、期待した対価が得られないばかりか、M&A後の経営に思わぬ制約が生じる可能性も秘めています。
本記事では、売り手である中小企業経営者がアーンアウト条項と向き合う上で本当に知るべきメリット・デメリット、そして契約前に必ず押さえるべき5つの重要ポイントを、実務的な観点から分かりやすく解説します。
【基本の理解】アーンアウト条項とは何か?
アーンアウトの仕組みを分かりやすく解説
ではまず、アーンアウト条項そのものについて理解を深めましょう。
アーンアウト条項とは、M&Aの対価の一部を、M&A成立後の一定期間における業績目標の達成度合いに応じて後払いする、という契約上の取り決めです。
法律用語では「条件付取得対価」とも呼ばれます。
一言でいえば、「会社の将来の頑張りを、追加の売却価格に反映させる約束」と言えるでしょう。
買い手から売り手へ、確定対価(例:3億円)が支払われる。
設定した業績目標(例:3年後のEBITDAが1億円)の達成を目指す。
目標を達成した場合、買い手から売り手へ、追加対価(例:1億円)が支払われる。目標未達の場合、追加対価は支払われない(または減額される)。
この仕組みがなぜ有効かというと、売り手と買い手の「企業価値」に対する考え方のギャップを埋めてくれるからです。
売り手は「自社の将来性はこんなものではない」と高く評価し、買い手は「将来のことは不確実だ」と慎重に評価します。
この溝を、アーンアウトという「未来の結果で答え合わせをする」仕組みが埋めてくれるのです。
なぜ今、中小企業のM&Aで注目されるのか?
近年、なぜこのアーンアウトが中小企業のM&Aでも注目されているのでしょうか。
その最大の理由は、M&Aの対象となる企業の性質が変化してきたことにあります。
このような企業のM&Aでは、売り手と買い手の希望価格に大きな隔たりが生まれがちです。
「将来これだけ伸びるのだから、もっと高く評価してほしい」という売り手と、「その成長が本当に実現するのか確信が持てない」という買い手。
この平行線を解消し、交渉を妥結に導くための現実的な選択肢として、アーンアウトが活用されているのです。
【売り手経営者視点】アーンアウトのメリット
アーンアウトは、売り手である経営者にとって大きな可能性を秘めています。
具体的に3つのメリットを見ていきましょう。
1. 将来の成長性を価格に反映させ、企業価値を最大化できる
これが売り手にとって最大のメリットです。
現時点での業績や純資産だけでなく、自社が持つ将来の成長ポテンシャルを売却価格に上乗せできます。
例えば、私が以前ご支援したあるソフトウェア開発企業は、画期的な新製品をリリースした直後でした。
足元の業績はまだ大きくありませんでしたが、経営者は「2年後には市場を席巻する自信がある」と確信していました。
そこでアーンアウトを導入し、「2年後の製品売上高」を目標に設定。
結果、見事に目標を達成し、当初の提示額より1.5倍高い価格での売却を実現しました。
このように、自社の将来性に絶対的な自信がある経営者にとって、アーンアウトは正当な評価と高いリターンを得るための強力な武器となり得ます。
2. 買い手との価格交渉を円滑に進められる
M&A交渉が難航する典型的なパターンが、価格のミスマッチです。
売り手の希望額に対し、買い手が「高すぎる」と感じれば、交渉はそこで止まってしまいます。
アーンアウトは、この状況を打開する潤滑油の役割を果たします。
買い手側が持つ「高値掴みリスク」を、「業績が達成されたら支払う」という形で低減させることができるからです。
これにより、買い手は交渉のテーブルにつきやすくなり、結果としてM&Aの成立可能性そのものを高める効果が期待できます。
希望価格に大きな開きがある場合ほど、アーンアウトは双方の妥協点を見出すための有効なツールとなり得るのです。
3. M&A後も経営へのモチベーションを維持しやすい
M&A後も、売り手である元経営者が一定期間、会社に残って経営に関与するケースは少なくありません。
この場合、アーンアウトの目標達成がご自身の追加報酬に直結するため、事業成長への強いインセンティブになります。
これは買い手にとってもメリットです。
元経営者のモチベーションが高いことは、円滑な事業の引継ぎ、いわゆるPMI〈Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス〉の成功に不可欠だからです。
売り手と買い手の利害が「事業を成長させる」という一点で一致するため、M&A後の協力関係を築きやすくなるのです。
【売り手経営者視点】アーンアウトのデメリットと潜在リスク
しかし、光が強ければ影もまた濃くなります。
アーンアウトには、経営者が必ず認識しておくべき重大なデメリットとリスクが存在します。
1. 追加対価が支払われない・減額されるリスク
これが最大かつ最も分かりやすいデメリットです。
M&A後の市場環境の急変、競合の台頭、あるいは買い手側の経営方針の変更など、自らの努力だけではコントロールできない要因で業績目標が未達に終わる可能性があります。
その場合、期待していた追加対価は一切受け取れません。
「アーンアウトで最大2億円」という甘い言葉を信じ、当初の売却価格を低く設定してしまうと、結果的に安値で会社を売却したことになりかねないのです。
これは決して他人事ではありません。
2. M&A後の経営の自由度が著しく低下する可能性
アーンアウト期間中は、良くも悪くも「目標達成」が至上命題となります。
その結果、買い手から経営方針に対して細かく干渉されるリスクが生まれます。
「その設備投資は本当に必要か?」
「コスト削減のために、この部門の人員採用は見送ってほしい」
「もっと短期的な売上につながる施策を打てないのか?」
このように、本来やりたかった中長期的な成長戦略が取れなくなり、短期的な数字作りのための経営を強いられるかもしれません。
報告義務の負担が増え、経営者としての裁量が失われるストレスは、想像以上に大きいものです。
これでは、まるで「アーンアウトの奴隷」です。
3. 買い手による意図的な目標達成の阻害
これは最も警戒すべきリスクです。
悪質なケースでは、買い手が追加対価の支払いを免れるため、意図的に目標達成を阻害する行為に出る可能性があります。
例えば、アーンアウトの目標が「営業利益」だったとしましょう。
買い手は、グループ共通経費と称して不当に高い管理費を負担させたり、必要な投資を抑制して事業の成長を妨げたりすることで、意図的に利益を低く操作することができてしまいます。
このような事態を防ぐためには、後述する「5つのポイント」で解説するような、緻密な契約上の防御策が不可欠です。
中小企業経営者が知るべき5つの最重要ポイント
では、アーンアウトを導入する際に、売り手経営者は何をすべきか。
ここでは、私が常にクライアントにお伝えしている5つの最重要ポイントを解説します。
ポイント1:目標指標(KPI)は「明確」かつ「操作されにくい」ものか?
アーンアウトの根幹をなすのが、目標となるKPI〈Key Performance Indicator:重要業績評価指標〉です。
このKPIの選び方が、成否の9割を決めると言っても過言ではありません。
例えば、「売上高」は一見分かりやすい指標ですが、利益を度外視した値引き販売でも達成できてしまうため、買い手から敬遠されることがあります。
逆に、買い手のさじ加減で変動させやすい「営業利益」だけを指標にすると、先ほど述べたような意図的な阻害のリスクが高まります。
具体的には、以下のような指標が考えられます。
- EBITDA〈イービットディーエー〉:税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出する利益。設備投資や借入金利の影響を受けにくく、事業そのものの収益力を測る指標としてM&Aで多用されます。
- 特定の製品やサービスの売上高・契約件数
- 新規顧客獲得数
- ウェブサイトのユニークユーザー数
自社のビジネスモデルにとって何が最も本質的な成長指標なのかを考え抜き、客観的で測定可能なKPIを設定することが極めて重要です。
ポイント2:達成条件と算定方法は「具体的」で「一義的」か?
「目標を達成したら支払う」といった曖昧な口約束は、将来の紛争の火種にしかなりません。
契約書には、誰が読んでも同じ解釈しかできないレベルまで、具体的かつ一義的に条件を明記する必要があります。
- いつまでに(期間):例「2028年3月31日までに」
- どの指標が(KPI):例「2027年度のEBITDAが」
- いくらになったら(目標値):例「1億円以上になった場合」
- いくらを(支払額):例「金5,000万円を」
- いつまでに支払うのか(支払期日):例「2028年6月30日までに支払う」
さらに、KPIの「算定方法」についても、具体的な計算式まで契約書に落とし込むべきです。
例えば、EBITDAを指標にするなら、その計算の基礎となる財務諸表の範囲や、特殊な費用の扱いなどを細かく定義しておく必要があります。
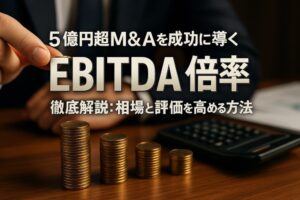
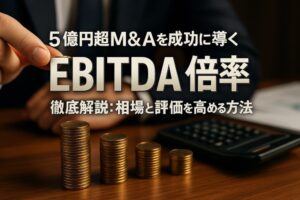
ポイント3:経営の独立性はどこまで担保されるか?
アーンアウト期間中、元経営者として事業に関与する場合、その権限と責任の範囲を明確に定義することが不可欠です。
目標達成の責任を負うのであれば、そのための権限も与えられなければアンフェアです。
- 設備投資の決裁権:いくらまでの投資なら、自己の判断で実行できるのか。
- 人材採用の権限:どのポジションの採用を、誰の承認で行えるのか。
- マーケティング予算:目標達成に必要な予算が、一方的に削減されないか。
これらの権限が確保されていなければ、目標達成の手段を奪われたまま結果だけを求められるという、理不尽な状況に陥りかねません。
「アーンアウト期間中の経営に関する重要事項については、売り手の事前承諾を要する」といった包括的な条項を盛り込む交渉も視野に入れるべきです。
ポイント4:情報開示と報告の義務は妥当な範囲か?
アーンアウト期間中、買い手は目標の進捗をモニタリングするため、売り手に様々な情報開示や報告を求めてきます。
これは当然の権利ですが、その範囲と頻度が過度な負担にならないか、契約前にしっかり確認する必要があります。
逆に、売り手側にも権利があります。
目標達成状況を正確に把握するため、買い手に対して必要な会計情報の開示を要求する権利を確保すべきです。
買い手側の経理システムでしか確認できない数値をKPIにしている場合、そのデータが正確かどうかを検証できなければ、言いなりになるしかありません。
双方の権利と義務のバランスが取れた、フェアな情報開示条項を目指しましょう。
ポイント5:信頼できる専門家(弁護士・M&Aアドバイザー)はいるか?
最後に、そして最も重要なことです。
アーンアウトは極めて複雑で、法務・税務・会計の専門知識が絡み合う高度な取引です。
これを経営者お一人で判断し、交渉に臨むのはあまりにも危険です。
私が独立系コンサルタントとして申し上げるのも何ですが、特定の買い手や仲介会社に偏らない、真に売り手の味方となってくれる専門家の存在が不可欠です。
- M&A実務に精通した弁護士:契約書の隅々までリスクを洗い出し、法的に不利な点がないかをチェックします。
- 中立的なM&Aアドバイザー:KPIの設定から価格交渉、経営権の確保まで、戦略的に交渉をサポートします。
情報こそが経営者の武器です。
そして、専門家選びこそが、M&Aの成否を分ける最大の要因です。
人生を賭けて築き上げてきた会社のために、将来のトラブルを防ぐ最大の防御策として、信頼できる専門家への投資を惜しまないでください。
よくある質問(FAQ)
Q: 買い手はなぜアーンアウトを提案してくるのですか?
A: 主に2つの狙いがあります。
1つ目は、将来の業績が不透明な事業への投資リスクを下げたい(高値掴みを避けたい)という買い手側の防御的な理由です。2つ目は、M&A後も売り手経営者に残ってもらい、その知見やリーダーシップを活かして事業成長にコミットしてほしい、という攻撃的な理由です。
多くの場合、売り手と買い手の企業価値に対する考え方のギャップを埋めるための、合理的な提案と捉えることができます。
Q: アーンアウトの期間はどのくらいが一般的ですか?
A: ケースバイケースですが、一般的にはM&A成立後の1年~3年程度で設定されることが多いです。
事業の特性や、業績が安定して成長軌道に乗るまでに見込まれる期間を考慮して、買い手と売り手の交渉によって決定されます。
あまりに長すぎると、売り手の負担が大きくなりすぎるため注意が必要です。
Q: 目標が達成できなかった場合、ペナルティはありますか?
A: 基本的に、目標未達に対するペナルティとして売り手が何かを支払うことはありません。
あくまで「目標を達成した場合に追加の対価が支払われる」という成功報酬型の契約です。
したがって、未達の場合は「追加の支払いがない」というのが原則です。
ただし、契約内容によっては当初の売却価格が減額されるような特殊な取り決めも理論上は考えられますので、契約書の文言は細心の注意を払って確認してください。
Q: アーンアウト期間中に、会社がさらに転売されたらどうなりますか?
A: 非常に重要な論点です。
これは「チェンジ・オブ・コントロール条項」として、契約書に明記しておく必要があります。
例えば、「第三者への再売却時点でアーンアウトの支払いを全額確定させる(アクセラレーション)」、「再売却先の企業がアーンアウトの義務をそのまま引き継ぐ」といった条項が考えられます。
この点を見落とすと、会社の所有者が変わった途端に、ご自身のアーンアウトの権利が反故にされてしまうリスクがあります。
Q: 税金の支払いはどのタイミングで発生しますか?
A: アーンアウトの税務は非常に複雑で、かつ売り手の手取り額に致命的な影響を与える可能性があるため、絶対に専門家である税理士に相談してください。
大原則として、個人株主の場合、M&A成立時に受け取った対価は「株式譲渡所得(税率約20%)」として課税されます。
しかし、後日受け取るアーンアウトの追加対価は、税務上「雑所得」と判断される可能性があります。
雑所得は他の給与所得などと合算される総合課税の対象となり、最高で約55%の累進課税が適用される恐れがあるのです。
これは株式譲渡所得の税率と比べて非常に高く、手取り額が大きく変わってきます。
課税のタイミングは、原則としてアーンアウトの支払いが確定した年(通常は受け取った年)に、その金額に対して確定申告が必要になります。
まとめ
アーンアウト条項は、将来性に自信のある中小企業にとって、企業価値を最大化するための強力な武器となり得ます。
それは間違いありません。
しかし、その輝かしいメリットの裏には、「期待した対価が得られないリスク」や「経営の自由を失うリスク」、そして「意図せぬ高額な税負担のリスク」が潜んでいることを、決して忘れないでください。
重要なのは、メリットとデメリットを天秤にかけ、自社の状況、そしてご自身のM&A後の人生設計にとって、本当に適した選択なのかを冷静に見極めることです。
そして、もしアーンアウトを導入するならば、本記事で解説した「5つのポイント」を羅針盤としてください。
曖昧な点を一切残さない緻密な契約設計が、あなたの未来を守る唯一の盾となります。
M&Aは情報戦であり、交渉の場です。
そして、その成否を分けるのは、経営者であるあなたの隣に、誰が座っているかです。
人生を賭けて築いた会社のために「納得感のあるM&A」を実現できるよう、信頼できる専門家と共に、慎重に交渉を進めていただきたいと思います。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。