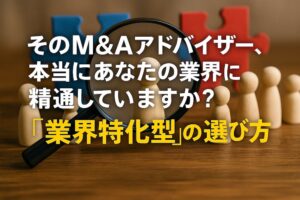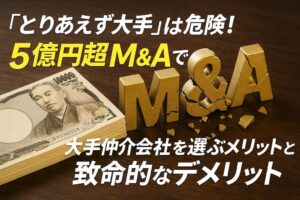「紹介されたから」は危険?M&Aアドバイザー選びで社長が陥りがちな失敗
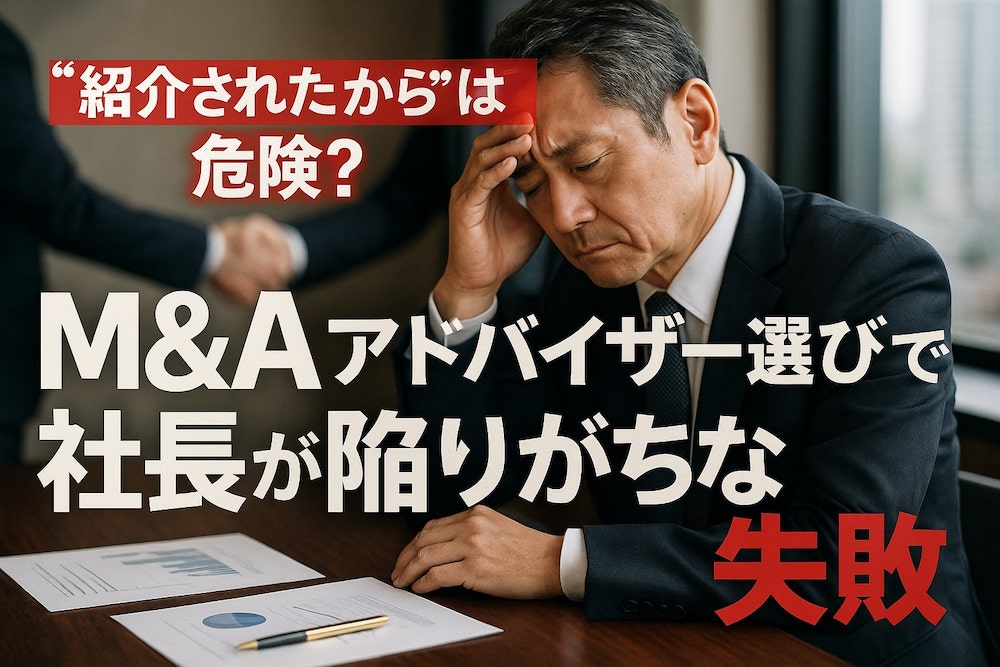
こんにちは。
独立系M&Aコンサルタントの高橋 健一です。
会社の未来を左右するM&A。
その成否の8割は、伴走するアドバイザー選びで決まると言っても過言ではありません。
金融機関に在籍していた頃、そして独立後の今も、私は多くの経営者がアドバイザー選びで悩む姿を見てきました。
特に多いのが、「メインバンクから紹介されたから」「尊敬する経営者の知人だから」といった理由で、深く吟味せずに契約し、後に「こんなはずではなかった」と後悔するケースです。
紹介は安心材料の一つに見えますが、時として企業の価値を最大化する機会を奪う足枷にもなり得ます。
本記事では、なぜ「紹介されたから」という理由だけでアドバイザーを選ぶのが危険なのか、その構造的な問題と、経営者が本当に信頼できるパートナーを見極めるための実践的な方法を、私の経験と中立的な視点から徹底的に解説します。

なぜ「紹介されたから」という理由だけでM&Aアドバイザーを選ぶのは危険なのか?
失敗事例1:紹介者の顔を立ててしまい、不利な条件でも「NO」と言えない
まず考えられるのが、心理的な交渉力の低下です。
これは、私が銀行員時代に目の当たりにした、ある部品メーカーの社長のケースが象徴的でした。
「いつもお世話になっているメインバンクの〇〇さんからの紹介だから、無下にはできないよ。」
そうおっしゃる社長の手元には、相場より明らかに高い手数料が記載された契約書案がありました。
疑問を感じつつも、紹介者の顔を立てたいという気持ちが働き、強く交渉できないのです。
結果として、高額な手数料を支払ったり、自社に不利な専任契約〈特定の1社にしか依頼できなくなる契約〉を結んでしまったりする。
この「断りづらさ」こそが、紹介がもたらす最初の罠なのです。
失敗事例2:自社の業界や規模に合わない「専門性のミスマッチ」
次に、紹介されたアドバイザーが、必ずしもあなたの会社の専門家ではないというリスクです。
M&Aは、業界や事業規模によって評価すべきポイントが全く異なります。
例えば、歴史ある製造業の価値は、長年培った技術力や取引先との関係性にあるかもしれません。
一方、急成長中のIT企業であれば、独自のアルゴリズムや将来の市場性が価値の源泉です。
紹介されたアドバイザーが、あなたの会社の事業規模(例えば5億円規模)や業界のM&Aに精通していなければ、どうなるでしょうか。
本来評価されるべき価値が見過ごされ、企業価値が不当に低く見積もられたり、事業の将来性を理解しない相手先を紹介されたりする危険性があるのです。
失敗事例3:見えにくい「利益相反」の構造に巻き込まれる
これは最も根深く、経営者が見抜きにくい問題です。
「利益相反」とは、一方の利益が、もう一方の不利益になる状態を指します。
例えば、紹介者である金融機関と、紹介されたM&Aアドバイザー(特に仲介会社)の間に、紹介料などの金銭的な関係性があるケースを考えてみましょう。
この場合、アドバイザーはクライアントであるあなたの会社よりも、継続的に案件を紹介してくれる金融機関の意向を優先するインセンティブが働く可能性があります。
さらに、売り手と買い手の両方から手数料を得るM&A仲介会社の場合、構造的に利益相反のリスクを抱えています。
リピート取引が期待できる優良な買い手企業を優遇し、あなたの会社の売却価格を最大化する努力を怠る。
そんな最悪のシナリオも、この構造からは起こり得るのです。


そもそも「紹介」は誰のためのものか? – 構造的問題の客観的解説
では、そもそも「紹介」は、本当にあなたの会社のために行われているのでしょうか。
もちろん、善意からの紹介も数多く存在します。
しかし、その裏側にある構造を冷静に分析することも重要です。
紹介者である金融機関には、M&Aの成立によって得られる手数料や、関連融資の実行といったビジネス上の目的(ノルマ)が存在する場合があります。
また、紹介先のM&A会社との関係を維持したいという力学も働くでしょう。
つまり、「紹介」という行為は、必ずしも「売り手経営者の利益最大化」という一点のみを目的としているわけではないのです。
この現実を理解することが、思考停止に陥らず、自社の利益を守るための第一歩となります。
社長が陥りがちなM&Aアドバイザー選びの3つの罠
罠1:「大手だから」「有名だから」という思考停止
「あの会社は業界最大手だから安心だ。」
これは、アドバイザー選びで非常によく聞かれる言葉ですが、危険な思考停止に他なりません。
確かに、大手には実績や情報ネットワークの豊富さというメリットがあります。
しかし、本当に重要なのは「会社の看板」ではなく、「自社の担当者」の力量と誠実さです。
私が知る限りでも、大手M&A会社に所属していても、経験の浅い担当者が機械的にプロセスを進めるケースは少なくありません。
特に、5億円規模のM&A案件は、大手にとっては数ある案件の一つとして、後回しにされてしまう可能性も否定できないのです。
会社の規模や知名度だけでなく、自社の企業文化や社長であるあなたとの相性を見極めることが不可欠です。
罠2:手数料体系を理解しないまま契約してしまう
M&Aの手数料は複雑ですが、これを理解しないまま契約するのは絶対に避けるべきです。
手数料には主に「着手金」「中間金」「成功報酬」があります。
特に注意すべきは、成功報酬の計算ベースとなる「取引金額」の定義です。
【図表挿入】
▼レーマン方式の計算ベースによる手数料の比較例
- 前提: 株式価値5億円、有利子負債2億円、その他負債1億円
- ケースA:株式価値ベース
- 計算対象:5億円
- 手数料:5億円 × 5% = 2,500万円
- ケースB:移動総資産ベース
- 計算対象:8億円(株式価値5億 + 負債総額3億)
- 手数料:(5億円 × 5%) + (3億円 × 4%) = 2,500万円 + 1,200万円 = 3,700万円
ご覧の通り、同じM&Aでも、契約書のわずかな記述の違いで1,200万円もの差が生まれるのです。
契約前に、手数料の計算方法を隅々まで確認し、納得できるまで説明を求めてください。
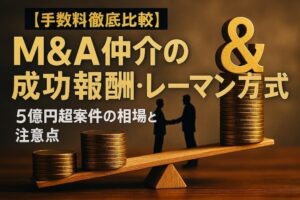
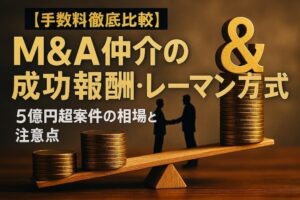
罠3:自社の「想い」や「ビジョン」を軽視するアドバイザーを選んでしまう
M&Aは、単なる数字の取引ではありません。
そこには、創業から今日まで会社を支えてきた従業員の生活、築き上げてきた企業文化、そして何より、社長であるあなたの「想い」が詰まっています。
「従業員の雇用を必ず守ってほしい」
「この社風を引き継いでくれる会社に譲りたい」
こうした目に見えない価値を深く理解し、交渉のテーブルで言語化し、相手に伝えてくれるアドバイザーでなければ、たとえ高値で売れたとしても、心からの納得感は得られないでしょう。
アドバイザーの面談では、財務の話だけでなく、あなたの会社の歴史やビジョンについて、どれだけ真剣に耳を傾けてくれるか。
その姿勢にこそ、アドバイザーの人間性と価値観が表れるのです。
【中立解説】M&Aアドバイザーの種類と特徴を正しく理解する
では、具体的にどのような選択肢があるのでしょうか。
ここでは代表的な3つのタイプを、それぞれのメリット・デメリットと共に公平に解説します。
M&A仲介会社:売り手と買い手の「間」に立つ調整役
中小企業のM&Aで最も一般的な存在です。
売り手と買い手の双方と契約し、中立的な立場で両者の間を取り持ち、取引の成立(マッチング)を目指します。
- メリット → 幅広い買い手候補のネットワークを持ち、スピーディーなマッチングが期待できる。
- デメリット → 前述の通り、売り手と買い手の双方から手数料を得るため、構造的な「利益相反」のリスクを抱える。必ずしも売り手の利益が最大化されるとは限らない。
仲介会社を利用する場合は、その構造を理解した上で、担当者がいかに自社の利益を考えてくれるかを慎重に見極める必要があります。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー):売り手の「味方」に徹する代理人
FAは、売り手か買い手の「どちらか一方」とのみ契約し、依頼主の利益を最大化することだけを使命とします。
あなたが売り手としてFAを雇った場合、そのFAは100%、あなたの「味方」として行動する代理人です。
- メリット → 利益相反のリスクがなく、徹底的に売り手の立場で交渉戦略を練り、売却価格や条件の最大化を追求してくれる。
- デメリット → 相手探しは自社のネットワークや提携先を駆使するため、仲介会社に比べて時間がかかる場合がある。一般的に手数料は仲介会社より高額になる傾向がある。
会社の価値を1円でも高く評価してほしい、絶対に譲れない条件がある、といった場合に非常に心強い存在です。
銀行・証券会社、会計事務所など:それぞれの得意分野と限界
メガバンクや大手証券会社には専門のM&A部隊があり、特に大型案件に強みを発揮します。
一方で、地域金融機関の場合、専門部署はなく、提携するM&A仲介会社へ「紹介」することが主な業務となっているケースも少なくありません。
また、顧問税理士や会計事務所も相談先の一つですが、彼らの専門はあくまで財務・税務です。
企業価値評価はできても、買い手候補を探すネットワークや、複雑な交渉を乗り切る実務経験が十分でない場合があることも理解しておくべきでしょう。
失敗しない!社長が自らアドバイザーを見極めるための実践的チェックリスト
契約前に必ず確認すべき「10の質問」
アドバイザー候補との面談では、受け身にならず、こちらから積極的に質問をぶつけてください。
以下に、私が経営者の方に必ずお勧めしている質問リストを挙げます。
- 貴社の収益構造は?(仲介として双方から得るのか、FAとして片方から得るのか)
- 私の会社の担当チームの体制と、各担当者の経歴・実績を教えてください。
- 過去に、私の会社と同じ業界・規模のM&Aを手掛けた具体的な実績はありますか?
- 手数料体系について、成功報酬の計算ベース(株式価値か移動総資産か等)を含め、全ての費用を具体的に説明してください。
- 貴社が考える、私の会社の企業価値(価格レンジ)とその算定根拠を教えてください。
- どのようなプロセスで、どのような買い手候補を探してきますか?
- 利益相反のリスクについて、貴社はどのように考え、どのような対策を講じていますか?
- もし交渉が難航した場合、どのようなサポートをしてくれますか?
- 契約期間と、中途解約の条件を教えてください。
- なぜ、あなたは他のアドバイザーではなく、自分が私の会社にとって最適だと考えますか?
これらの質問への回答の明瞭さ、誠実さ、そして具体性が、アドバイザーの信頼性を測るリトマス試験紙となります。
担当者の「力量」と「誠実さ」を見抜くポイント
最終的にパートナーとなるのは、一人の「人間」です。
面談では、以下のポイントに注目してください。
- レスポンスは迅速かつ丁寧か。
- 専門用語を、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。
- こちらの話を遮らず、真摯に最後まで耳を傾ける姿勢があるか。
- メリットだけでなく、M&Aに伴うリスクやデメリットについても正直に話してくれるか。
- 何よりも、社長であるあなたと「人として」信頼関係を築けそうか。
直感も大切にしてください。
父も中小企業の経営者でしたが、最後は「こいつになら任せられる」という感覚を大事にしていました。
その感覚は、多くの場合正しいものです。
なぜ「セカンドオピニオン」が重要なのか
最後に、最も重要な行動を一つだけ挙げるとすれば、それは「セカンドオピニオン」を取ることです。
紹介された1社の話だけを鵜呑みにせず、必ず2〜3社の異なるタイプの専門家から話を聞いてください。
これは、医療の世界で主治医以外の医師の意見を聞くのと同じです。
M&Aという会社の未来を左右する重大な外科手術において、複数の専門家の意見を聞くのは当然の権利であり、義務でさえあります。
国も「中小M&Aガイドライン」の中で、セカンドオピニオンの活用を推奨しています。
比較することで、提示された企業価値や手数料が妥当な水準なのか、自社にとって最適なパートナーは誰なのかが、客観的に見えてくるはずです。


よくある質問(FAQ)
Q: 複数のアドバイザーに同時に相談しても問題ありませんか?
A: 全く問題ありません。むしろ、積極的にそうすべきです。
ただし、本格的に業務を依頼する「アドバイザリー契約」を結ぶのは、最終的に1社に絞るのが一般的です。
契約前の相談・面談段階では、複数の候補を比較検討することが、失敗しないための最大の鍵となります。
Q: 手数料の相場が分かりません。着手金は払うべきでしょうか?
A: 手数料体系は会社により様々ですが、近年は「完全成功報酬型」(着手金・中間金が無料)の会社も増えています。
着手金は、M&Aが成立しなくても返金されない費用です。
これを支払うと「払った分を取り返したい」という心理が働き、途中で疑問を感じても断りづらくなる可能性があります。
サービス内容と費用が見合っているか慎重に検討し、納得できない場合は着手金のない会社を選ぶのも賢明な選択です。
Q: 良いアドバイザーと悪いアドバイザーの決定的な違いは何ですか?
A: 一言で言えば、「誰のために仕事をしているか」という視点の違いです。
良いアドバイザーは、常にあなたの会社の価値とあなたの「想い」を深く理解し、その最大化のために全力を尽くします。
悪いアドバイザーは、自分の会社の利益(手数料)を優先し、取引を早く成立させること自体が目的になりがちです。
面談を通じて、そのアドバイザーが本当に「あなたの味方」なのかを見極めてください。
Q: 紹介してくれた人の顔を潰さずに、断る良い方法はありますか?
A: 感謝と敬意を伝えつつ、あくまで自社の経営判断であることを丁寧に説明するのが良いでしょう。
例えば、「この度は素晴らしいご縁をいただき、誠にありがとうございました。複数の専門家の方からお話を伺い、弊社の特殊な事情も踏まえて総合的に検討した結果、今回は別の専門家にお願いすることにいたしました」といった伝え方が考えられます。
誠実に対応すれば、相手も理解してくれるはずです。
Q: M&A仲介の「利益相反」が問題視されていますが、具体的に何が危険なのですか?
A: 最も危険なのは、あなたの会社の利益が最大化されない可能性がある点です。
仲介会社は売り手と買い手の双方から手数料を得るため、取引を成立させることが最優先目標になりがちです。
その結果、例えば「より高く買ってくれる可能性のある他の買い手候補を探す努力を怠る」「交渉において、リピート顧客になりやすい買い手側に有利な条件で話を進めてしまう」といったリスクが生まれます。
これが、利益相反の具体的な危険性です。
まとめ
M&Aアドバイザー選びは、会社の未来を託すパートナー選びです。
「紹介されたから」という理由は、あくまで出会いのきっかけの一つに過ぎません。
大切なのは、紹介という安心感に思考を委ねることなく、ご自身の目で、耳で、そして経営者としての直感で、そのアドバイザーが本当に信頼に足る相手かを見極めることです。
本記事でご紹介した視点やチェックリストが、社長の皆様にとって、最良のパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。
M&Aはゴールではなく、会社と従業員の未来を創るための重要なステップです。
その第一歩であるアドバイザー選びで、決して後悔しないでください。
私も、中立的な立場から経営者の皆様に有益な情報を提供し続けることをお約束します。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。