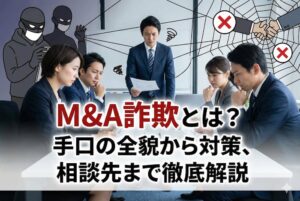意向表明書とは?M&A専門家が記載項目・書き方から法的拘束力まで徹底解説
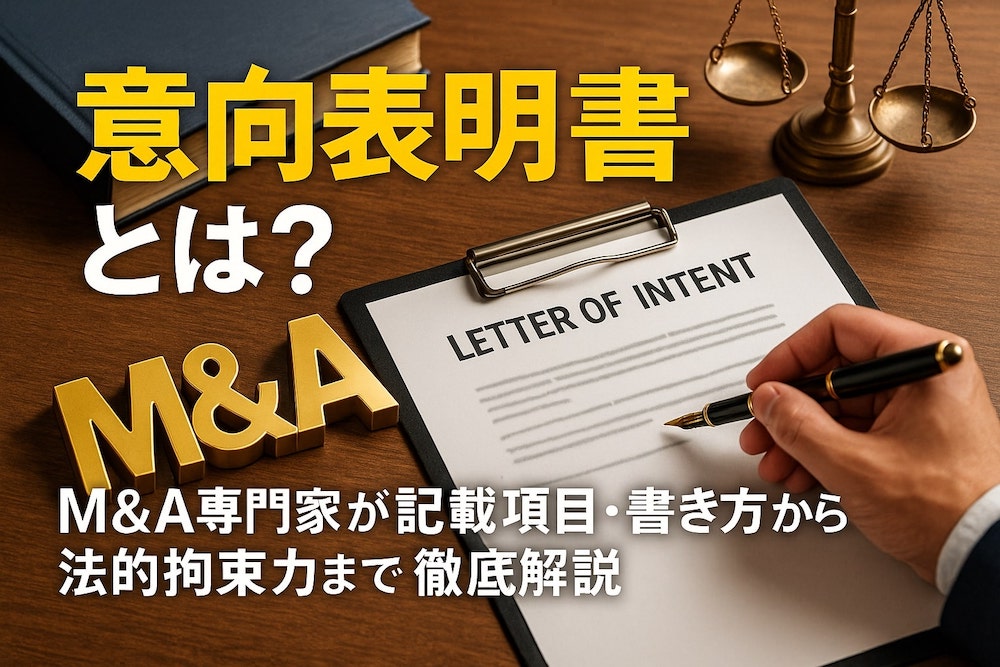
M&Aの交渉プロセスにおいて、買い手候補から提示される「意向表明書(LOI)」。
これは単なる意思表示の書面ではなく、その後の交渉の行方を大きく左右する、いわば航海の「羅針盤」です。
しかし、多くの経営者がその真の重要性や、各項目に隠された買い手の意図を十分に理解しないまま対応してしまいがちです。
本記事では、売り手経営者の皆様が「納得感のあるM&A」を実現するために、意向表明書の読み解き方から賢い対応方法まで、私の実務経験に基づいて徹底解説します。
この一枚の書面を武器に変えるための知識を、ぜひここで手に入れてください。
【総論】意意向表明書(LOI)とは?M&Aプロセスにおける真の役割
まず、「意向表明書とは、そもそも何なのか?」という基本から押さえていきましょう。
この書面の役割を正しく理解することが、全ての交渉の第一歩となります。
M&A専門家が語る意向表明書の定義と目的
意向表明書〈Letter of Intent、略してLOI〉とは、M&Aの検討プロセスにおいて、買い手候補が売り手に対して、買収の意向と希望する基本条件を伝えるために提出する書面です。
これは、交渉の初期段階、多くはトップ面談などを経て、買い手が「本格的に検討を進めたい」と考えたタイミングで提示されます。
私が金融機関で見てきた多くのケースでも、この意向表明書が、それまでの漠然とした交渉を具体的な論点に落とし込む「交渉のスタートライン」として機能していました。
つまり、買い手の真剣度を測り、その後の交渉の土台となる条件を整理することが、この書面の最大の目的なのです。
意向表明書と基本合意書(MOU)の決定的な違い
ここで多くの経営者が混同しがちなのが、「基本合意書〈Memorandum of Understanding、略してMOU〉」との違いです。
では、この二つは何が違うのでしょうか?
決定的な違いは、「誰が」「どのタイミングで」「どのレベルで」合意するかにあります。
| 項目 | 意向表明書(LOI) | 基本合意書(MOU) |
|---|---|---|
| 提出者 | 買い手から売り手への一方的な意思表示 | 売り手と買い手の双方が合意し、署名 |
| タイミング | 交渉の初期段階 | 意向表明書の内容を基に交渉し、合意後 |
| 合意レベル | 買い手の希望条件の提示 | 双方の現時点での合意内容の確認 |
簡単に言えば、意向表明書は買い手からの「ラブレター」のようなものであり、それを受けて条件をすり合わせ、双方が「お付き合いを前提に考えましょう」と確認するのが基本合意書です。
実務上、この二つを区別することで、交渉のステップを丁寧に進める意味合いがあるのです。
なぜ意向表明書は省略されることがあるのか?
意向表明書の提出は、M&Aプロセスにおいて必須ではありません。
では、どのような場合に省略されるのでしょうか?
例えば、古くからの取引関係があるなど、売り手と買い手の間で既に強固な信頼関係が構築されている「相対取引」のケースです。
このような場合、意向表明書という形式的なステップを省略し、いきなり基本合意書の交渉に入ることもあります。
省略のメリットは交渉スピードの向上ですが、デメリットとして、初期段階での条件整理が曖昧になり、後々の交渉で齟齬が生じるリスクもはらんでいます。
中立的な立場から申し上げれば、交渉の土台を固めるためにも、可能な限り意向表明書を取得し、書面で相手の考えを確認することをお勧めします。
【項目別】意向表明書の記載内容と売り手が確認すべき裏側の意図
意向表明書を受け取った際、ただ字面を追うだけでは不十分です。
各項目に込められた買い手の「裏側の意図」を読み解くことが、交渉を有利に進める鍵となります。
M&Aスキームと買収対象範囲
ここには、買い手がどのような手法で会社や事業を譲り受けたいかが記載されています。
具体的には、「株式譲渡」なのか「事業譲渡」なのか、といったM&Aの枠組み〈スキーム〉です。
売り手経営者として確認すべきは、「なぜ、買い手はこのスキームを提案しているのか?」という視点です。
例えば、買い手側の税務上のメリットや、特定の許認可を引き継ぎたいといった事情が背景にあるかもしれません。
提案されたスキームが自社にとって最適とは限りませんので、専門家と相談し、その妥当性を慎重に検討する必要があります。


買収価格(譲渡価額)とその算定根拠
経営者にとって最も関心の高い項目でしょう。
しかし、ここで絶対に注意すべきは、提示された価格の金額だけに目を奪われないことです。
重要なのは、その「価格の算定根拠」と、付随する「価格調整条項」です。
私が金融機関時代に何度も目にしたのは、初期に高い価格を提示して売り手の関心を引き、その後のデューデリジェンス〈買収監査〉で様々な理由をつけて大幅な減額を要求するケースです。
「貴社の将来性を高く評価し、EBITDA〈利払前・税引前・減価償却前利益〉の7倍で評価しました」といった記載があれば、その算出基礎となる事業計画が現実的か、自社の認識とズレがないかを確認することが減額リスクを防ぐ第一歩となります。
役員・従業員の処遇とM&A後の経営方針
父が中小企業を経営していた経験から、私が最も共感するのがこの項目への想いです。
ご自身の退職金はもちろん、長年苦楽を共にしてきた従業員の雇用がどうなるのかは、最大の関心事でしょう。
意向表明書の段階では、「従業員の雇用は原則として維持する」といった抽象的な表現に留まることも少なくありません。
もし記載が曖昧であれば、後の交渉で「具体的に何年間の雇用を保証するのか」「処遇の変更はあるのか」といった点を明確にする必要があります。
経営者の想いを守るためにも、ここは決して妥協してはならない重要な交渉ポイントです。
独占交渉権:安易な付与が招くリスク
独占交渉権とは、一定期間、他の買い手候補と交渉しないことを約束するものです。
買い手は、多額の費用がかかるデューデリジェンスを安心して進めるために、この権利を要求するのが一般的です。
しかし、売り手にとって、これは諸刃の剣です。
安易に独占交渉権を付与すると、その間に現れるかもしれない、より良い条件を提示する他の候補者と交渉する機会を失ってしまいます。
デューデリジェンス(DD)の実施範囲と期間
デューデリジェンス〈DD〉は、買い手が売り手企業の財務や法務などのリスクを精査するプロセスです。
このDDの範囲や期間が、売り手側の負担に直結します。
不必要に広範な資料の提出を求められたり、長期間にわたって対応に追われたりすると、本業に支障をきたす恐れさえあります。
意向表明書に記載されたDDの範囲と期間が、今回のM&Aの規模や内容に対して妥当なものか、専門家の目線で確認することが重要です。
デューデリジェンスについては以下の記事で詳しく解説しております。
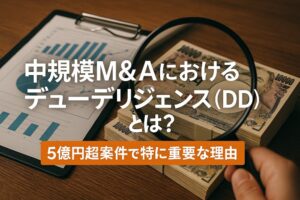
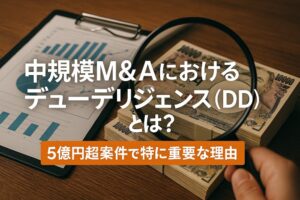
意向表明書の法的拘束力はどこまで?専門家が解説する重要ポイント
「この書面にサインしたら、もう後戻りできないのでは?」というご質問をよく受けます。
意向表明書の法的拘束力について、正確に理解しておきましょう。
原則として法的拘束力はないが、軽視は禁物
結論から言うと、意向表明書の大部分の条項には、原則として法的拘束力はありません。
これは、あくまで交渉のたたき台であり、最終的な合意ではないからです。
しかし、だからといって軽視するのは非常に危険です。
一度合意した内容には道義的な拘束力が生じ、正当な理由なくこれを覆すことは、買い手との信頼関係を著しく損ない、交渉決裂の原因となり得ます。
その後の交渉のベースとなる重要な書面であるという認識は、常に持っておくべきです。
法的拘束力を持たせることが多い条項とは?
意向表明書の中でも、例外的に法的拘束力を持たせることが一般的な条項があります。
代表的なものは、先ほど解説した「独占交渉権」と、M&Aに関する情報を外部に漏らさないことを約束する「秘密保持義務」です。
なぜなら、これらの条項は、買い手が安心して交渉やDDを進めるための「手続きのルール」だからです。
買い手は、これらのルールが破られるリスクを避けるため、明確に法的拘束力があることを記載します。
署名する際は、これらの条項の存在と内容を特に注意深く確認してください。
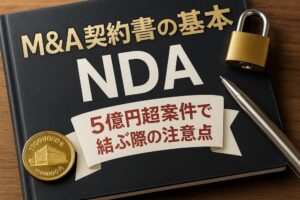
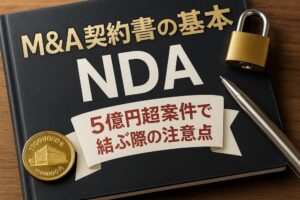
「誠実交渉義務」に隠された意味
条項の中に「誠実交渉義務」という一文が含まれることがあります。
これは、「お互いに、真摯な態度で最終契約の締結に向けて交渉努力をしましょう」という約束です。
この条項に厳密な法的拘束力を持たせるケースは稀ですが、実務上は非常に重要です。
正当な理由なく交渉を打ち切ったり、不合理な要求を繰り返したりした場合、この義務に違反したと見なされる可能性があります。
相手方への配慮と、真摯な交渉姿勢を示すための重要な条項と理解してください。
売り手経営者が意向表明書を受け取った後の正しい対応手順
では、実際に意向表明書を受け取ったら、どのように行動すべきでしょうか?
慌てず、冷静に、以下の3つのステップで進めることが成功の鍵です。
ステップ1:記載内容の精査と不明点の洗い出し
まずは書面を隅々まで熟読し、各項目が自社の希望と合致しているか、曖昧な点や不利な条件はないかを確認します。
この作業は、必ずM&Aアドバイザーなどの専門家と共に行うべきです。
自分一人では気づけないリスクや、交渉すべきポイントを客観的な視点から洗い出すことができます。
「この文言の真意は何か?」「ここに潜むリスクは何か?」といった疑問点をリストアップしていきましょう。
ステップ2:複数の意向表明書を比較検討する際の基準
もし複数の買い手候補から意向表明書を受け取った場合、それは非常に幸運な状況です。
しかし、ここで判断を誤ってはなりません。
では、何を基準に比較すればよいのでしょうか?
価格はもちろん重要ですが、それだけで決めるのは早計です。
私がお勧めするのは、以下の多面的な評価軸です。
- 価格の妥当性:金額だけでなく、算定根拠と実現可能性はどうか?
- M&Aへの熱意:事業への理解は深いか?担当者は信頼できるか?
- シナジー効果の具体性:自社の強みをどう活かそうとしているか?
- 従業員の処遇:雇用や文化を大切にしてくれるか?
- 資金調達の確実性:買収資金の裏付けは確かか?
これらの要素を総合的に評価し、自社の未来を最も安心して託せる相手を見極めることが重要です。
ステップ3:交渉戦略の立案と回答の準備
精査と比較検討が終われば、次はいよいよ交渉です。
「どの条件は譲歩できるか」「どの条件は絶対に譲れないか」を明確にし、交渉の優先順位を決めます。
例えば、「価格は多少譲歩しても、従業員の雇用維持は絶対条件」といった形です。
その上で、意向表明書に対する回答書を作成するか、あるいは基本合意書の対案を準備し、次の交渉に臨みます。
この戦略立案こそが、M&Aアドバイザーの腕の見せ所でもあります。
よくある質問(FAQ)
Q: 意向表明書に署名・捺印を求められた場合、応じるべきですか?
A: 法的拘束力がない部分が多いとはいえ、署名・捺印は重い意味を持ちます。
応じる前に、必ずM&Aアドバイザーなどの専門家に相談し、記載内容、特に「独占交渉権」などの法的拘束力を持つ条項を十分に理解することが不可欠です。
安易な署名は、その後の交渉の自由度を奪う危険性があります。
Q: 提示された買収価格が想定より低い場合、どう対応すれば良いですか?
A: すぐに断ってしまうのは得策ではありません。
まずは、買い手側に価格の算定根拠を丁寧に確認することが重要です。
その上で、自社の強み(技術力、顧客基盤など)や将来性を改めて具体的に伝え、価格交渉の余地を探ります。
企業価値評価の観点から、見過ごされている価値を提示することが交渉の糸口になります。
Q: 意向表明書を提出してきた買い手の信用力はどう判断すれば良いですか?
A: 書面の内容だけでなく、買い手企業そのものを多角的に調査することが重要です。
具体的には、企業のウェブサイトや決算公告で財務状況を確認する、過去のM&A実績を調べる、業界内での評判を聞く、といった方法があります。
アドバイザーを通じて、より詳細な信用調査を行うことも可能です。
Q: 意向表明書の内容が、後の最終契約で変更されることはありますか?
A: はい、十分にあり得ます。
特に、デューデリジェンスの結果、帳簿に現れない債務や訴訟リスクといった新たな問題が発見された場合、それを理由に価格や条件が変更される可能性があります。
意向表明書の段階で楽観視せず、最終契約が締結されるまで、気を抜かずに誠実な情報開示と交渉を続けることが重要です。
Q: 意向表明書のテンプレートは使っても問題ありませんか?
A: テンプレートはあくまで一般的な項目を理解するための参考資料です。
M&Aは一つとして同じものがない、個別性の非常に高い取引です。
テンプレートをそのまま使うのではなく、自社の状況や交渉相手との関係性に応じて、専門家と共に内容を一つひとつ吟味し、カスタマイズすることが不可欠です。
まとめ
意向表明書は、M&Aという長い航海の出発点であり、その後の交渉の方向性を決定づける極めて重要な書面です。
本記事では、中立的なM&A専門家の立場から、売り手経営者が意向表明書の各項目に込められた意図を深く理解し、戦略的に対応するためのポイントを解説しました。
重要なのは、記載された条件を鵜呑みにするのではなく、その裏側を読み解き、自社の価値を最大化するための交渉を行うことです。
そして、何よりも経営者自身が「納得感」を持って次のステップに進むこと。
そのために、本記事で得た知識を武器としてご活用いただければ幸いです。
M&Aの成功は、正しい情報と、信頼できる専門家との連携から始まります。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。