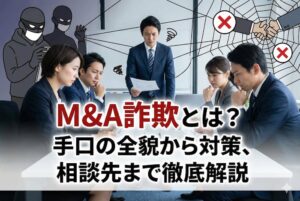5億円超M&Aの一般的な流れと期間:相談からクロージングまでを徹底ガイド
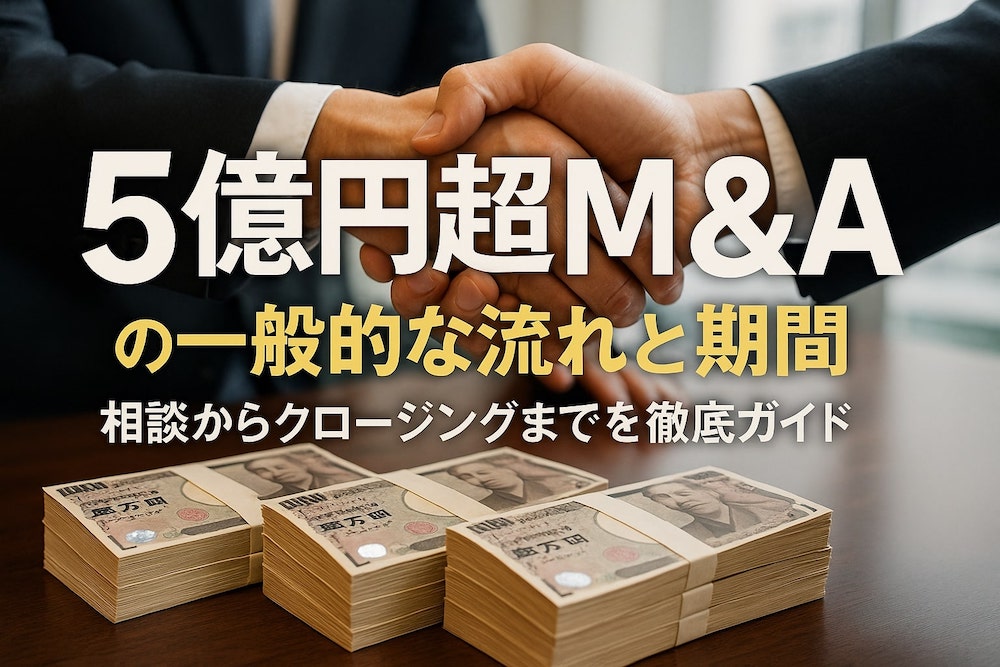
5億円を超える規模のM&Aは、経営者にとって人生を左右する重大な決断です。
しかし、そのプロセスは複雑で、どのくらいの期間を要するのか、誰に相談すべきか、多くの経営者が不安を抱えています。
はじめまして、独立系M&Aコンサルタントの高橋 健一と申します。
大手金融機関で数々のM&Aに携わった後、現在は特定の組織に属さない完全に中立な立場で、中堅・中小企業の経営者をご支援しています。
本記事では、一般的な情報サイトでは語られない「5億円規模」のM&Aに特化した流れと期間を徹底解説します。
この規模だからこそ注意すべきポイントや、成功の鍵を握る「専門家選び」の客観的な基準まで、私の実務経験に基づいて具体的にお伝えします。
この記事を読めば、M&Aの全体像を明確に描き、自信を持って次の一歩を踏み出せるようになるはずです。
5億円超M&Aの全体像と期間の目安
M&Aプロセスの全体フロー
では、M&Aはどのような旅路をたどるのでしょうか。まずは全体像を把握することが、不安を解消する第一歩です。
M&Aのプロセスは、大きく分けて以下の4つのフェーズで進行します。
まるで駅伝のタスキリレーのように、各フェーズの役割を確実に果たし、次の工程へと繋いでいくイメージです。
- フェーズ1:準備・検討段階
- 目的設定、専門家選定、企業価値評価など。
- フェーズ2:マッチング・交渉段階
- 買い手候補の探索、トップ面談、基本合意締結など。
- フェーズ3:デューデリジェンスと最終契約
- 買収監査(DD)、最終条件交渉、最終契約締結など。
- フェーズ4:クロージングとPMI
- 株式・対価の決済、経営の引き継ぎ、統合プロセスなど。
標準的な所要期間:平均9ヶ月~1年半
M&Aの検討を開始してから、最終的に会社(株式)の引き渡しが完了するクロージングまで、一般的に9ヶ月から1年半程度の期間を要します。
ただし、これはあくまで標準的な目安です。
私が現場で見てきた中では、準備が万全で買い手候補がすぐに見つかったケースでは半年で完了したこともありますし、逆にデューデリジェンスで想定外の問題が見つかり、交渉が難航して2年以上かかった案件もありました。
特に5億円規模のM&Aは、買い手側も慎重な判断を下すため、期間が変動しやすいことを念頭に置いておく必要があります。
フェーズ1:準備・検討段階(期間:1~3ヶ月)
なぜ売却するのか? M&Aの目的と戦略を明確にする
M&Aを成功させるための最初の、そして最も重要なステップは「目的の明確化」です。
あなたは、なぜ会社を譲渡しようとお考えなのでしょうか。
後継者が見つからないからでしょうか。
あるいは、大手資本の傘下で事業をさらに成長させたいからでしょうか。
それとも、創業者として利益を確定し、新たな人生を歩みたいからでしょうか。
この「M&Aの軸」が明確でないと、交渉の過程で条件が少し変わっただけで判断が揺らいでしまいます。
私がご支援する際には、必ず経営者様と1対1でじっくりと対話し、この目的を言語化することから始めます。
この「想い」こそが、後の交渉で譲れない一線を守るための羅針盤となるのです。
【最重要】誰と進めるか? 専門家選びの中立的視点
M&Aの成否は、伴走する専門家選びで8割が決まると言っても過言ではありません。
しかし、多くの経営者がこの選択で悩まれます。
ここでは、私の「完全に中立な立場」から、各専門家の特徴を公平に解説します。
- M&A仲介会社 → 売り手と買い手の「間」に立ち、中立的な立場で交渉を調整し、成約を目指します。双方から手数料を得るのが一般的です。
- FA(ファイナンシャル・アドバイザー) → 売り手か買い手の「どちらか一方」と契約し、依頼者の利益を最大化するために活動します。証券会社や銀行、独立系ブティックファームなどがあります。
- その他専門家 → 顧問税理士や公認会計士、金融機関なども相談窓口となります。
では、5億円規模のM&Aでは、どの専門家が最適なのでしょうか。
結論から言えば、一概に「これがベスト」という正解はありません。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせて選ぶことが重要です。
| 専門家の種類 | メリット | デメリット | 5億円規模での適性 |
|---|---|---|---|
| M&A仲介会社 | ・豊富な買い手候補ネットワークを持つ ・中立的な立場で交渉が円滑に進みやすい ・中小企業M&Aの実績が豊富 | ・構造的に利益相反(※)のリスクを抱える ・手数料体系が会社により様々 | ◎ 多くのケースで第一候補となる |
| FA | ・依頼者の利益最大化を徹底的に追求する ・複雑な交渉や大型案件に強い | ・手数料が比較的高額になる傾向 ・相手方との直接交渉で対立構造になりやすい | △ 非常に複雑な利害関係がある場合など |
| 銀行・証券会社 | ・長年の取引関係による信頼感 ・融資と一体で提案できる強み | ・必ずしもM&A専門部署の担当者ではない ・自行の利益を優先する可能性がある | ○ まずは相談してみる価値あり |
(※)利益相反:売り手からは高く、買い手からは安くという相反する要望の間で、仲介会社が自社の手数料(成約)を優先する判断を下す可能性があること。詳しくは「利益相反問題を斬る! M&A仲介における「売り手」と「買い手」の理想的な関係とは?」の記事でも解説してます。
私の経験上、5億円規模のM&Aでは、実績豊富なM&A仲介会社を主軸に検討しつつ、長年の付き合いがある銀行にも声をかけてみるのが現実的な進め方です。
重要なのは、複数の専門家と面談し、担当者の知見や誠実さ、そして何より「自社のことを真剣に考えてくれるか」という相性を見極めることです。


自社の価値を知る:企業価値評価(バリュエーション)の基本
専門家への相談と並行して、自社がどれくらいの価値で評価されるのか、概算を把握しておくことも大切です。
企業価値評価〈バリュエーション〉には様々な手法がありますが、ここでは代表的なものを簡単にご紹介します。
DCF法
将来会社が生み出すキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り引いて評価する手法。理論的ですが、中小企業では精緻な事業計画の策定が難しく、適用が困難な場合もあります。
類似会社比較法
事業内容が似ている上場企業の株価や財務指標を参考に、自社の価値を類推する手法。客観性は高いですが、比較対象となる適切な企業を見つけるのが難しいという側面があります。
年買法(時価純資産+営業利益の数年分)
中小企業のM&A実務で広く用いられる簡易的な手法。会社の時価純資産額に、営業利益の3~5年分を「のれん(ブランドや技術力など目に見えない価値)」として上乗せして計算します。


フェーズ2:マッチング・交渉段階(期間:3~6ヶ月)
買い手候補の探索とノンネームでの打診
専門家との契約が完了すると、いよいよ本格的なマッチングが始まります。
まずは、専門家が持つネットワークの中から、あなたの会社の強みや文化に合致しそうな買い手候補を数十社リストアップします〈ロングリスト〉。
そこからさらに候補を絞り込み〈ショートリスト〉、打診を開始します。
この最初の打診では、会社名が特定されない匿名の情報〈ノンネームシート〉を使用します。
これは、M&Aを検討しているという事実が外部に漏洩するのを防ぐための非常に重要な手続きです。
秘密保持契約(NDA)と企業概要書(IM)の開示
ノンネームシートを見て関心を示した買い手候補とは、次に秘密保持契約〈NDA〉を締結します。
この契約を結んではじめて、より詳細な企業情報が記載された資料〈企業概要書(IM)〉を開示することができます。
IMは、いわば「会社の魅力を伝えるプレゼン資料」です。
財務データはもちろん重要ですが、私がいつも経営者様にお伝えするのは「数字以外の価値」をしっかりと盛り込むことの重要性です。
例えば、長年培ってきた独自の技術、特定の地域での圧倒的なブランド力、熟練した従業員チームの存在など、貸借対照表には載らない「見えない資産」こそが、買い手の心を動かすのです。
経営者同士の対話:トップ面談の進め方と心構え
書類上の情報交換が進むと、次はいよいよ売り手と買い手の経営者同士が顔を合わせる「トップ面談」が行われます。
これは、単なる質疑応答の場ではありません。
お互いの経営理念や事業にかける想い、そして何より「従業員を大切にしてくれるか」といった価値観を確かめ合う、極めて重要な機会です。
ある老舗企業のM&Aでは、買い手社長の「御社の暖簾(のれん)と従業員さんを、我々が責任を持って守ります」という一言が、売り手経営者の心を決めました。
面談では、誠実な姿勢で自社の強みと課題を語り、相手の話にも真摯に耳を傾けることが、信頼関係を築く鍵となります。
交渉の第一歩:基本合意書(LOI)の締結
トップ面談を経て、双方がM&Aに前向きな意思を確認できると、具体的な条件交渉の基礎となる「基本合意書〈LOI〉」を締結します。
ここには、譲渡価格の目安、今後のスケジュール、そして買い手だけに交渉権を与える「独占交渉権」などが盛り込まれます。
多くの項目は、この時点ではまだ法的な拘束力を持ちません。
しかし、その後の交渉の土台となる重要な合意であり、真摯に交渉を進めるという双方の意思表示でもあります。
フェーズ3:デューデリジェンスと最終契約(期間:2~4ヶ月)
買収監査(デューデリジェンス)で何が調べられるのか?
基本合意を締結すると、買い手側による詳細な調査、いわゆる「デューデリジェンス〈DD〉」が始まります。
これは、買い手が「聞いていた話と違う」というリスクを回避するために、公認会計士や弁護士などの専門家を動員して、売り手企業を多角的に精査するプロセスです。
では、5億円規模の企業では、特に何が厳しく見られるのでしょうか。
私の金融機関時代の経験から、特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 財務DD:オーナー経営者にありがちな、個人的な支出と会社の経費の混同〈公私混同〉や、親族企業との不透明な取引は厳しくチェックされます。
- 法務・労務DD:サービス残業などの「未払賃金」は、将来の訴訟リスクに繋がる「簿外債務」として最も警戒される項目の一つです。社会保険の加入状況や、取引先との契約書管理なども精査されます。
売り手としては、このDDに誠実に対応することが信頼関係の維持に不可欠です。
事前に専門家と協力し、想定される問題点を洗い出して整理しておくことが、プロセスを円滑に進める鍵となります。
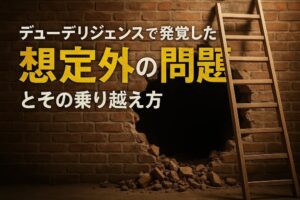
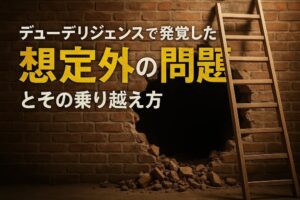
交渉の最終局面:最終契約書(DA)の締結
DDの結果、重大な問題が発見されなければ、いよいよ交渉の最終局面です。
DDで明らかになったリスクなどを反映させ、最終的な譲渡価格や条件を詰めていきます。
そして、双方が合意に至れば、法的な拘束力を持つ「最終契約書〈DA/SPA〉」を締結します。
この契約書には、売り手が「会社の内容は開示した情報に間違いありません」と保証する「表明保証」などの重要条項が含まれ、弁護士を交えて慎重に内容を精査する必要があります。
フェーズ4:クロージングとPMI(期間:1ヶ月~)
M&Aの最終手続き:クロージング
最終契約書の締結後、契約内容に定められた前提条件がすべて満たされたことを確認し、株式の引き渡しと譲渡対価の決済を行います。
この手続きを「クロージング」と呼び、これをもってM&Aは法的に成立します。
経営者にとっては、長かったM&Aの旅路が一つのゴールを迎える瞬間です。
M&Aはゴールではない:PMI(統合プロセス)の重要性
しかし、M&Aの成功の真価が問われるのは、クロージングの後です。
買い手企業が、あなたの会社を自社に円滑に統合していくプロセス「PMI(Post Merger Integration)」こそが、M&Aが本当に成功だったかを決定づけます。
PMIは主に買い手主導で行われますが、売り手経営者も、従業員の不安を取り除き、主要な取引先への挨拶回りを行うなど、円滑な引き継ぎに協力する重要な役割を担います。
私が目指すのは、単に高く売れるM&Aではありません。
残された従業員が新しい環境で活き活きと働き、会社がさらに発展していく、そんな「納得感のあるM&A」です。
そのためには、クロージング後のPMIまで見据えたお相手選びが不可欠なのです。
よくある質問(FAQ)
Q: 5億円規模のM&Aにかかる費用(手数料)はどれくらいですか?
A: 専門家や契約形態により大きく異なりますが、一般的には成功報酬として「レーマン方式」という料率テーブルが用いられます。
これは譲渡価額が大きくなるほど料率が下がる仕組みです。
【レーマン方式の一般的な料率テーブル】
- 5億円以下の部分:5%
- 5億円超~10億円以下の部分:4%
- 10億円超~50億円以下の部分:3%
仮に譲渡価額がちょうど5億円だった場合、成功報酬は「5億円 × 5% = 2,500万円(税別)」が一つの目安となります。
これに加えて、相談開始時に支払う「着手金」や、月々の活動費である「リテイナーフィー」が必要な会社もありますので、契約前に手数料体系をしっかりと確認することが重要です。
Q: 従業員や取引先には、どのタイミングで伝えるべきですか?
A: 情報漏洩は、M&Aの交渉を破談に追い込む最大のリスクです。
そのため、従業員や取引先への公表は、最終契約を締結し、M&Aが確定した後、クロージングの直前または直後に行うのが一般的です。
私の経験上、伝える際は経営者自身の言葉で、M&Aを決断した理由と、従業員の雇用や取引関係を維持する方針を誠実に説明することが、無用な混乱を避けるために不可欠です。
Q: M&Aの交渉途中で、売却をやめることはできますか?
A: 法的拘束力のない「基本合意書」の段階であれば、交渉を中止することは可能です。
しかし、一度「独占交渉権」を付与すると、その期間中は他の候補と交渉できなくなります。
また、「最終契約書」を締結した後は、一方的な破棄は契約違反となり、多額の違約金が発生する可能性があります。
安易な中止は自社の信用を大きく損なうリスクがあることも、心に留めておくべきです。
Q: 会社の業績が悪いと売却は難しいですか?
A: 一概にそうとは言えません。
赤字であっても、買い手にとって魅力的な価値があればM&Aは成立します。
例えば、独自の技術や特許、特定のエリアでの高いシェア、優れた人材、特別な許認可などがそれに当たります。
金融機関の視点で見ても、財務諸表に表れない「見えない価値」をいかに言語化し、アピールできるかが鍵となります。
買い手側にも、赤字企業の繰越欠損金を引き継ぐことで節税に繋がるというメリットがある場合もあります。
Q: 買い手はどのような企業が多いですか?
A: 5億円規模のM&Aでは、同業の中堅・大手企業が、事業エリアの拡大やシェアの獲得を目的として買い手となるケースが最も一般的です。
また、近年では、既存事業とのシナジーを求めて異業種の企業が新規参入するケースや、成長投資を目的とする投資ファンドによる買収も増えています。
買い手のタイプによって、M&A後の経営方針も異なりますので、自社の目的に合った相手を見極めることが重要です。
まとめ
5億円超のM&Aは、平均して9ヶ月から1年半という長い期間を要する一大プロジェクトです。
本記事では、独立系コンサルタントの視点から、準備段階からクロージング後のPMIまで、各フェーズの具体的な流れと注意点を解説しました。
特に重要なのは、M&Aの目的を明確にし、自社に最適な専門家を「中立的な視点」で選ぶことです。
情報こそが、経営者であるあなたの最大の武器となります。
本記事で得た知識をもとに、後悔のない、納得感のあるM&Aを実現してください。
あなたの会社が築き上げてきた価値を、次世代へと正しく繋ぐための第一歩を、自信を持って踏み出しましょう。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。