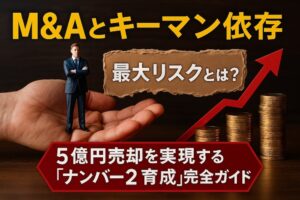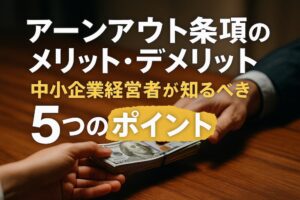中規模M&Aの表明保証条項:5億円案件で売り手が注意すべきポイント
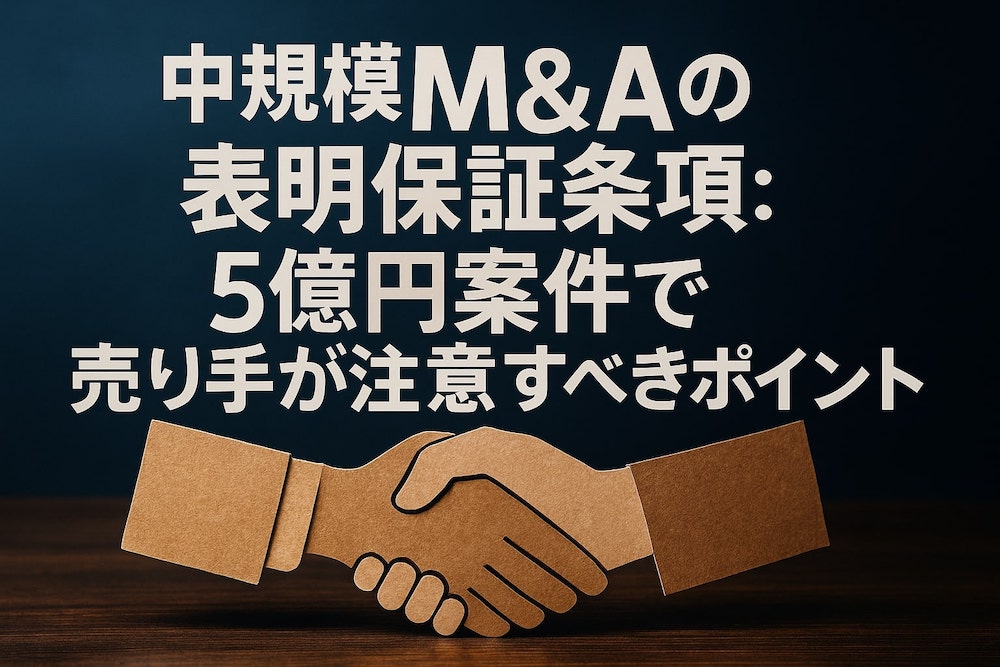
5億円規模のM&Aは、経営者にとって人生を賭けた決断です。その最終局面である株式譲渡契約において、最も神経を使うべき条項の一つが「表明保証」です。
大手金融機関で数々の中小企業M&Aに携わってきた私の経験から断言できるのは、この表明保証条項への理解と準備が、M&A後の経営者の未来を大きく左右するということです。
表明保証は、単なる法務的な手続きではありません。買い手への誠実さを示すと同時に、売り手であるあなた自身を予期せぬリスクから守るための重要な「防御策」なのです。
本記事では、特定の仲介会社に偏らない完全に中立的な立場から、5億円規模のM&Aで売り手経営者が本当に注意すべき表明保証のポイントを、実務経験を交えて分かりやすく解説します。
なぜ5億円規模のM&Aで「表明保証」が特に重要なのか?
経営者の言葉で解説:表明保証条項とは何か
では、そもそも「表明保証」とは何なのでしょうか?法律用語が並ぶ契約書を見ると、つい身構えてしまいますよね。
一言で言えば、表明保証とは「会社の健康状態に関する、売り手から買い手への約束事リスト」です。株式譲渡契約を締結する時点、あるいはM&Aが完了する時点において、「私の会社は、このリストに書かれている内容について、間違いなくこの状態です」と売り手が表明し、その内容を保証することを指します。
買い手はM&Aに先立ち、デューデリジェンス〈DD:買収監査〉で会社の財務や法務状況を調査します。しかし、限られた時間の中ですべてのリスクを洗い出すことは不可能です。そこで買い手は、DDを補完する目的で、売り手に対してこの「約束事リスト」への署名を求めるのです。
もし後日、この約束が破られていた(=表明保証違反)ことが発覚すれば、買い手は売り手に対して損害賠償を請求できる、という仕組みになっています。
中小企業特有のリスクと買い手の視点
特に企業価値5億円前後の中堅・中小企業において、この表明保証が極めて重要になるのには理由があります。それは、中小企業には特有の潜在的リスクが存在し、買い手もその点を強く警戒しているからです。
私が金融機関時代に見てきた典型的な例は、以下のようなものです。
- 管理体制の不備:経理や労務管理を社長やそのご家族が担っており、専門的な管理部門が存在しない。
- 経営者個人への依存:重要な取引先との関係が、契約書ではなく社長個人の信頼関係だけで成り立っている。
- 過去の取引記録の曖昧さ:昔の契約書が紛失していたり、口約束で進めてきた取引があったりする。
買い手の立場からすれば、これらはすべて「見えない爆弾」のように映ります。だからこそ、買い手は表明保証という形で「社長、口頭だけでなく、書面で正式に約束してください」と、リスクの所在を明確にしようとするのです。
これは決して買い手による意地悪ではなく、彼らが自身の投資を守るための合理的な行動と言えます。
【実例で学ぶ】5億円規模の案件で特に狙われやすい表明保証7項目
表明保証の項目は数十から百以上に及ぶこともありますが、全てが同じ重要度ではありません。ここでは、私が実務で見てきた中で、特に5億円規模の中小企業M&Aで論点になりやすい7つの項目を厳選し、その備え方と共に解説します。
1. 財務諸表の正確性(特に「簿外債務」と「未払残業代」)
これは最も狙われやすく、かつ影響が大きい項目です。買い手は提示された決算書を信じて買収価格を算定するため、「この財務諸表は適正で、すべての負債が計上されています」という保証を求めます。
特に問題となるのが「簿外債務」、つまり貸借対照表に載っていない隠れた債務です。その代表格が「未払残業代」。中小企業では、長年の慣行からサービス残業が常態化しているケースが少なくありません。M&Aを機に従業員の権利意識が高まり、過去に遡って残業代を請求されれば、数千万円単位の偶発債務が発生することもあります。
2. 知的財産権(ソフトウェアライセンス、商標など)
「うちはメーカーじゃないから知財は関係ない」と思っていませんか?それは大きな誤解です。例えば、業務で使用しているパソコンのソフトウェア。従業員が勝手にコピーしたものを使っていたり、ライセンス契約に違反した使い方をしていたりしませんか?
私が関わったあるIT企業のケースでは、開発に使っていたオープンソースソフトウェアのライセンス規約を誤って解釈しており、M&A後の事業計画に大きな支障が出ることが判明しました。自社で開発した製品だけでなく、他者から借りている権利についても正確な把握が求められます。
3. 労務関連(サービス残業、社会保険の加入状況)
未払残業代もここに含まれますが、他にも注意すべき点があります。例えば、パートやアルバイトの社会保険の加入漏れです。加入義務があるにもかかわらず未加入だった場合、過去2年分に遡って保険料の納付を求められる可能性があります。
従業員とのトラブルは、M&A後の円滑な事業運営に直接影響します。買い手は、従業員の満足度や労務コンプライアンスの状況を非常に気にします。
4. 許認可・届出の網羅性
建設業、飲食業、運送業、古物商など、事業運営に許認可が必要な業種は数多くあります。これらの許認可が適切に取得・更新されているか、という点も厳しく問われます。
ある製造業の案件では、工場の増築時に必要な届出が漏れていたことがDDで発覚し、M&Aのクロージングが大幅に遅れました。社長自身が「昔のことだから」と失念しているケースも少なくないため、注意が必要です。
5. 重要な契約関係(チェンジ・オブ・コントロール条項)
これは見落とすとM&Aの前提が根底から覆る可能性がある、非常に重要な項目です。主要な取引先や、本社・工場の賃貸借契約書などに、「株主の変更(=M&A)があった場合、相手方は契約を解除できる」という趣旨の条項〈チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項〉が含まれていることがあります。
もし最大の売上を誇る取引先との基本契約にこの条項があり、M&A後に契約を打ち切られてしまったら、事業価値は大きく毀損します。買い手にとって、これは絶対に避けたいリスクです。
6. 環境関連(土壌汚染、アスベストなど)
製造業や、自社で土地・建物を所有している企業で特に注意が必要な項目です。過去の事業活動に起因する土壌汚染や、建物に使用されているアスベスト(石綿)などが、後から発覚するリスクです。
これらの浄化や除去には莫大な費用がかかるため、買い手は非常に敏感になります。売り手である経営者自身が、何十年も前の土地利用の歴史まで把握していないケースも多く、潜在的なリスクとなりやすいのです。
7. 訴訟・紛争リスク
現在、訴訟を抱えていないことはもちろんですが、「将来的に紛争に発展する可能性のある事案」も表明保証の対象となります。例えば、退職した元従業員とのトラブルの火種や、顧客からのクレームでまだ解決していないものなどが含まれます。
「これは内々で処理したから大丈夫だろう」という自己判断は危険です。買い手は、どんな些細な火種でも、M&A後に大きな火事になる可能性を懸念しています。
表明保証違反のリスクから身を守る!売り手の交渉術と防御策
では、これらのリスクに対して、売り手はどうすれば身を守れるのでしょうか?ここでは具体的な交渉術と防御策をお伝えします。
最大の防御は「正直な情報開示(ディスクロージャー)」
まず、大原則として覚えていただきたいのは、「隠すことが最大のリスク」だということです。不利な情報を隠して契約をしても、後で発覚すれば深刻な表明保証違反となり、多額の損害賠償を請求されることになります。
最大の防御策は、「開示書(ディスクロージャー・スケジュール)」を効果的に活用することです。これは、表明保証条項の「例外リスト」のようなものです。例えば、「未払残業代は存在しない」という表明保証項目に対し、開示書で「ただし、〇〇部門において月平均〇時間程度の未払残業代が存在する可能性がある」と正直に記載すれば、その事実は表明保証違反の対象から外れます。
不利な情報でも正直に開示することで、リスクを飼いならし、交渉のテーブルに乗せることができるのです。これは誠実さの証しとなり、かえって買い手からの信頼を得ることにも繋がります。
交渉すべき3つの重要ポイント:上限・期間・下限
開示で対応しきれないリスクについては、契約条件でコントロールします。特に重要なのが、損害賠償責任の範囲を限定する以下の3つのポイントです。
1. 補償上限額(キャップ)
表明保証違反があった場合に売り手が支払う損害賠償額の上限です。買い手は譲渡対価の100%を求めてきますが、売り手としてはできるだけ低く抑えたいところです。
5億円規模の案件では、譲渡対価の10%~50%程度が実務的な落としどころになることが多いです。
2. 補償期間(サバイバル)
M&A完了後、いつまで表明保証違反の責任を負うかという期間です。これがなければ永久に責任を負うことになりかねません。一般条項は1年~2年、税務関連は税務調査のリスクを考慮して3年~7年といったように、項目ごとに期間を設定するのが一般的です。
3. 補償下限額(バスケット/ミニマム)
少額の損害賠償請求をいちいち受けないようにするためのものです。「損害額が〇〇円に達するまでは請求しない」という取り決めです。譲渡対価の0.5%~1%程度を目安に設定することが多いです。これにより、経営者はM&A後の些細な請求に煩わされることがなくなります。
「知る限り」という魔法の言葉(知識表明)の正しい使い方
表明保証の条文に「売り手の知る限りにおいて(as far as Seller’s knowledge is concerned)」という一文を加えることで、責任範囲を限定する方法があります。これは「私が知っている範囲では問題ありませんが、私が知らないことについては保証できません」という意味合いを持ちます。
ただし、この「魔法の言葉」を安易に多用すると、買い手から「自社のことを何も把握していないのか?」と不信感を抱かれる可能性があります。本当に調査が困難な過去の事実や、将来の予測に関わるような項目など、ここぞという場面で限定的に使うのが効果的な交渉術です。
【高橋健一の視点】表明保証保険は5億円案件で有効か?
最近、「表明保証保険(R&W保険)」という選択肢も注目されています。これは、売り手の表明保証違反による損害賠償責任を、売り手に代わって保険会社が買い手に支払うというものです。
中立的な立場から見るメリット・デメリット
保険会社のPRを鵜呑みにするのではなく、客観的にメリットとデメリットを評価することが重要です。
売り手のメリット
最大のメリットは、M&A後に表明保証違反が発覚しても、金銭的な負担を保険会社に移転できることです。これにより、売り手は安心して譲渡代金を手にし、事業承継を完了できる「クリーンイグジット」が実現できます。
デメリット/注意点
最大のデメリットはコストです。保険料は補償限度額の1%~3%程度が目安ですが、多くの場合で最低保険料が設定されており、500万円以上になることも珍しくありません。5億円のM&Aで数百万の保険料は大きな負担です。
また、開示書に記載した既知の事実や、意図的に調査しなかった事項は補償の対象外となるなど、万能ではない点も理解しておく必要があります。
費用対効果の判断基準
では、どのような場合に保険の利用を検討すべきでしょうか?私の経験上、以下のようなケースでは費用対効果が見合う可能性があります。
- 相続人が複数いて、将来の補償責任を巡るトラブルを避けたい場合
- 買い手が海外企業や投資ファンドで、非常に厳しい表明保証を求めてきている場合
- 譲渡代金をすぐに次の事業投資や引退後の生活資金として使いたい場合
最終的には、保険料という「確定したコスト」を支払って将来の「不確定なリスク」を回避するかどうかの経営判断になります。
最終契約の前に!信頼できる専門家(弁護士)との連携が成否を分ける
ここまで様々な実務ポイントを解説してきましたが、これらを経営者一人で判断し、交渉するのは極めて困難です。ここで専門家の力が不可欠となります。
なぜ仲介会社任せでは危険なのか
M&Aのプロセスを支援してくれる仲介会社は心強い存在ですが、表明保証の交渉に関しては注意が必要です。仲介会社の成功報酬は、M&Aの「成約」によって発生します。そのため、彼らのインセンティブは、良くも悪くも取引をまとめる方向に向かいがちです。
売り手の表明保証リスクを一つ一つ細かく潰していくことよりも、取引を円滑に進めることを優先する場面がないとは言い切れません。
あなたの利益を100%守るためには、あなただけの代理人が必要なのです。
M&Aに強い弁護士の見極め方
その代理人こそが、M&Aの表明保証交渉の経験が豊富な弁護士です。単に企業法務に詳しいだけでなく、実際に買い手側の弁護士と丁々発止の交渉を繰り広げた経験のある弁護士でなければ務まりません。
良い弁護士を見極めるには、以下のような質問を投げかけてみるとよいでしょう。
- 「これまで売り手側で担当したM&A案件の規模と件数を教えてください」
- 「表明保証の交渉で、特に重視しているポイントは何ですか?」
- 「仲介会社や買い手から紹介された弁護士ではなく、セカンドオピニオンとして相談できますか?」
仲介会社からの紹介を鵜呑みにせず、複数の弁護士と面談し、心から信頼できると感じるパートナーを選ぶことが、あなたの未来を守る上で最後の、そして最も重要なステップです。
よくある質問(FAQ)
Q: 少しでも高く売りたいので、不利な情報は隠しても良いですか?
A: 絶対に避けるべきです。私の経験上、後で意図的な隠蔽が発覚した場合、損害賠償額が譲渡代金を上回る「賠償地獄」に陥るケースすらあります。誠実な情報開示こそが、最終的に売り手であるあなた自身を守る最善の策だと断言します。
Q: 表明保証違反が見つかったら、すぐに契約解除になりますか?
A: 必ずしもそうではありません。違反の重要度によります。軽微な違反であれば、契約書で定めた上限額の範囲内で金銭的な補償をして解決することがほとんどです。契約書に「どのような場合に契約解除できるか」が明記されていますので、弁護士と事前にその条件をしっかり確認することが重要です。
Q: 簿外債務があるか自分でも分かりません。どう調査すれば良いですか?
A: まずは顧問税理士に相談し、過去の会計処理にリスクがないかを徹底的に見直すことが第一歩です。特に、引当金の計上や固定資産の減損処理などは論点になりやすい部分です。必要であれば、M&A専門の会計事務所にセカンドオピニオンを依頼し、財務デューデリジェンスの予行演習をしてもらうことも極めて有効です。
Q: 買い手から提示された表明保証の条文が多すぎて、全てに対応できません。
A: その通りです。すべてを完璧に保証するのは不可能ですし、その必要もありません。だからこそ交渉が重要になります。弁護士と共に、「自社にとってリスクが高く、絶対に受け入れられない項目」「交渉次第で修正可能な項目」「比較的リスクが低く、受け入れやすい項目」を仕分けし、交渉の優先順位をつけることが現実的な対応策です。
Q: 表明保証保険の保険料は誰が負担するのが一般的ですか?
A: ケースバイケースですが、交渉事項の一つです。売り手がリスクを回避するために加入するため売り手が負担するケースもあれば、買い手が安心して買収を進めるために負担するケース、あるいは双方が折半するケースもあります。最近では、買い手側が主導して保険に加入する「買い手型」の保険も増えています。
まとめ
5億円規模のM&Aにおける表明保証条項は、売り手経営者にとって大きなプレッシャーとなる専門領域です。しかし、その本質は決して複雑なものではありません。「自社の情報を誠実に伝え、予期せぬリスクの範囲を契約書で明確にする」こと、これに尽きます。
金融機関時代から独立後の現在まで、私は多くの経営者の決断に立ち会ってきました。「納得感のあるM&A」を実現された方は、例外なくこの表明保証というプロセスに真摯に向き合っていました。
本記事で解説したポイントを参考に、信頼できる専門家と連携し、自社の状況を正確に把握・開示することで、過度なリスクを負うことなく、安心して次のステージへ進む準備を整えてください。情報こそが、この重要な局面における経営者の最大の武器となるのです。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。