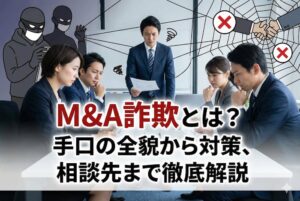【M&A用語集】これだけは押さえたい専門用語を分かりやすく解説
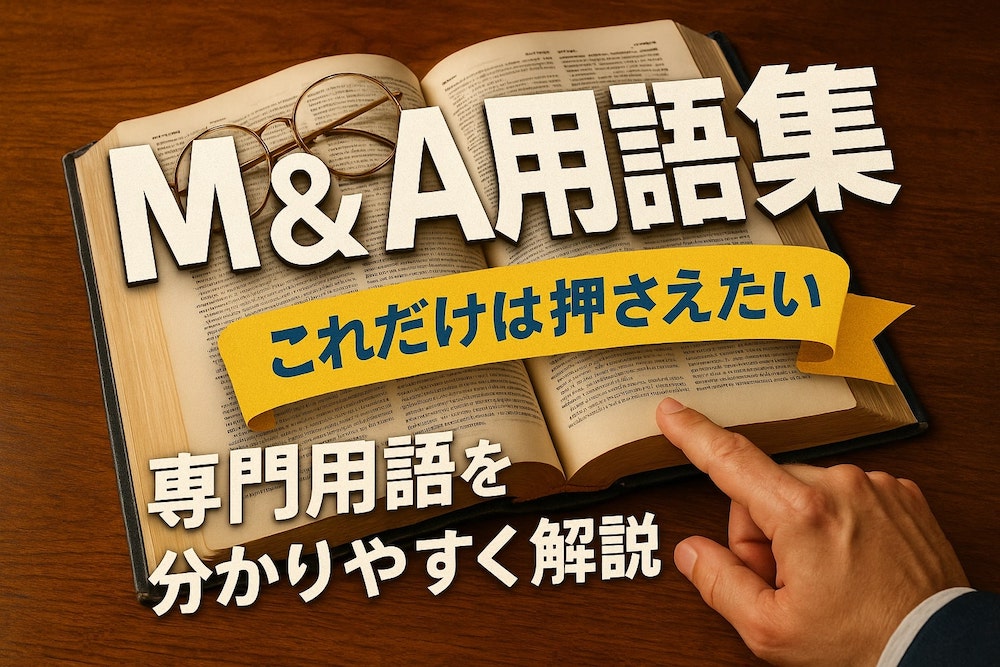
M&Aを検討し始めた経営者の皆様が、最初に直面する壁の一つが「専門用語の多さ」ではないでしょうか。専門家との会話や資料の中で、意味の分からない言葉が出てきて戸惑った経験をお持ちかもしれません。
しかし、ご安心ください。全ての用語を完璧に暗記する必要はありません。重要なのは、各用語がM&Aのプロセスのどこで登場し、どのような意味を持つのか、その勘所を押さえることです。
本記事は、単なる用語の辞書ではありません。M&Aという複雑な航海を乗り切るための「地図」です。私がこれまで多くの中小企業経営者をご支援してきた経験から、これだけは押さえておきたいという必須用語を厳選しました。
さらに、それぞれの用語が「なぜ重要なのか」「どの専門家と話す際にキーポイントとなるのか」を、中立的な立場から分かりやすく解説します。
この記事を読めば、専門家との対話を有利に進め、納得感のあるM&Aを実現するための第一歩を踏み出せるはずです。
M&Aの全体像を掴む!基本の3つのカテゴリー
まずは、M&Aの全体像を理解するための基本的な用語から見ていきましょう。これらは、いわばM&Aの世界の「登場人物」「目的」「手段」にあたります。
① M&Aの「主体」と「目的」に関する用語
M&Aの議論を始める前に、まず「誰が、何のために」行うのかを明確にしなければなりません。自社の立ち位置と目的を定義するための、最も基本的な用語です。
売り手(ターゲット)
会社や事業を譲渡する側。
買い手(買収者)
会社や事業を譲り受ける側。
事業承継
後継者不在などを理由に、M&Aを通じて第三者に事業を引き継ぐこと。私の父も中小企業の経営者でしたが、常にこの問題を意識していました。
シナジー効果
企業同士が統合することで生まれる相乗効果のこと。〈1+1が2以上になる効果〉。例えば、販路の拡大、技術の融合、コスト削減などが挙げられます。買い手は、このシナジー効果を期待して買収価格を決定します。
② M&Aの「手法(スキーム)」に関する用語
次に、どのような方法で会社や事業を動かすのか、その「手法〈スキーム〉」に関する用語です。手法によって税務や手続きが大きく異なるため、自社にとって最適な選択をすることが重要です。
株式譲渡
売り手企業の株主が、その保有株式を買い手に売却する手法。中小企業のM&Aでは、手続きが比較的簡便であるため、最も多く用いられるスキームです。会社の経営権が包括的に移転します。
事業譲渡
会社の事業の一部または全部を、買い手に売却する手法。特定の事業だけを切り出して売却したい場合に有効です。ただし、従業員の転籍や契約の巻き直しなど、手続きが煩雑になる側面もあります。
会社分割
会社の一部事業を切り離し、別会社として独立させたり、既存の他社に承継させたりする手法。組織再編行為の一環として用いられます。
合併
複数の会社を一つの法人格に統合する手法。
③ M&Aの「専門家」に関する用語
さて、ここがM&Aの成否を分ける上で、私が最も重要だと考えているポイントです。M&Aの航海には、信頼できる水先案内人が不可欠ですが、専門家にはそれぞれ異なる役割と立場があります。
M&A仲介会社
売り手と買い手の「両方」と契約し、中立的な立場で両者の間に入り、交渉を調整してM&Aの成立を目指します。日本の友好的M&Aでは主流の形態です。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)
売り手か買い手の「どちらか一方」とだけ契約し、その依頼者の利益が最大化するように助言・交渉を行います。依頼者の「代理人」という立場です。
弁護士
契約書の作成・レビューや法務デューデリジェンスなど、M&Aプロセスの法務面全般をサポートします。
公認会計士・税理士
財務・税務デューデリジェンスや企業価値評価、M&Aの税務戦略の立案などを担当します。
「仲介」と「FA」の違いは、特に慎重に理解すべきです。
仲介会社は双方から手数料を得るため、構造的に「利益相反」が生じる可能性があります。例えば、早く取引を成立させることを優先するあまり、一方の依頼者にとって不利な条件での妥結を促す、といったケースも理論上は考えられます。
もちろん、多くの仲介会社は職業倫理に基づき、誠実に業務を遂行しています。
重要なのは、経営者自身がこの構造を理解し、「この担当者は本当に自社のことを考えてくれているか?」という視点を常に持つことです。
FAは完全に自社の味方ですが、相手方との直接交渉になるため、交渉が難航する可能性もあります。
どちらが良いと一概には言えず、自社の状況やM&Aの目的に応じて、複数の専門家と面談し、慎重にパートナーを選ぶべきです。
M&Aのプロセス順で理解する!実践的な重要用語
ここからは、M&Aの実際の流れに沿って、各ステップで登場する重要用語を解説します。「いつ、何のために」使われる言葉なのかを理解することで、交渉を有利に進めることができます。
【ステップ1】検討・相談フェーズ
M&Aの準備運動ともいえる初期段階です。ここで結ぶ契約が、後々のプロセス全体を規定するため、非常に重要です。
秘密保持契約書(NDA/CA)
M&Aの検討を始め、具体的な企業情報をやり取りする際に、最初に締結する契約です。〈Non-Disclosure Agreement / Confidentiality Agreement〉の略で、内容は同じです。
これにより、開示した自社の機密情報が外部に漏洩することを防ぎます。逆に言えば、これを結ばずに安易に情報開示してはいけません。
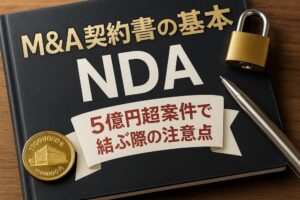
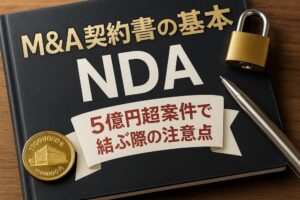
アドバイザリー契約
M&A仲介会社やFAに正式に業務を依頼する際に結ぶ契約です。ここで必ず確認すべきは「業務範囲」と「報酬体系」です。
特に報酬は、着手金、中間金、成功報酬などがあり、成功報酬の計算方法(レーマン方式が一般的)や、その計算基準(「株式価値」か「有利子負債を含む企業価値」か)によって、支払う金額が数百万円単位で変わることもあります。契約書にサインする前に、隅々まで読み込み、不明点は必ず質問してください。
ノンネームシート
企業名を伏せた〈ノンネーム〉状態で、会社の概要をまとめた資料です。アドバイザーがこれを使って、買い手候補に打診を行います。
「業種、エリア、売上規模、事業の強み」などが簡潔に記載されます。特定されない範囲で、自社の魅力が最大限伝わる内容になっているか、アドバイザーと一緒に知恵を絞るべきポイントです。
【ステップ2】マッチング・交渉フェーズ
買い手候補が見つかり、いよいよ具体的な交渉が始まる段階です。経営者の皆様の意思決定が、M&Aの方向性を大きく左右します。
トップ面談
売り手と買い手の経営者同士が初めて顔を合わせる場です。これは単なる条件交渉の場ではありません。
私が現場で見てきた成功事例では、経営者同士が互いの経営理念や従業員への想い、事業の未来像に共感し合ったことで、難しい条件交渉を乗り越えられたケースが数多くあります。自社の「目に見えない価値」を伝える絶好の機会と捉えましょう。
意向表明書(LOI)
〈Letter of Intent〉の略。トップ面談などを経て、買い手が「この条件であれば貴社を買収したいと考えています」という意思を、売り手に対して正式に示す書面です。
希望買収価格やスキーム、今後のスケジュールなどが記載されます。これはあくまで買い手からの「提案書」であり、これをもって売却が決まるわけではありません。
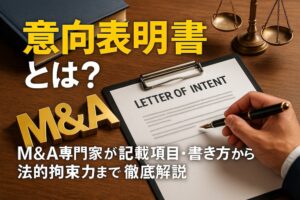
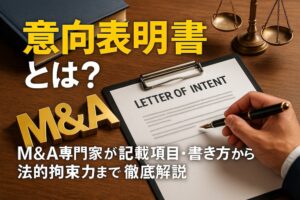
基本合意書(MOU)
〈Memorandum of Understanding〉の略。LOIの内容をベースに、売り手と買い手の双方がM&Aの基本的な条件について「合意」したことを確認するための契約書です。一般的に買収価格などの主要条件に法的拘束力はありませんが、「独占交渉権」の付与が重要なポイントになります。
これは「基本合意の有効期間中は、他の買い手候補と交渉しません」という約束です。買い手にとっては、この後のデューデリジェンスに安心してコストを投下できるメリットがあります。
【ステップ3】最終契約フェーズ
M&Aの最終コーナーです。専門的な調査や契約締結が行われ、専門家の力が不可欠になりますが、経営者自身もその内容を理解しておくことが、後々のトラブルを防ぎます。
デューデリジェンス(DD/買収監査)
基本合意後、買い手が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセスです。財務・税務・法務・事業など、多角的な観点から行われます。
ある老舗企業のケースでは、DDで過去の税務処理の誤りが発覚しましたが、経営者が誠実に対応し、修正したことで、かえって買い手からの信頼を得ることができました。DDは「会社の健康診断」のようなものです。誠実な情報開示が、最終的な信頼関係の構築に繋がります。
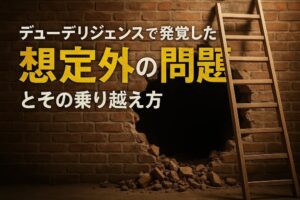
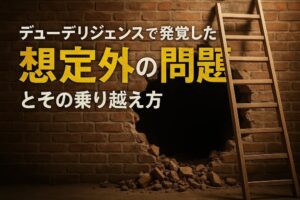
企業価値評価(バリュエーション)
会社の値段を算定するプロセスです。専門家は、DCF法〈将来生み出すキャッシュフローを基に評価〉、純資産法〈会社の純資産を基に評価〉、類似会社比較法〈上場している同業他社の株価などを参考に評価〉といった複数の手法を組み合わせて理論価値を算出します。
ここで重要なのは、評価額は絶対的なものではなく、あくまで交渉の「出発点」であるということです。最終的な売却価格は、交渉によって決まります。
最終契約書(DA/SPA)
M&Aの全ての条件を確定させる、最終的な契約書です。DA〈Definitive Agreement〉は総称で、株式譲渡の場合はSPA〈Stock Purchase Agreement〉と呼ばれます。ここには、最終的な譲渡価格、クロージングの前提条件、そして「表明保証」といった極めて重要な項目が含まれます。
表明保証とは、売り手が「開示した情報は全て真実かつ正確です」と保証する条項で、もし違反があれば損害賠償の対象となり得ます。
クロージング
譲渡代金の決済と、株式や事業の引き渡しが完了する、M&A取引の実行日です。この日をもって、会社の経営権が正式に買い手に移転します。まさに、M&Aという駅伝のタスキが渡される瞬間です。
よくある質問(FAQ)
Q: M&Aの専門用語は全て覚える必要がありますか?
A: 全てを暗記する必要はありません。重要なのは、本記事で紹介したような必須用語の「意味」と「使われる場面」を理解し、専門家との会話についていけるようになることです。分からない用語が出てきたら、遠慮なくその場で専門家に質問する姿勢が何よりも大切です。「情報こそが経営者の武器」です。知ったかぶりは禁物です。
Q: M&A仲介会社とFAは、どちらに相談するのが良いのでしょうか?
A: 一概にどちらが良いとは言えません。仲介会社は売り手と買い手の間に入り、双方の妥協点を探りながら成約を目指すため、交渉がスムーズに進みやすいメリットがあります。
一方、FAは完全に自社の味方として利益の最大化を目指してくれる心強さがあります。自社の状況(例えば、交渉力に自信があるか、業界に詳しいか)や、M&Aで何を最も重視するか(スピードか、価格か)によって最適なパートナーは異なります。
それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、複数の専門家と面談し、信頼できると感じた相手を選ぶことを強くお勧めします。
Q: 企業価値評価で提示された金額が、そのまま売却価格になるのですか?
A: 必ずしもそうではありません。企業価値評価は、あくまで客観的なデータに基づいた理論値であり、交渉の出発点に過ぎません。
最終的な売却価格は、買い手が見込むシナジー効果の大きさや、他に有力な買い手候補がいるかといった交渉状況、経済全体のタイミングなど、様々な要因によって理論値を上回ることも下回ることもあります。評価額の根拠を理解し、自社の強みを的確にアピールすることが価格交渉の鍵となります。
Q: デューデリジェンス(DD)では、何でも正直に開示しないといけないのですか?
A: はい、誠実な情報開示が原則です。意図的に不利な情報(例えば、簿外債務や潜在的な訴訟リスクなど)を隠した場合、後で発覚すると最終契約書の「表明保証」違反となり、多額の損害賠償を請求されるリスクがあります。
DDは買い手からの厳しい調査であると同時に、自社の課題を客観的に洗い出す良い機会でもあります。真摯に対応することが買い手との信頼関係を築き、結果として円滑なM&Aに繋がるのです。
Q: 「のれん」とは何ですか?
A: 「のれん(営業権)」とは、M&Aの買収価格が、買収される企業の純資産額(資産から負債を引いた額)を上回った際の、その差額のことです。これは、企業のブランド力、技術力、顧客基盤といった貸借対照表には載らない「目に見えない価値」が、金額として評価されたものと言えます。
会計上、この「のれん」は無形固定資産として計上され、日本の会計基準では原則として20年以内の期間で規則的に償却(費用計上)していくことになります。


まとめ
本記事では、M&Aを検討する経営者の皆様が押さえておくべき必須用語を、プロセスの流れに沿って解説しました。用語の一つひとつを理解することは、M&Aの全体像を把握し、各ステップで適切な判断を下すための羅針盤となります。
特に重要なのは、M&A仲介会社やFAといった専門家の役割を正しく理解し、自社の状況に最適なパートナーを選ぶことです。専門用語を知ることは、彼らと対等に渡り合い、自社の利益を守るための「武器」になります。
M&Aは、経営者人生における非常に大きな決断です。情報格差によって不利な立場に立つことなく、納得のいく形で大切な会社を未来へ繋ぐために、本記事で得た知識をぜひご活用ください。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。


※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。