【独占インタビュー】5億円超で会社を売却した社長が語る「決断の瞬間」
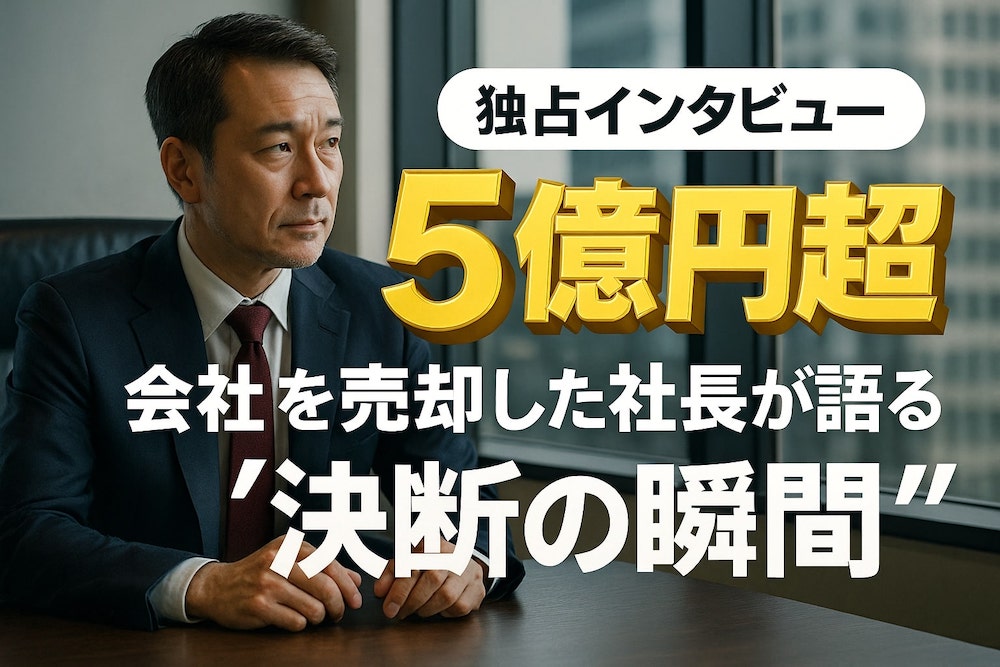
会社の売却は、経営者にとって人生を左右する大きな決断です。
「本当にこの選択で良いのか」
「長年苦楽を共にした従業員はどうなるのか」
「自分の人生はどう変わるのか」
出口の見えない問いに、眠れない夜を過ごす経営者は少なくありません。
本記事では、5億円超で会社を売却したある経営者に独占インタビューを実施。
事業の将来と個人の人生の間で揺れ動いた葛藤、買い手との交渉の舞台裏、そして全てを懸けた「決断の瞬間」について、生々しい言葉で語っていただきました。
これは単なる成功譚ではありません。
M&Aの専門家である私の視点も交えながら、あなたの迷いを照らし、次の一歩を踏み出すための「リアルな道標」をお届けします。
なぜ「会社売却」という選択肢が生まれたのか?【決断の序章】
業界の先行き不安と、後継者不在という現実
「正直に言うと、最初は会社を売るなんて考えもしませんでした」
そう語るのは、関東地方で精密部品製造業を営む田中社長(仮名・60歳)です。
創業から25年、従業員50名の会社を5億2000万円で大手メーカーに売却した田中社長の決断の背景には、多くの中小企業経営者が直面する共通の課題がありました。
「転機は3年前でした。大手企業がデジタル化を進める中、うちのような従来型の製造業は価格競争に巻き込まれるようになったんです」
田中社長の会社が手がけていたのは、自動車部品の精密加工。
長年培った技術力で安定した収益を上げていましたが、業界全体のデジタル化の波は避けられませんでした。
「設備投資に億単位の資金が必要になる。でも、それを回収できる保証はない。何より、息子は全く違う道を歩んでいて、会社を継ぐ気はありませんでした」
この状況は決して特殊なケースではありません。
帝国データバンクの調査によると、2024年の全国後継者不在率は52.1%で、依然として半数以上の企業で後継者が不在となっています [1]。
特に、田中社長のような60代の経営者では、後継者不在率はさらに高くなります。
「このまま行けば、会社は私の代で終わり。従業員の雇用も守れない。そんな現実が見えてきたとき、初めてM&Aという選択肢を意識しました」
最初の相談相手は「顧問税理士」。しかし感じた「情報格差」
多くの経営者がそうであるように、田中社長も最初に相談したのは長年付き合いのある顧問税理士でした。
「先生に相談したところ、『M&Aも一つの選択肢ですね』と言われましたが、具体的な進め方や自社の価値については、正直よく分からないという感じでした」
これは決して税理士の能力不足ではありません。
M&Aは専門性の高い分野であり、税務や会計の専門家であっても、必ずしもM&Aの実務に精通しているとは限らないのです。
「自分でインターネットで調べても、情報が多すぎて何が正しいのか分からない。M&A仲介会社のホームページを見ても、どこが信頼できるのか判断がつきませんでした」
田中社長が感じた「情報格差」は、多くの経営者が直面する課題です。
M&A市場は急速に拡大しており、2024年のM&A件数は前年比14%増の1,221件と、17年ぶりに過去最多を更新しました [2]。
しかし、情報の非対称性により、売り手側の経営者が不利な立場に置かれるケースも少なくありません。
「結局、3ヶ月ほど一人で悩み続けました。その間、会社の業績は下がり続け、従業員にも不安が広がっているのを感じていました」
【高橋の視点】M&Aが選択肢になる「経営のサイン」とは
田中社長のケースから見えてくるのは、M&Aを検討すべき典型的な「サイン」です。
私がこれまで相談を受けた経営者の多くが、以下のような状況に直面していました。
1. 後継者不在問題
現在、事業承継の「脱ファミリー化」が進んでおり、M&Aほか(20.5%)、外部招聘(7.5%)など、社外の第三者を経営トップとして迎え入れる傾向が強まっています [1]。
2. 業界構造の変化
デジタル化、グローバル化、規制変更など、業界全体の構造変化に対応するための大規模投資が必要になった場合、単独での対応が困難になることがあります。
3. 経営者の年齢と健康問題
60代以上の経営者の場合、自身の健康問題や体力的な限界を感じ始めることが、M&Aを検討するきっかけになることが多いです。
4. 従業員の雇用維持への責任感
「会社を畳むより、従業員の雇用を守りたい」という経営者の責任感が、M&Aという選択肢を後押しすることがあります。
重要なのは、これらのサインを感じたときに、一人で抱え込まずに専門家に相談することです。
情報収集は早ければ早いほど、選択肢が広がります。
5億円超の評価額へ。信頼できるパートナーとの交渉の舞台裏
買い手候補との「お見合い」。重視したのは事業へのリスペクト
田中社長が最終的にM&A仲介会社に相談を決めたのは、知人の経営者からの紹介がきっかけでした。
「同業者の先輩が、『信頼できる仲介会社を知っている』と紹介してくれたんです。最初の面談で、担当者が私の会社の技術について詳しく質問してくれたとき、『この人たちなら任せられる』と感じました」
M&A仲介会社の選定は、成功の鍵を握る重要な要素です。


現在、M&A仲介手数料には法的な規制や上限がなく、各社が独自に設定しているため、手数料体系は会社ごとに大きく異なります [3]。
小規模M&A(売買価格が数億円程度)の場合、M&A仲介手数料の相場は売買価格の5%〜10%程度とされています [4]。
「手数料も重要でしたが、それ以上に、私たちの事業を理解し、適切な買い手を見つけてくれるかどうかを重視しました」
企業価値評価の結果、田中社長の会社は当初4億円程度と算定されました。
中堅・中小企業では「コストアプローチ」が基本とされ、「時価純資産+実質営業利益」という年買法(年倍法)がよく使用されます 。
「最初の評価額を聞いたときは、正直『こんなものか』と思いました。でも、仲介会社の方が『技術力や顧客基盤を考慮すれば、もっと高い評価を得られる可能性がある』と言ってくれたんです」
その後、複数の買い手候補との面談が始まりました。
M&Aにおけるトップ面談は「お見合い」に例えられるほど、経営者同士の相性が重要です。
「3社と面談しましたが、最終的に選んだ大手メーカーの社長は、私たちの技術について『素晴らしい』と何度も言ってくれました。単に安く買い叩こうとするのではなく、私たちの価値を認めてくれていることが伝わってきました」
交渉で最もこだわった「従業員の雇用維持」と、譲れなかった一線
価格交渉が本格化する中で、田中社長が最も重視したのは金額ではありませんでした。
「もちろん適正な価格は重要でしたが、それ以上に従業員の処遇について徹底的に話し合いました」
これは多くの経営者に共通する想いです。
中小企業庁の調査によると、売却・譲渡を検討する経営者の82.7%が「従業員の雇用維持」を重視しています [5]。
「最低3年間の雇用維持、現在の労働条件の維持、そして可能な限り昇進の機会も確保してほしいと要求しました。買い手企業は最初『2年間』と言っていましたが、粘り強く交渉して3年間で合意できました」
また、田中社長は会社のブランド名の存続についても強くこだわりました。
「25年間築き上げてきた会社の名前を残してほしいと伝えました。買い手企業は『子会社として独立性を保つ』と約束してくれました」
交渉の過程で、企業価値は当初の4億円から5億2000万円まで上昇しました。
「技術力の高さ、安定した顧客基盤、そして従業員のスキルレベルの高さを買い手企業が評価してくれた結果だと思います」
【高橋の視点】「企業価値」は財務諸表だけでは決まらない
田中社長のケースが示すように、企業価値は単純に財務諸表の数字だけで決まるものではありません。
特に中小企業の場合、以下の「見えない価値」が評価額を大きく左右することがあります。
1. 技術力・ノウハウ
長年蓄積された技術やノウハウは、財務諸表には現れませんが、買い手にとって大きな価値となります。
2. 顧客基盤・ブランド力
安定した顧客関係や地域でのブランド力は、将来の収益性を保証する重要な要素です。
3. 人材・組織力
優秀な従業員や組織文化は、M&A後の統合成功の鍵となります。
4. 立地・設備
好立地の工場や最新設備は、買い手の事業展開において戦略的価値を持ちます。
田中社長の会社が当初の評価額から30%以上高い価格で売却できたのは、これらの「見えない価値」を買い手企業が適切に評価したからです。
重要なのは、売り手側がこれらの価値を明確に言語化し、買い手に伝えることです。
「私たちの強みは何か」「なぜ買い手にとって価値があるのか」を論理的に説明できれば、適正な評価を得られる可能性が高まります。
すべてが決まった「決断の瞬間」とその後の心境
最後の決め手となった、買い手経営者の「未来へのビジョン」
条件面での合意が見えてきた段階で、田中社長の心を最終的に動かしたのは、買い手企業の社長が語った将来ビジョンでした。
「最後の面談で、相手の社長が『田中さんの会社の技術と、うちの全国販売網を組み合わせれば、もっと多くのお客様に価値を提供できる。一緒に新しい市場を開拓しましょう』と言ってくれたんです」
この言葉が、田中社長の決断を後押ししました。
「単に会社を買い取るのではなく、一緒に成長していこうという姿勢を感じました。私たちの技術が、より大きなステージで活かされる。それが何より嬉しかったです」
M&Aの成功要因を分析した調査では、PMI(Post Merger Integration:買収後統合)の検討を開始した企業ほど、M&Aの満足度が期待以上となった割合が高いことが分かっています [6]。
買い手企業の明確なビジョンと統合計画は、売り手にとって安心材料となるのです。
従業員へ。最終契約締結後に「自分の言葉」で伝えた日
基本合意書の締結後、田中社長が最も緊張したのは従業員への発表でした。
「情報漏洩のリスクを避けるため、従業員には最終契約が済むまで一切話せませんでした。その間、『社長の様子がおかしい』と心配をかけてしまったと思います」
最終契約締結の翌日、田中社長は全従業員を集めて説明会を開きました。
「皆さんの雇用と処遇を最優先に交渉しました。新しい会社でも、これまで以上に活躍の場が広がります」
田中社長の言葉に、従業員からは驚きの声とともに、安堵の表情が見られました。
「最初はショックを受けた従業員もいましたが、雇用が守られること、昇進の機会も確保されることを説明すると、『社長、ありがとうございます』と言ってくれる人もいました」
実際に、多くのケースでM&A実施後も売却側従業員の雇用が維持されているという調査結果があります [7]。
従業員にとってM&Aは、雇用の安定化や新たなキャリア機会の創出につながることが多いのです。
契約書にサインした時、感じたのは「安堵」と一抹の「喪失感」
最終契約書へのサインの瞬間について、田中社長はこう振り返ります。
「ペンを持つ手が震えました。25年間の人生が、この一筆で変わるんだと思うと、感慨深いものがありました」
契約書にサインした瞬間の心境は複雑でした。
「まず感じたのは安堵感でした。従業員の雇用が守られる、会社の技術が継承される、そして私自身も個人保証から解放される。長年の重荷が下りた感じでした」
一方で、喪失感も否定できませんでした。
「同時に、人生を賭けてきた会社を手放すという寂しさもありました。これは仕方のないことだと思います」
この複雑な感情は、多くの売却経験者が共有するものです。
M&Aによる事業承継について、8割以上の経営者が満足していると回答している一方で 、何らかの感情的な葛藤を経験することも事実です。
重要なのは、この感情を受け入れながらも、決断の正しさを信じることです。
会社売却後のリアルと、今、迷える経営者へのメッセージ
売却後の人生。悠々自適ではなく「新たな挑戦」を選択
M&A完了から1年が経過した現在、田中社長は完全に引退したわけではありません。
「買い手企業から顧問として残ってほしいと言われ、週3日ほど会社に通っています。後輩の指導や新規事業の立ち上げに関わらせてもらっています」
これは珍しいケースではありません。
M&Aによる譲渡を経験した経営者の36.2%が「役員として継続」しており、多くの経営者が何らかの形で事業に関わり続けています [8]。
「完全に引退するには、まだ早いと思っています。これまでの経験を活かして、若い世代の育成に貢献したいです」
また、田中社長は売却で得た資金の一部を使って、新たな事業への投資も検討しています。
「地元の若い起業家を支援するファンドに参加することを考えています。今度は投資家として、地域経済の発展に貢献したいです」
今、会社売却を考える経営者へ。「後悔しないために、情報武装を」
インタビューの最後に、田中社長から同じ立場の経営者へのメッセージをいただきました。
「M&Aを検討している経営者の方には、まず正しい情報を集めることをお勧めします。私も最初は不安でしたが、信頼できる専門家と出会えたことで、納得のいく結果を得ることができました」
田中社長が強調するのは、情報収集の重要性です。
「M&A仲介会社も、税理士も、弁護士も、それぞれ得意分野が違います。複数の専門家から話を聞いて、セカンドオピニオンを得ることが大切です」
また、従業員への配慮についても言及しました。
「従業員の処遇については、絶対に妥協しないでください。彼らの人生も背負っているという責任感を持って交渉に臨むべきです」
最後に、決断のタイミングについてアドバイスをいただきました。
「迷っているうちに、会社の価値が下がってしまうこともあります。早めに情報収集を始めて、選択肢を広げておくことが重要です」
【高橋の視点】「納得感のあるM&A」を実現するために
田中社長のインタビューから見えてくるのは、「納得感のあるM&A」を実現するための重要なポイントです。
1. 譲れない条件の明確化
金額だけでなく、従業員の処遇、会社の理念の継承など、自分にとって本当に重要なことを明確にすることが大切です。
2. 信頼できる専門家の選定
M&A仲介会社、税理士、弁護士など、それぞれの専門性を理解し、信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵となります。
3. 十分な情報収集と検討時間
急いで決断する必要はありません。十分な情報収集と検討時間を確保することで、後悔のない選択ができます。
4. 従業員への誠実な対応
従業員は会社の最も重要な資産です。彼らの処遇を最優先に考えることが、結果的に企業価値の向上にもつながります。
現在、M&Aによる事業承継について、売り手・買い手ともに5割以上の企業が満足しているという調査結果があります [8]。
しかし、満足度を高めるためには、適切な準備と専門家のサポートが不可欠です。
M&Aは単なる会社の売買ではありません。
経営者の人生、従業員の未来、そして会社が築いてきた価値を次の世代に継承する重要な決断です。
その決断が、関わるすべての人にとって最良の結果をもたらすよう、私たち専門家も全力でサポートしていきます。
よくある質問(FAQ)
Q: 会社売却の相談は、どのタイミングで誰にするのがベストですか?
A: 漠然と意識し始めた段階で、まずは利害関係のない中立的な専門家に相談することをお勧めします。
顧問税理士や金融機関も選択肢ですが、M&Aの知見が十分でない場合もあります。
複数の専門家から話を聞き、セカンドオピニオンを得ることが重要です。
早期の情報収集により、選択肢が広がり、より良い条件での売却が可能になります。
Q: 従業員の雇用や待遇は、本当に守られるのでしょうか?
A: 最終契約書に一定期間の雇用維持や労働条件の維持を盛り込むことが可能です。
実際に、売却・譲渡を検討する経営者の82.7%が「従業員の雇用維持」を重視しており、多くのケースで雇用が維持されています。
しかし、最も重要なのは買い手企業の経営方針や文化です。
交渉段階で、従業員を大切にする企業かどうかを徹底的に見極めることが、彼らの未来を守ることに繋がります。
Q: 自分の会社の「本当の価値」を知るにはどうすれば良いですか?
A: 企業価値評価には複数の手法があり、一概には言えません。
簡易診断は可能ですが、「本当の価値」は買い手候補との交渉の中で形成されます。
自社の強み(技術、顧客基盤、ブランドなど)を正しく言語化し、それを高く評価してくれる相手を見つけることが、価値を最大化する鍵となります。
財務諸表に現れない「見えない価値」も重要な評価要素です。
Q: 売却を決断した後、後悔することはありませんか?
A: 「もっと高く売れたのでは」「あの選択は正しかったのか」という思いがよぎる可能性はゼロではありません。
しかし、M&Aによる事業承継について、8割以上の経営者が満足していると回答しています。
後悔を最小限にするには、プロセスに納得感を持つことが重要です。
情報を尽くし、信頼できる専門家と相談し、考え抜き、最後はご自身で「決断」すること。
そのプロセス自体が、未来の自分を支えてくれます。
Q: M&A仲介会社はどのように選べば良いですか?
A: 手数料体系の透明性、実績、担当者との相性に加え、自社の業界や事業への理解が深いかどうかが重要です。
小規模M&Aの場合、仲介手数料の相場は売買価格の5%〜10%程度ですが、2024年からM&A支援機関登録企業の手数料が公表され、比較検討が容易になりました。
また、売り手と買い手の双方から手数料を得る「仲介」か、売り手の利益最大化を目指す「アドバイザリー」か、その立ち位置を理解することも大切です。
複数の会社から話を聞き、最も信頼できるパートナーを選択してください。
まとめ
5億円超での会社売却。
その華々しい結果の裏には、一人の経営者の、血の滲むような葛藤と孤独な闘いがありました。
今回のインタビューで明らかになったのは、M&Aの成否を分けるのが、単なる財務戦略や交渉術だけではないという事実です。
自社の未来をどう描くか、従業員の生活をどう守るか、そして自身の人生をどう歩むか。
その一つ一つの問いと真摯に向き合い、悩み抜いた先にこそ、「納得感のある決断」は待っています。
現在、中小企業のM&A件数は年々増加傾向にあり、2024年は前年比14%増と過去最多を更新しました。
しかし、件数の増加以上に重要なのは、一つ一つのM&Aが関わるすべての人にとって最良の結果をもたらすことです。
この記事が、今まさに岐路に立つあなたの心を照らす一筋の光となり、勇気ある一歩を踏み出すきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。
あなたの会社の価値を、そしてあなた自身の人生の価値を、最大化する選択をしてください。
情報を武器に、信頼できるパートナーと共に、納得のいく決断を下すことができれば、M&Aは単なる会社の売買を超えた、新たな価値創造の機会となるはずです。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。
参考文献
[1] 帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2024年)」2024年11月22日
[2] 「【2024年M&Aレポート】過去最多の1221件、17年ぶりに記録更新」2025年1月9日
[3] 「M&A手数料は高い?25社売り手向け比較!アドバイザリー」2025年6月2日
[4] 「中小企業の会社売却はM&Aの仲介手数料で比較しよう!」2024年11月6日
[5] 中小企業庁「第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用」2021年中小企業白書
[6] 経済産業省「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性」2024年6月28日
[7] 日本総合研究所「中小企業によるM&Aの現状と課題」2022年3月31日
[8] 「【12/10日は『M&Aの日』】M&Aによる譲渡を経験した経営者を対象とした調査」2024年12月10日



