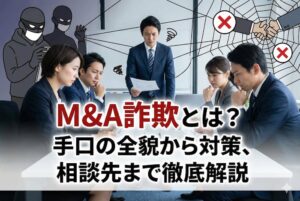会社売却、最高のタイミングはいつ?5億円超を目指す社長の決断ポイント
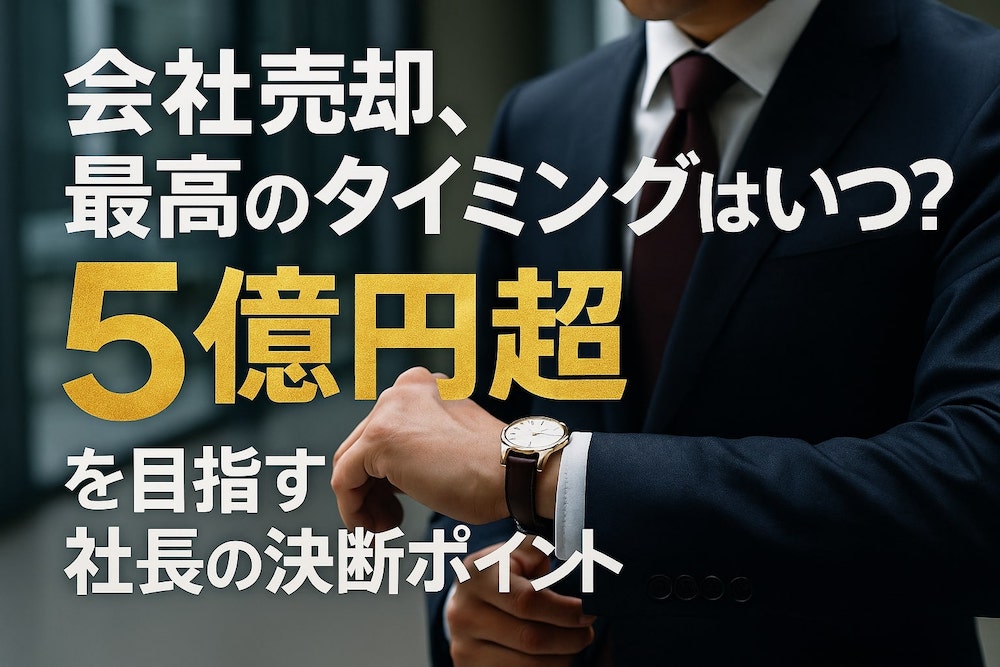
中小企業M&Aの最新動向から読み解く、後悔しない売却タイミングの見極め方と企業価値最大化の実践的戦略を、独立系M&Aコンサルタントが徹底解説
「会社は我が子同然。簡単に手放せるものではない。」
私が日々接する経営者の皆様から、必ずと言っていいほど聞かれる言葉です。
創業から苦楽を共にしてきた従業員、長年支えてくださった取引先、そして何より、血と汗と涙で築き上げてきた事業への深い愛着。
その想いの重さは、同じく中小企業経営者であった私の父を見て育った身として、痛いほど理解できます。
しかし同時に、「このままでは事業の未来が見えない」「後継者がいない」という不安の声も、年々大きくなっています。
実際、2025年には中小企業経営者の約245万人が70歳を超え、そのうち半数以上が後継者未定という深刻な状況を迎えます[1]。
では、どうすればよいのでしょうか?
本記事では、独立系M&Aコンサルタントとして年間50件以上の相談に対応してきた私の客観的な視点から、経営者が後悔しない決断を下すための「羅針盤」をお示しします。
特に、5億円超の売却を実現するために不可欠な「タイミングの見極め方」「企業価値の最大化」「具体的なステップ」を、専門用語を噛み砕きながら解説していきます。
まずは、なぜ今、会社売却を真剣に考えるべきなのか。
その背景から見ていきましょう。
なぜ今、会社売却を考えるべきか?中小企業M&Aの最新動向
増加するM&A件数と「売り手市場」の現実
「M&Aなんて、大企業の話でしょう?」
5年前なら、その認識も間違いではありませんでした。
しかし、状況は劇的に変化しています。
2024年の日本企業のM&A件数は4,700件と過去最多を更新し、前年比17.1%増という驚異的な伸びを記録しました。
さらに注目すべきは、中小企業のM&A成約件数が2012年から2017年の5年間で3倍超に急増している点です[2]。
この数字が意味することは何でしょうか?
それは、優良な中小企業に対する買い手の意欲が極めて高く、まさに「売り手市場」が形成されているということです。
私が最近支援した埼玉県の製造業(売上高8億円)のケースでは、買い手候補が10社も名乗りを上げ、最終的に当初想定の1.5倍の価格で成約に至りました。
特に、以下の業界では買い手企業の動きが活発です。
🗒 IT業界では、NTTデータが2025年度までにM&Aに1,000億円を投じる方針を発表。
人材不足と技術革新への対応から、優秀なエンジニアを抱える企業への投資意欲が高まっています。
🗒 介護業界では、2025年に34万人の人材不足が予測される中、ALSOKやベネッセHDなど異業種大手が続々と参入。
安定した顧客基盤を持つ介護事業者への需要が急増しています。
🗒 食品業界では、市場規模114兆円という巨大マーケットで、大手外食チェーンやPEファンド(プライベート・エクイティ・ファンド=投資ファンド)による買収が活発化。
すかいらーくHDは2025~2027年に3~5件のM&Aを計画しています。
経営者の決断を後押しする国の支援制度とは
「でも、M&Aって費用もかかるし、手続きも複雑そう…」
そんな不安を抱く経営者も多いでしょう。
実は、国もこの課題を重く見て、充実した支援制度を整備しています。
これらの制度を知っているかどうかで、M&Aの成功確率は大きく変わります。
事業承継・引継ぎ支援センターは、47都道府県すべてに設置された公的相談窓口です。
親族内承継から第三者への売却まで、あらゆる相談にワンストップで対応。
相談料は無料で、秘密も厳守されます。
さらに、事業承継・引継ぎ補助金では、M&Aにかかる専門家費用の一部が補助されます。
仲介手数料やデューデリジェンス(買収監査)費用など、通常なら数百万円かかる費用の負担が大幅に軽減されるのです。
ある経営者は「国がここまで支援してくれるとは思わなかった」と驚いていました。
確かに、これほど手厚い支援が受けられる今こそ、M&Aを検討する絶好の機会といえるでしょう。
5億円の壁を超える「会社売却の最高のタイミング」5つの見極めポイント
では、具体的にいつ売却すれば、5億円超の価値を実現できるのでしょうか?
私は「外部要因」と「内部要因」、そして「経営者要因」の3つの視点から、5つのチェックポイントを設けています。
【外部要因】市場が味方する時:業界再編と景気の波に乗る
①業界再編の波をつかむ
「なぜ今、うちの業界でM&Aが増えているんですか?」
IT企業の社長からよく聞かれる質問です。
答えは明確です。
ChatGPTに代表される生成AIの登場により、IT業界は大変革期を迎えているからです。
この技術革新の波に乗り遅れまいと、大手企業は優秀な技術者と先進技術を持つ中小企業の買収に動いています。
介護業界も同様です。
2024年度の介護報酬改定(1.59%プラス)を受け[3]、経営環境が改善。
大手企業にとって、今が優良事業者を獲得する好機となっています。
重要なのは、この波は永続しないということ。業界再編期は通常3~5年で一巡します。
タイミングを逃せば、買い手の意欲は急速に冷め、企業価値も下がってしまうのです。
②金融環境を味方につける
M&Aでは、買い手企業の多くが銀行融資を活用します。
つまり、金利が低く、銀行が融資に積極的な時期こそ、高値での売却が期待できるのです。
2024年現在、日銀の金融緩和政策により、企業向け融資は依然として低金利。
しかし、今後の金利上昇リスクを考えると、この好環境がいつまで続くかは不透明です。
【内部要因】会社の価値が頂点にある時:業績好調と成長ストーリー
③「もう一段の成長には大型投資が必要」という転換点
これは、私が「黄金の売り時」と呼ぶタイミングです。
ある食品製造業の社長は、こう話していました。
「売上は順調に伸びているが、次のステージに行くには新工場が必要。でも、10億円の投資は正直リスクが大きすぎる。」
まさにこの瞬間こそ、最高の売り時なのです。
なぜなら、買い手企業にとっては「成長余地が明確に見える優良企業」だからです。
果物に例えるなら、完熟の一歩手前。
まだ成長の余地を残しているからこそ、買い手は高い価値を認めるのです。
④3期連続の増収増益がもたらす説得力
企業価値の算定では、直近3期の業績が重視されます。
特に、3期連続で増収増益を達成している企業は、買い手から「安定成長企業」として高く評価されます。
逆に、1期でも赤字があると、企業価値は2~3割下がることも。
「来期は厳しそうだ」と感じたら、今期中の売却を真剣に検討すべきでしょう。
【経営者要因】社長の年齢と情熱:引き際を見誤らない勇気
⑤経営者の年齢による企業価値への影響
これは言いにくい話ですが、避けて通れない現実があります。
経営者が70歳を超えると、買い手企業の見る目は厳しくなります。
「後継者育成は間に合うのか」「健康面は大丈夫か」「変化に対応できるか」。
こうした不安が、企業価値の減少につながるのです。
私は経営者の引き際を、プロスポーツ選手の引退に例えています。
全盛期を少し過ぎたくらいで引退する選手は、惜しまれながら次のキャリアに進めます。
しかし、限界まで現役にこだわると、晩節を汚すことにもなりかねません。
60代前半から中盤。
体力・気力ともに充実し、新しいことにもチャレンジできる。
この時期の決断こそが、経営者にとっても、会社にとっても、最良の選択となることが多いのです。
企業価値を最大化する!5億円超を目指すための「磨き上げ」戦略
タイミングを見極めたら、次は企業価値を高める「磨き上げ」です。
これは、家を売る前のリフォームのようなもの。
適切な磨き上げで、企業価値は20~30%上昇することもあります。
財務の健全化:買い手が真っ先にチェックする3つのポイント
①社長への貸付金は必ず清算を
デューデリジェンス(買収監査)で真っ先に指摘されるのが、役員貸付金の存在です。
「社長が会社から借りているお金」は、買い手にとって大きなリスク要因。
できれば売却の1年前までに、完済または資本金への振り替えを済ませておきましょう。
②不要資産の整理で企業価値アップ
高級車、使っていない不動産、ゴルフ会員権…。
これらの「事業に直接関係ない資産」は、売却前に処分することをお勧めします。
なぜなら、これらは企業価値の算定から除外されることが多いからです。
ある製造業では、遊休不動産を3,000万円で売却し、その資金で老朽設備を更新。
結果的に、企業価値が5,000万円上昇しました。
③決算書3期分の準備と粉飾の排除
「少しくらいの粉飾なら…」という考えは、命取りになります。
私が見てきた破談案件の3割は、粉飾決算の発覚が原因でした。
むしろ、「過去に計上漏れがありました」と正直に申告する方が、信頼を得られます。
清廉潔白な決算書3期分。
これが、5億円超の売却への第一歩です。
事業の強みを可視化する:無形資産の価値を伝える技術
独自技術・ノウハウの「見える化」
「うちには特別な技術なんてない」
そう謙遜する社長も多いのですが、本当にそうでしょうか?
ある金属加工業の社長も同じことを言っていました。
しかし、詳しく聞いてみると、不良品率が業界平均の10分の1。
これは、30年かけて磨き上げた品質管理ノウハウの賜物でした。
このノウハウを「品質管理マニュアル」として文書化し、教育プログラムも整備。
結果、当初提示額の1.8倍で売却に成功しました。
優良顧客基盤の価値証明
「お客様との信頼関係」も、立派な資産です。
取引年数、リピート率、顧客単価の推移。
これらのデータを整理し、「なぜお客様に選ばれ続けているのか」を明確に説明できるようにしましょう。
特に、大手企業との長期取引実績は、企業価値を大きく押し上げる要因となります。
「株式譲渡」か「事業譲渡」か?自社に最適な売却手法の選び方
M&Aの手法選びは、税金面で数千万円の差が生じることもある重要な決断です。
それぞれの特徴を、具体例を交えて解説します。
シンプルで税務上有利な「株式譲渡」
株式譲渡は、会社の株式を丸ごと買い手に売却する方法です。
最大のメリットは、税制面での優遇です。
ただし、2025年1月からは要注意です。
年間所得3.3億円を超える部分については、最大27.5%まで税率が上昇する「ミニマムタックス」が導入されます。[4]
5億円の売却なら3.3億円以下なので従来通りですが、それ以上の大型案件では増税の影響を受けることになります。
手続きの簡便さも大きな利点です。
株主名簿の書き換えと、法務局への役員変更登記。
基本的にはこれだけで、経営権の移転が完了します。
一方、注意点もあります。
簿外債務(帳簿に載っていない債務)も含めて、すべてが買い手に引き継がれること。
だからこそ、事前の財務整理が重要なのです。
必要な事業だけを売却できる「事業譲渡」
事業譲渡は、会社の中の特定事業だけを切り出して売却する方法です。
不採算部門を手元に残し、優良部門だけを高値で売却できるメリットがあります。
私が支援した飲食チェーンでは、好調な居酒屋事業だけを事業譲渡で売却。
不振のカフェ事業は自社で立て直し、2年後に別の買い手に売却しました。
このように、戦略的な売却が可能になります。
ただし、税務面では不利になることが多いです。
どちらを選ぶべきか?
私は「迷ったら株式譲渡」とアドバイスしています。
特別な事情がない限り、シンプルで税務上有利な株式譲渡が、5億円超を目指す経営者には適しているでしょう。
失敗しないM&Aの進め方:専門家と歩む8つのステップ
M&Aは、登山に似ています。
適切なガイド(専門家)と共に、一歩一歩着実に進めることが成功への近道です。
ここでは、実際の流れを8つのステップで解説します。
ステップ1〜4:準備から交渉開始まで
ステップ1:相談・準備(1~2ヶ月)
まずは、信頼できる専門家への相談から始まります。
事業承継・引継ぎ支援センターなら無料で相談でき、中立的なアドバイスが受けられます。
この段階で重要なのは、「なぜ売却するのか」という目的の明確化。
「従業員の雇用を守りたい」「事業を発展させたい」「老後資金を確保したい」。
目的によって、選ぶべき買い手も変わってきます。
ステップ2:仲介会社との契約(2週間程度)
仲介会社選びは、医者選びと同じくらい重要です。
手数料の安さだけで選ぶと、後で後悔することになりかねません。
チェックポイントは3つ。
- 業界知識が豊富か
- 過去の成約実績は十分か
- 担当者との相性は良いか
特に③は軽視されがちですが、半年以上の長い付き合いになるため、実は最も重要です。
ステップ3:買い手候補の探索(1~3ヶ月)
企業名を伏せた「ノンネームシート」で、買い手候補にアプローチします。
「関東地方の食品製造業、売上10億円、営業利益率8%」といった概要情報だけで、意外なほど多くの問い合わせが来ることがあります。
最近では、平均10社程度の買い手候補が手を挙げるケースが増えています。
選択肢が多いことは良いことですが、すべてと面談するわけにはいきません。
仲介会社と相談しながら、3~5社に絞り込みます。
ステップ4:トップ面談・条件交渉(1~2ヶ月)
いよいよ買い手候補との面談です。
この「お見合い」は、M&Aの成否を左右する重要な場面。
私がいつもアドバイスするのは、「等身大の自分を見せること」。背伸びをしても、後でボロが出ます。
むしろ、課題も含めて正直に話す方が、信頼関係が築けます。
条件交渉では、価格だけでなく、従業員の処遇、社名やブランドの扱い、自身の処遇なども重要。
「社長には最低2年は残ってほしい」という要望も多いので、心の準備をしておきましょう。
ステップ5〜8:最終契約から統合プロセスへ
ステップ5:基本合意(2週間程度)
双方の意向が固まったら、基本合意書を締結します。
これにより、買い手には一定期間の「独占交渉権」が与えられます。
基本合意は、いわば「仮契約」。
まだ引き返すことは可能ですが、ここからは本格的な調査が始まります。
ステップ6:デューデリジェンス(1~2ヶ月)
デューデリジェンス(買収監査)は、M&Aの「健康診断」です。
財務、法務、事業、人事など、あらゆる角度から企業を調査されます。
準備すべき主な資料は以下の通りです。
- 財務:決算書・税務申告書(3~5年分)、売掛・買掛明細、在庫明細、固定資産台帳
- 法務:定款、株主名簿、重要契約書、許認可証
- 人事:従業員名簿、組織図、就業規則、給与台帳
- 事業:事業計画書、顧客リスト、競合分析資料
多くの経営者が「こんなに調べられるのか」と驚きますが、これは買い手の「転ばぬ先の杖」。
むしろ、徹底的に調査してもらった方が、後のトラブルを防げます。
ステップ7:最終契約締結(2週間程度)
デューデリジェンスで大きな問題がなければ、いよいよ最終契約です。
株式譲渡契約書は、通常50ページを超える大部なもの。
弁護士のサポートを受けながら、一つ一つ確認していきます。
特に重要なのは「表明保証条項」。
これは、売り手が買い手に対して「隠れた債務はありません」「重要な契約はすべて開示しました」と保証するものです。
後で虚偽が発覚すれば、損害賠償請求される可能性もあるため、慎重な確認が必要です。
ステップ8:クロージング(1ヶ月程度)
契約締結から実際の株式譲渡・代金決済までを「クロージング」と呼びます。
この期間に、従業員への発表、取引先への通知、各種名義変更などを行います。
従業員への発表は、特に神経を使う場面です。
「会社が売られた」というネガティブな受け止め方をされないよう、「なぜこの選択をしたのか」「従業員にとってどんなメリットがあるのか」を丁寧に説明する必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q: 会社売却の相談から成立まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 一般的には6ヶ月~1年半が目安です。
ただし、これはあくまで平均的な期間。
買い手がすぐに見つかり、3ヶ月で成約したケースもあれば、理想の買い手を待って2年かけたケースもあります。
重要なのは、焦らないこと。
「今月中に売りたい」という切羽詰まった状況では、足元を見られ、安値での売却になりかねません。
余裕を持った計画が、良い条件での成約につながります。
Q: 仲介会社への手数料は、どのくらいかかりますか?
A: 成功報酬型が一般的で、「レーマン方式」という計算方法が用いられます。
売却額5億円の場合、5億円×5%=2,500万円が目安となります。
「高い!」と感じるかもしれませんが、考えてみてください。
適切な買い手を見つけ、交渉をまとめ、複雑な手続きをすべて代行してくれる。
その対価として、また、より高い売却価格を実現するための投資として、多くの経営者が納得されています。
最近は着手金無料の会社も増えており、成約しなければ費用はかかりません。
まずは相談してみる価値はあるでしょう。
Q: 従業員の雇用はどうなりますか?
A: 株式譲渡の場合、会社の法人格はそのまま維持されるため、雇用契約も原則として継続されます。
つまり、従業員から見れば、社長が変わるだけで、自分たちの立場は変わりません。
むしろ、多くの場合、買い手企業は従業員を「貴重な財産」と考えています。
なぜなら、その会社の事業を支えてきたのは、他ならぬ従業員だからです。
私の経験では、M&A後に給与や福利厚生が改善されたケースの方が多いです。
大手企業の傘下に入ることで、研修制度が充実したり、昇進の機会が広がったりすることもあります。
ただし、こうした条件は契約書に明記することが大切。
「向こう3年間は、従業員の雇用条件を維持する」といった条項を入れることで、従業員の不安を取り除くことができます。
Q: 5億円で売却できた場合、手取りはいくらになりますか?
A: 株式譲渡でオーナー個人が対価を受け取る場合の試算をしてみましょう。
売却額:5億円
仲介手数料:▲2,500万円(レーマン方式5%)
差引:4億7,500万円
この4億7,500万円に対して、譲渡所得税がかかります。
2024年中の売却なら、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)。
4億7,500万円×20.315%=約9,650万円
最終手取り:4億7,500万円-9,650万円=約3億7,850万円
なお、2025年以降は年間所得3.3億円超の部分に増税される可能性がありますが、5億円の売却なら影響は限定的です。
この手取り額を見て、「思ったより少ない」と感じる方もいるでしょう。
しかし、一代で3億円超の資産を築けたことは、立派な成功です。
この資金を元に、新たな事業にチャレンジする経営者も多くいます。
まとめ
ここまで、会社売却の最適なタイミングと、5億円超を実現するための具体的な方法をお伝えしてきました。
改めて、「最高のタイミング」とは何かを整理しましょう。
それは、市場環境(業界再編、金融環境)、会社の状態(業績、成長余地)、経営者個人の状況(年齢、意欲)の3つの要因が、最も良い形で重なった瞬間です。
2024年のM&A件数が過去最多を更新し、各業界で大手企業の買収意欲が高まっている今。
そして、国の支援制度が充実し、金融環境も良好な今。
まさに、千載一遇のチャンスが訪れているといえるでしょう。
しかし、このタイミングを活かせるかどうかは、準備次第です。
財務の健全化、強みの可視化、適切な専門家の選定。
これらの準備には、少なくとも半年から1年はかかります。
「まだ早い」と思っているうちに、気づけば手遅れになっている。
これが、私が見てきた多くの失敗例に共通するパターンです。
一方で、早めに準備を始め、余裕を持って交渉に臨んだ経営者は、想定以上の好条件で会社を託すことができています。
そして何より、従業員も取引先も、経営者自身も、全員が前を向いて新しいスタートを切れています。
会社売却は、決して「敗北」ではありません。
むしろ、会社を次のステージに導き、関わるすべての人に新たな可能性をもたらす「英断」なのです。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。
参考文献
[1] 中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題
[2] M&Aの現状
[3] 24年度報酬改定 プラス1.59で決着 1月に新報酬案
[4] グローバル・ミニマム課税とは(パンフレット等)|国税庁