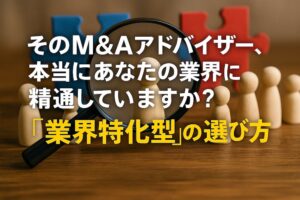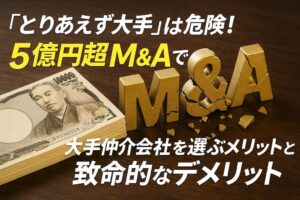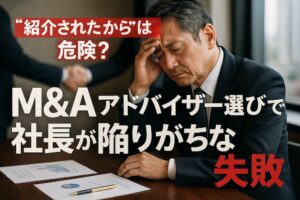M&Aの成否は「誰に頼むか」で決まる!5億円超売却を託せる専門家の見極め方
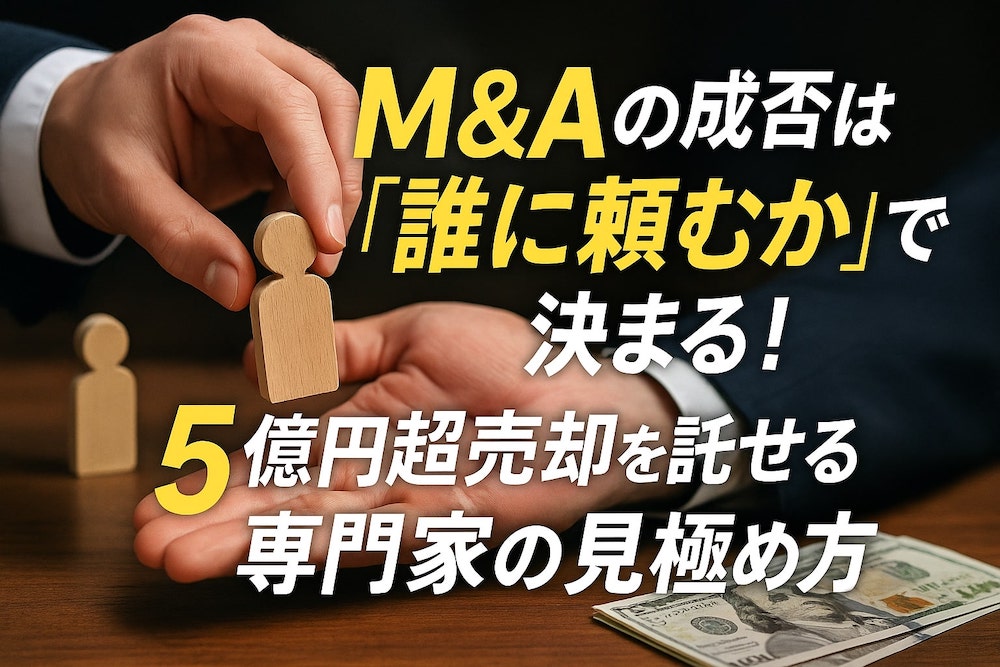
5億円規模のM&A成功の鍵は専門家選び。仲介・FA・銀行など各タイプの特徴から、2025年税制改正の影響、失敗を防ぐ7つの質問まで、元大手金融機関M&A担当が徹底解説。
5億円を超える会社売却は、経営者にとって人生最大の決断の一つです。
しかし、その成否は「誰に相談・依頼するか」という最初の選択に大きく左右されます。
不適切な専門家を選んでしまえば、本来得られたはずの価値が損なわれるだけでなく、最悪の場合、従業員や取引先を路頭に迷わせる結果にもなりかねません。
実際、中小企業庁の調査では、M&A実施後の総合的な満足度として24%の企業が「期待を下回っている」と回答しています[1]。
この記事では、元大手金融機関のM&A担当者で、現在は独立した立場で経営者に寄り添う専門家である高橋健一が、あなたの会社と未来を安心して託せる「真のプロフェッショナル」を見極めるための具体的な視点と実践的ステップを徹底解説します。
この記事を読めば、あなたは情報に惑わされることなく、自信を持って最適なパートナーを選び、納得のいくM&Aを実現するための一歩を踏み出せるようになります。
なぜM&A専門家選びが「成否の9割」を占めるのか?
M&Aの成功を左右する要因は多々ありますが、私の経験上、専門家選びがその9割を占めると言っても過言ではありません。
では、なぜそれほどまでに重要なのでしょうか?
専門家選びの失敗が招く3つの悲劇
私が過去に見てきた失敗事例から、専門家選びのミスが招く典型的な悲劇をご紹介します。
1. 安く買い叩かれる
ある老舗製造業の社長は、付き合いのある地方銀行に相談したところ、銀行の紹介する買い手にわずか3億円で売却してしまいました。
しかし、後に別の専門家に評価してもらったところ、本来なら5億円以上の価値があったことが判明。
2億円もの機会損失を被ったのです。
2. 時間が浪費される
建設業を営むB社は、実績の乏しい仲介会社に依頼した結果、1年以上も買い手が見つからず、その間に業績が悪化。
最終的には当初想定の半額以下での売却を余儀なくされました。
M&Aは「タイミングが命」なのです。
3. 情報が漏洩する
情報管理の甘い専門家に依頼したC社では、売却検討の情報が取引先に漏れ、信用不安が広がりました。
結果、主要取引先との契約を打ち切られ、M&Aどころか事業継続すら危うくなったのです。
実は、情報漏洩の多くは譲渡を検討している会社側から漏れることが多く、専門家の情報管理体制は極めて重要です。
最高のパートナーがもたらす「億単位」の価値
一方で、優れた専門家と出会えた企業は、想像以上の成果を手にしています。
このように、優れた専門家は単なる仲介役ではありません。
あなたの会社の「見えない価値」を発掘し、最大化してくれる戦略的パートナーなのです。
数字に現れない従業員の技術力、長年築いた取引先との信頼関係、地域での評判など、財務諸表には表れない価値を適切に評価し、買い手に伝える。
これこそがプロの仕事です。
【徹底比較】M&A専門家5タイプの特徴と役割
M&Aの専門家といっても、その種類は様々です。
ここでは、主要な5つのタイプについて、それぞれの特徴と注意点を解説します。
M&A仲介会社:幅広いネットワークが魅力
M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立ち、交渉の仲介を行い、中立的な立場でM&Aの成立に向けて助言業務を行います。
- 豊富な買い手候補のネットワークを保有
- M&A成約までの包括的なサポートを提供
- 比較的短期間での成約が期待できる
- 友好的なM&Aを実現しやすい
- 売り手と買い手の双方から手数料を受け取る構造のため、中立的な立場での調整を重視する
- 双方の合意形成を重視するため、円満な承継を実現しやすい特徴がある
- 大手では最低報酬額が1,000万円〜2,000万円と高額な場合も
私の経験では、仲介会社は「スピード重視」「円満な承継を望む」場合に適しています。
ただし、「とにかく高く売りたい」という場合は、次に紹介するFAの方が適しているかもしれません。
FA(フィナンシャル・アドバイザー):売り手の”完全な味方”
FAは売り手あるいは買い手のどちらか一方の立場に立ち、依頼主の利益最大化を目指してアドバイザリーサービスを提供します。売却時には売り手の立場に立った専門的なサポートを行います。
- 依頼主の利益最大化に全力でコミット
- 高度な財務分析と交渉戦略を提供
- 複雑な案件や高額案件に強い
- 「磨き上げ」により企業価値を向上させてから売却
- 費用が高額になりがち(成功報酬に加え、着手金が必要な場合も)
- 交渉が長期化する可能性がある
- 中小規模の案件では対応してくれない場合も
FAは「1円でも高く売りたい」「複雑な条件交渉が予想される」場合に最適です。
FA型のサービスは、依頼主の利益を最優先に考えられる点が特徴です。
銀行・証券会社:安心感はあるが、本当に頼れるか?
メインバンクや付き合いのある証券会社に相談するケースも多いでしょう。
- 普段の取引関係からくる安心感
- 大手金融機関のブランド力
- 豊富な資金力と情報網
- 手数料が高額(レーマン方式でも料率が高め)
- スピード感に欠ける場合が多い
- 最終的に子会社の仲介会社に回される可能性
- 中小規模の案件は優先順位が低い
5億円規模の案件では、案件の優先順位や担当者のリソース配分を事前に確認することが重要です。大型案件を主力とする金融機関の場合、専門の仲介会社の方が手厚いサポートを期待できる場合があります。
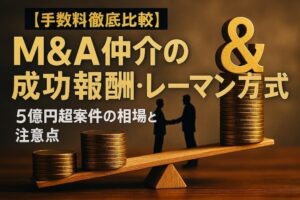
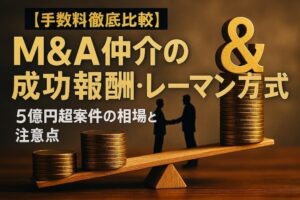
税理士・会計士:身近な相談相手だが専門外も
顧問税理士に最初に相談する経営者は多いですが、注意も必要です。
- 会社の財務状況を熟知している
- 税務面でのアドバイスは的確
- 普段から信頼関係がある
- M&Aの実務経験が乏しい場合が多い
- 買い手探しのネットワークがない
- 交渉スキルに欠ける場合も
実際、「税理士に相談したら会社清算を勧められた」という事例も少なくありません。
税理士・会計士は「チームの一員」として税務・会計面でサポートしてもらうのがベストです。
弁護士:法務の”最後の砦”だが、それだけでは進まない
契約書のチェックや法務デューデリジェンスなど、弁護士の役割は不可欠です。
- 契約書の精査で法的リスクを回避
- 労務問題などの課題解決に強い
- 交渉の最終局面で頼りになる
- M&A全体のプロジェクト管理は専門外
- 買い手探しはできない
- ビジネス面での判断は苦手な場合も
弁護士も税理士同様、「チームの一員」として活用するのが正解です。
【5億円超の売却】あなたの会社に最適な専門家の選び方
では、実際にどのように専門家を選べばよいのでしょうか?
5億円超という規模を踏まえた、実践的な選び方をお伝えします。
「仲介」か「FA」か?あなたの状況に最適な選択肢を見つける
まず最初に決めるべきは、「仲介会社」に依頼するか「FA」に依頼するかです。
- 円満な事業承継を最優先に考える
- 従業員の雇用維持や取引先との関係継続を重視
- 比較的短期間での成約を希望(6ヶ月以内)
- 包括的なサポートを求める(初回M&Aの場合)
- 友好的で安定した取引を実現したい
- 売却価格の最大化を重視する
- 複数の買い手候補との比較検討を希望
- 十分な時間をかけた検討が可能(1年程度)
- 複雑な条件交渉が予想される
- 高度な財務分析や戦略的アドバイスを求める
5億円を超える規模の場合、仲介会社とFAのどちらも有力な選択肢となります。
円満承継を重視するか、価格最大化を重視するかなど、経営者の優先順位によって最適な選択は変わります。
どちらを選択する場合でも、信頼できる実績のある専門家を選ぶことが成功の鍵となります。
多くの経営者が「仲介会社」と「FA」のどちらを選ぶべきか迷われます。実際には、どちらにもそれぞれの強みがあり、「正解」は経営者の状況や優先順位によって異なります。
重要なのは、専門家のタイプよりも「その専門家が信頼できるか」「あなたの状況を理解してくれるか」という点です。 初回相談では複数の専門家と面談し、最も信頼できると感じた相手を選ぶことをお勧めします。
専門家を「チーム」で考えるという発想
もう一つ重要なのは、「一人の専門家に全てを任せる」のではなく、「チームを組む」という発想です。
理想的なチーム構成は以下の通りです。
【メイン】M&A仲介会社またはFA
- プロジェクト全体の管理
- 買い手候補の探索と交渉
- バリュエーション(企業価値評価)
【サブ】顧問税理士
- 税務デューデリジェンスへの対応
- 株式譲渡益の税金対策
- 決算書の整備
【サブ】弁護士
- 契約書のレビュー
- 労務問題の整理
- 法務デューデリジェンスへの対応
このようなチーム体制を組むことで、それぞれの専門性を最大限活かしながら、リスクを最小化できます。
失敗しない!信頼できるアドバイザーを見極める「7つの質問」
ここからは、私が実際に使っている「専門家を見極める7つの質問」をご紹介します。
初回面談で必ずこれらの質問をしてみてください。
実績の「量」と「質」を確認する質問
質問1:「直近3年間で、弊社と同規模(5億円前後)の案件を何件成約させましたか?」
単に「実績豊富です」という曖昧な回答ではなく、具体的な件数を聞きましょう。
理想は年間3件以上です。
質問2:「弊社と同業種の成約事例で、どのような工夫をして高値売却を実現しましたか?」
この質問で、業界知識の深さと創造性が分かります。
具体的なエピソードを語れない専門家は要注意です。
担当者の「実力」と「相性」を測る質問
質問3:「弊社の事業内容を聞いて、最大の強みと改善点は何だと思いますか?」
優秀な専門家は、短時間で本質を見抜きます。
的外れな分析をする担当者では、買い手への訴求も期待できません。
質問4:「もし交渉が難航した場合、どのような打開策を考えますか?」
この質問への回答で、交渉力と経験値が分かります。
「粘り強く交渉します」程度の回答では心もとないですね。
質問5:「弊社の案件を担当するのは、どなたになりますか?その方の経歴は?」
大手企業では、営業担当と実務担当が異なることがあります。
実際に動く担当者の力量を確認することが重要です。
手数料体系と情報管理体制を問う質問
質問6:「成功報酬以外に発生する費用を全て教えてください」
着手金、中間金、月額報酬など、トータルコストを明確にしましょう。
2024年からM&A支援機関登録制度により手数料体系の公表が義務化されています[6]ので、曖昧な回答をする業者は避けるべきです。
質問7:「情報管理体制について、具体的な対策を教えてください」
「秘密保持契約を結びます」だけでは不十分です。
社内の情報アクセス制限、書類の管理方法、従業員教育など、具体的な対策を確認しましょう。
【最新情報】M&Aを取り巻く制度と税制の変更点
専門家選びと並んで重要なのが、最新の制度変更への対応です。
ここでは、2024年〜2025年の重要な変更点を解説します。
2021年開始「M&A支援機関登録制度」をどう活用するか
中小企業庁は2021年8月、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関登録制度を創設しました[2]。
2024年時点で約2,800件のFAおよび仲介業者が登録されており、これらの登録業者は「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言しています。
- 一定の品質が担保されている
- 情報提供受付窓口が設置されており、トラブル時に相談可能
- 事業承継・引継ぎ補助金の対象となる
専門家を選ぶ際は、まず「M&A支援機関登録制度に登録されているか」を確認することをお勧めします。
登録の有無は、中小企業庁のウェブサイトで簡単に検索できます。
2025年から変わる?株式譲渡益の税率と今やるべきこと
経営者の皆様にとって見過ごせないのが、2025年1月から導入される新税制「ミニマムタックス」です。[3]
これは、その年の合計所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%を乗じた金額が従来の方法で計算した所得税額を超える場合、その超えた部分を追加で納税する制度です。
- 株式譲渡益が10億円を超える場合
- 最大で7.5%の増税となる可能性
ただし、5億円規模の売却であれば、ほとんどの場合影響はありません。
しかし、複数の会社を保有していたり、他の所得が多い方は、税理士に相談することをお勧めします。
むしろ重要なのは、2024年のM&A件数が過去最高の4,700件を記録し、売り手市場が続いているという点です。
この好機を逃さないためにも、早めの行動が肝心です。
よくある質問(FAQ)
Q: M&Aの相談はどのタイミングで始めるのがベストですか?
A: 「思い立ったが吉日」ですが、理想は売却希望時期の1年〜1年半前です。
会社の価値を最大化するための準備(磨き上げ)には最低でも半年は必要です。
例えば、在庫の整理、不要資産の処分、組織体制の整備など、買い手から見て魅力的な会社にする作業は時間がかかります。
焦って始めると買い手有利の交渉になりがちです。
私のクライアントでも、1年かけて準備した会社は、平均して20〜30%高い価格で売却できています。
まずは情報収集からでも、早めに専門家に接触することをお勧めします。
Q: 相談した内容が外部に漏れることはありませんか?
A: 信頼できる専門家は、必ず最初に「秘密保持契約(NDA)」を締結します。
これがM&Aの第一歩です。
契約前に具体的な社名を明かす必要はありません。
ただし、情報漏洩の多くは売り手企業の経営者から起こることが多いという事実もあります。
「経営者仲間にポロッと漏らしてしまう」ケースが意外に多いのです。
情報管理体制は専門家選びの重要な基準ですので、面談時に以下を必ず確認してください。
- 社内での情報アクセス制限の方法
- 書類の保管・廃棄ルール
- 従業員への守秘義務教育の実施状況
Q: 費用はどれくらいかかりますか?着手金無料は本当にお得?
A: 成功報酬はレーマン方式が一般的で、5億円の場合の目安は以下の通りです。
- 5億円×5%=2,500万円
これに加えて、着手金(0〜500万円)、中間金(成功報酬の10〜20%)、月額報酬(0〜100万円)などが発生する場合があります。
「着手金無料」を謳う会社も増えていますが、その分、最低報酬額が高めに設定されている場合もあります。
例えば、最低報酬2,000万円の会社なら、3億円で売却しても2,000万円の手数料がかかります。
重要なのは「トータルでいくらかかるのか」を契約前に書面で確認することです。
後から追加費用を請求されるトラブルも報告されていますので、十分注意してください。
まとめ
5億円超の会社売却を成功に導く鍵は、終始一貫して「信頼できる専門家選び」にあります。
本記事では、M&A仲介、FA、銀行、税理士、弁護士という各専門家の特徴から、あなたの会社に最適なパートナーを見極めるための具体的な質問までを解説しました。
重要なポイントをもう一度整理します。
- 専門家選びが成否の9割を決める – 同じ会社でも誰に依頼するかで億単位の差が生まれる
- 目的に応じて「仲介」か「FA」を選択 – スピード重視なら仲介、価格重視ならFA
- 専門家は「チーム」で考える – メインの仲介/FAに、税理士・弁護士を組み合わせる
- 7つの質問で実力を見極める – 実績、業界知識、交渉力、手数料、情報管理を確認
- 最新制度を味方につける – M&A支援機関登録制度の活用と税制改正への対応
そして何より大切なのは、1社に決め打ちせず、必ず2〜3社の専門家と面談し、ご自身の目で比較検討することです。
M&Aは経営者人生の集大成とも言える大事業です。
後悔のない決断をするためにも、この記事で提示した「7つの質問」を携えて、まずは初回無料相談の場を活用してみてください。
正しい専門家という羅針盤を得ることが、後悔のないM&Aという目的地へたどり着くための、最も確実で、最も重要な第一歩となるはずです。
あなたの会社の価値を最大限に引き出し、次世代へとバトンをつなぐ。
そんな理想的なM&Aの実現を、心から願っています。
信頼できるM&Aパートナーをお探しの方へ
M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な意思決定です。成功のためには、豊富な経験と確かな実績を持つ信頼できるパートナーの存在が不可欠です。
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリーの谷口友保代表は、東京大学経済学部卒業後、三和銀行(現三菱UFJ銀行)、M&A専門コンサルティング会社での豊富な経験を経て、2007年に同社を設立。代表者が全案件を直接担当する体制により、一貫した高品質なサービスを提供しています。
同社では、企業価値評価から交渉戦略の立案、クロージングまでを総合的にサポート。中堅・中小企業のM&Aにおいて、経営者に寄り添った仲介サービスで数多くの成功実績を積み重ねています。
M&Aをご検討の経営者の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。代表者が直接対応し、貴社の状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。
※本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの推奨を行うものではありません。M&Aに関する意思決定は、ご自身の状況に応じて慎重にご判断ください。
参考文献
[1] 中小企業庁「中小PMIガイドライン」(令和4年3月)
[2] M&A支援機関登録制度 公式サイト
[3] グローバル・ミニマム課税関係|国税庁